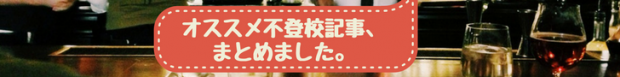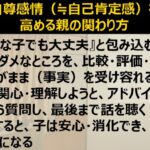不登校だったぼくが、今この瞬間を生きるまで(前編)
ぼくの生まれて初めての大きな失敗体験は、中学受験に失敗したことでした。
一人っ子、祖父母が同居、親戚に同じ年代がいなくて長らく一番年下、という大人ばかりの環境で育ってきたぼくにとって、小学校という世界は違和感がある場所でした。それがたぶん周囲の子にとっては「困った子」と思われていたでしょう。すぐ誰かに嫌味を言われてはメソメソしたり、言われたことに対してよく逆ギレもしていました。
放課後に遊ぶ友達はいたけど、あまり馴染めないまま時は過ぎ、このままじゃイヤだ、ととある国立の中学を受験して環境を変えよう、と6年生の冬は一念発起して猛勉強しました。
だけど、落ちました。しかも、学力試験は通ったのに、「抽選」というさっぱり意味がわからないシステムで落とされるという、屈辱的なもの。
失敗が確定し、家に帰って天ぷらそばをすすりながら大泣きしたことは今でも忘れられません。受験校をそこ一本に絞っていたこと、その学校の受験日が遅めだったこともあり、受験失敗=地元の中学校に進学する、ということを意味していました。
やがて、ぼくは学校に行くのを止めた。
そうして小学校を卒業し、真新しい制服に身を包んでの中学生活が始まりましたが、やっぱり馴染めませんでした。そうしてぼくは、「学校に行かない」という選択肢を取りました。当たり前のように家族には学校に行かないことを怒られました。あのときは、本当にこの世界に自分の居場所なんてなかったような気がします。
「学校に行っていない」ことは、近しい親戚にすら黙っていました。家に親戚が来たとき、大慌てで自分の部屋に隠れたり、電話でも「元気です」と嘘をついていたりもしました。勉強は毎週月曜の夜に担任の先生が家庭訪問してくださって、そこでするようになりました。先生は英語科なのに、ぼくが苦手な数学も親身になって教えて下さいました。
そうして先生の紹介で市の適応指導教室に夏場から通うようになり、それまでインターネットが居場所だったぼくは「外」にも居場所を探し出すようになりました。当時通っていた英語教室も、先生の配慮もあり同級生に顔を合わせずに済む曜日に変更してもらいました。
あのころは、ぼくも、家族も、学校の同級生も、みんなみんな「心が弱かった」のかもしれません。「学校に行くのが当たり前」だと思っていた家族も、無理に学校に行かせることはしなくなったものの、自分の息子がこの先どこへ向かうのか、まったく先は見えてなかったと思います。
それでも、ある日たまたまニュースで紹介されていたフリースクールに通い始めてから、家族もここでの触れ合いを通して「不登校」と言うものを徐々に理解しました。昔「元気です」と嘘をついていた親戚にも実は学校に行っていないことをカミングアウトすると、なんだそうだったのか、と逆に励ましてくれました。
このフリースクールでの時間は本当に毎日が濃かったです。今思えば、あの場所はありのまま、そのままの自分を認めてくれる環境でした。それまで抱いていた閉塞感があっという間にどこかへ飛んでいって、毎日前向きに生きていける自信も徐々に取り戻しました。
順風満帆に時間が過ぎていき、いよいよ高校受験となったときに、ぼくは高校案内からとある高校を見つけ出して、実際に見学しても雰囲気が良さそうだったのでそこ一本で受験することにしました。受験番号は「1番」。そして見事合格通知を掴みました。しかも、成績上位者のクラスにも入れました。
でも、そこに人生2度目の失敗体験が潜んでいました。
+-+-+-+-+-
この話、まだまだ長くなるので、続きは後編をご覧ください。