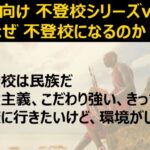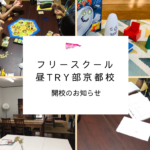不登校は「防ぐもの」なのか

ずっと疑問に思っていたことがあります。
それは、例えば不登校の子供たちが増えているという新聞記事で「不登校の生徒数過去最悪」などと書かれたり、「不登校の生徒の増加に歯止めをかけるべく対策が必要だ」などという論調の新聞記事があること。
「不登校は悪いことなのか?」という疑問に関しては以前コラムを書きました(最近気になる教育ニュースVol.2―不登校は「悪」なのか?)。そんな折、1月末に新たに不登校となった小中学生が6万5000人いるという調査結果が報じられました。
この記事で、ものすごーく引っかかったのが、「不登校を未然に防ぐ」という表現。
Shun on X (formerly Twitter): “そもそも不登校を「防ぐ」という認識から改めるべき。いい加減不登校は悪いものというレッテル貼るの勘弁してほしい。 / “新たに不登校になった小中学生6.5万人 2014年度:朝日新聞デジタル” https://t.co/GxbaTe4Zcu / X”
そもそも不登校を「防ぐ」という認識から改めるべき。いい加減不登校は悪いものというレッテル貼るの勘弁してほしい。 / “新たに不登校になった小中学生6.5万人 2014年度:朝日新聞デジタル” https://t.co/GxbaTe4Zcu
こんな意見を個人のTwitterで出したところ、えらくリツイートされて驚きました。
不登校は防いだってどうしようもない
不登校を防ぐ、ということはつまりできるかぎり子どもたちを学校に通わせるということになると思います。もちろん、少しのアプローチや配慮でやる気を取り戻したり、学級に復帰できる例もあると思いますが、そうは簡単に行きません。
例えば学校と言う環境そのものが苦手な場合、どうすれば学校に行けるようになるのでしょうか。あの学習机がずらっと並ぶ光景、一度に何十人が集まる雰囲気、先生の監視の目、こういうのが死ぬほど駄目な子どもたちもいます。そんな子たちを無理繰り毎日教室に呼び寄せたら、どうなってしまうでしょうか?
必ず深い傷を負い、それを一生引きずることになってしまうと思います。
いま、日本に小中学生は1000万人ほどいます。以前にも書きましたが、この1000万人の全員が、毎日朝8時半に学校にいる世界って正直かなりつまんないと思います。小中学生、というか人間はロボットではないので、1000万人全員が同じ考えを持って行動することはまずありえません。
「不登校を未然に防ぐ」と言う表現は、そういった原因から対策を練ろうという姿勢をまったく感じられず、このまま防ぐための施策に走ってもまったく意味がないと思います。もしも本気で不登校の数を減らしたいのなら(僕はそういう考えにも違和感を覚えますが)、「防ぐ」と言う認識をまず改める必要があると思います。
不登校は「受け入れる」ものなのではないか?
学校と言う環境そのものが苦手な子どもを「学校が好き」にならせようと努力しても、義務教育の9年間ではハッキリ言って無理です。一生涯をかけても克服するのに時間が足りるかどうかだと思うのに、人によっては突如苦手になる子もいる中で9年間はあまりにも短すぎます。
じゃあどうすればいいのか、と言えば、不登校を「受け入れ」、学校ではない違った教育の場や空間を作ることが、今大人に求められてるのだと思います。
フリースクールはもちろん、最近ではシュタイナー教育やオルタナティブ教育と言ったワードが注目を集めています。最初から学校ではなく、オルタナティブ教育を進めるNPOのスクールに通わせる親御さんも最近増えてきているという話を聞きます。こういった場が、不登校教育ではものすごく重要だと思います。
人間は理解されないということを異常に怖がる生き物でもありますし、多数派じゃないことに異常に不安を抱く生き物でもあります。隣の太郎くんは毎日元気に学校に行ってるのに、うちの子はなんで行けないんだろう・・・と不安に思う親御さんもいると思いますが、まずは「行かない」ことをひとつの考えとして受け止めるのは大事です。
なぜ学校に行かないのか、どういう考えをもって自分の子は毎日を過ごしているのか。少しずつ紐解けば、やっぱり学校に行くのが一番、ということになるかもしれませんし、学校側に不信感を持ったり、この子は学校と言う環境にあってないから行かせない、という結論が出るかもしれません。それでいいのです。
そこで理解されなくても、理解しない人にとって自分の子どもが学校に行くか行かないかなんて、突き詰めて考えれば別に生きていくうえで何ら関係のないことです。子どもとの関わりさえ細心の注意を払っておけば、いつかは周囲も受け入れてくれるでしょう。(もちろんとことん受け入れない人も中にはいますがね・・・)
一昔前に比べ、今は職業はもちろん考え方も多様化する時代になりました。そんな中で、未だに「学校」というひとつの環境に子どもたちを押し込め、型にはめた教育をする方がおかしいのではないか、と上記の僕のツイートを引用しておられた方もいました。一理あると思います。
「義務教育なんだから、学校に行く(行かせる)のは当たり前だろ」
こういうことを書くと、決まってこんな意見が出ます。しかし、「義務」というのはあくまで大人に対する義務なので、子どもたちから見れば「権利」でしかありません。つまり、別に子どもたちは学校に行っても行かなくてもいい訳です。
そのかわり大人側には、子どもたちに教育をきちんと施させる「義務」があるから「義務教育」なのです。そしてこの「義務」は、必ず学校に通わせることを意味しているわけではありません。「学びの環境を用意する」ことが義務なのです。
(参考:「学校に行かせなきゃ…」そんなお母さんに知ってほしい義務教育の本当の意味 | LITALICO(りたりこ)発達ナビ)
子どもが学校に行かず、大人が義務教育と言う建前で学校に行かせようとするのは、実は大きく間違っているという考え方ができますね。先述したように、まず「なんで学校に行けないのか?」が分からないと、いつまでたっても前へは進めません。いわゆる「無気力」や「甘え」にも、どこかに必ず大きな理由が隠れています。
そもそもこのような問題も「不登校が悪いものである」という誰からともなく広がった認識によるもの。学校が苦手と言う子どもたちの声なき声が、世間に響くような社会であってほしいと願いますし、ひとりの不登校経験者としてそういう社会にしていかなければならない、と痛感しています。
◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。