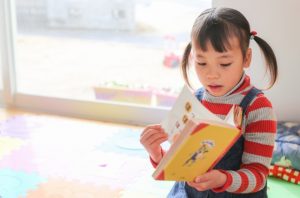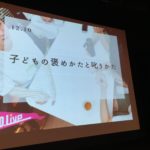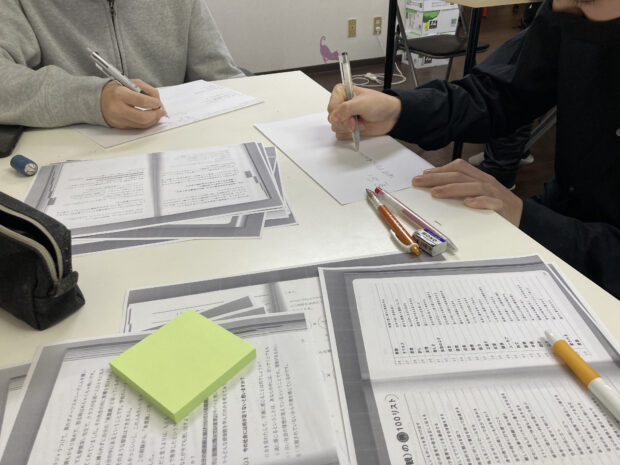こんにちは。D.Liveスタッフの得津です。
先日、先生向けに「不登校の子どもを新年度から担任することになった先生が知っておきたい8つのこと」というタイトルで新学期がはじまって子どもの不登校について面談するときに気をつけて欲しいことを書きました。今回はその反対で保護者さん向けの記事です。
特に、前年度から子どもが不登校になり、そのまま年度をまたいで新学期が始まるご家庭にとってお役立ていただければと思って書いています。保護者さん向けの不登校に関する記事はかなりたくさん書いているので、ブログのヘビーリーダーの方にとっては目新しい話はないかもしれませんが、どうぞお付き合いください。
1、長期戦を覚悟する
前年度、あるいはそれ以前から不登校になってしまったケースの場合、ある程度の長期戦は覚悟しておいたほうがいいです。始業式に気合いを入れて登校するケースもありますが、多くは長く続きません。年度が変わったはずみに登校が続くケースは稀です。もし、始業式に再び登校した場合にお願いしたいことがございます。
始業式に登校できても、また行けなくなることがあります。そのときに落ち込まないで欲しいのです。一番残念な気持ちになっているのはお子さんです。「もしかしたらこのまま行けるかも」という親や先生の期待をお子さんは感じています。
その期待に応えられなかったという事実はお子さんの劣等感につながるかも知れません。始業式に登校したら、「明日はどうする?(行かんでも良いけど)」くらいの気持ちでいるほうがお互いにとって健康的です。
2、先生は味方
新年度になって担任の先生が変わると思います。前年度の先生がどんなにイケてない先生だったとしても新しい先生は違うかも知れません。管理職の先生も変わるかも知れません。前年度には通らなかった要望も新しい先生なら通るかも知れません。先生が味方になってくれる可能性がありますので、まずは友好的にいきましょう。
3、先生も不登校をよく知らない
教師という仕事に就く人は多くの保護者さんと同じく、子ども時代に不登校の経験はありません。もちろん不登校の子どもを受け持ったこともあるでしょうが、何年も何年も不登校の子どもを指導した経験がある先生は少ないでしょう。ですから、先生もまた不登校の子どもへの適切な関わりをよく分かっていません。
これは別に悪いことではありません。少しの成功事例を絶対視して「私に任せてください。こうすればいいんです!」みたいなマッチョな指導をされても、子どもに合わなかったら大惨事です。それよりは、手探りでもいいから同じ目線で子どもにどうなってほしいか、どうサポートしていくかを話し合い実行していける関係の方がずっといいです。
同じ目線に立つために、ご自身が参考にされた本やブログや考え方などを先生に紹介するのも良いと思います。先生が気を悪くするんじゃないかなんて遠慮する必要はありません。
例えば、まちづくりの場合が顕著ですが、住民・行政・企業などの様々な立場の人が「街を良くするために何ができるか?」というテーマで話し合ったら、言ってることが全然かみ合わないことがままあります。同じ日本語を話しているはずなのに違う言語を話しているかと錯覚するくらいです。こんな問題が起こる理由は、一つの単語から想像する意味やイメージがズレているからです。つまり共通言語がないのです。
保護者さんと学校の先生との間でも同じことが起こり得ます。きっと「不登校」という単語からイメージすることがズレているはずです。このズレを埋めるためにも、ご自身が勉強したことをお伝えすることをオススメしたいのです。
4、子どものことはいろいろ教えてあげて
まず、面談の持ち方からお話しさせてください。多分、新学期が始まったら先生は一度お子さんに会わせてくださいと連絡が来るでしょう。「じゃあ・・」と子どもに会わせる。これは結構なバクチです。街コンや相席居酒屋に行って気の合う人を見つけるくらい上手くいく確率が低いと個人的には思っています。
だって考えてください。新しく担任したばかりで、先生はお子さんのことをほとんど知りませんよ。もちろん前担任から引き継いでいることはあるでしょうけど、他の子どもたちのことも引き継がれていますから、一人当たりの情報量はそんなに多くないです。こんな状態で訪問しても、お子さんと話せるトピックは少ないです。下手したら自己紹介と「明日は学校に来てね」という言葉だけで終わるかも知れません。
それではせっかくの機会がもったいないです。大事なのは、先生ともう一度会っても良いと思ってもらうことです。だから、いきなり子どもと合わせるよりは、事前に先生と保護者さんの二者面談から始めた方が良いです。
私たちD.Liveのフリースクール昼TRY部では、かならず保護者さんとの二者面談から始めます。お子さんがいきなり体験や見学に来ることはほとんどありません。まずは保護者さんからお子さんが不登校になった経緯やお子さんの好きなことなどを伺い、子どもと会っても大丈夫だと保護者さんに思ってもらったらお子さんと面談します。
全てはお子さんとスタッフの間に話せる糸口をつくるためです。「えぇー、会っても話すことないし。」とか、「何話したら良いか分からん。」と言われるのを少しでも防ぐために二者面談から始めています。
可能なら二者面談をして、お子さんの好きなことやこれまでの学校での過ごし方などを先生にお伝えしてください。手間はかかりますが、少なくとも子どもとの最初の出会いを街コンから、幹事がセッティングした合コンくらいには引き上げることができます。
5、学校に戻ることがゴールじゃない
先生向けの記事にも書きましたが、学校に戻ることをゴールに設定しないほうがいいです。もちろん生徒が再び登校できるようになったり、クラスに戻れるようになったりすることは素晴らしいことです。一方で、学校に来ることだけに狙いを絞って関わった結果、また不登校になってしまったケースもあります。
こんなことにならないためにも、学校に戻ることをゴールにするのではなく、子どもにあったゴールや居場所を探すほうが建設的です。中には「学校の空気感がムリ」という、学校では太刀打ちできない理由で学校にいけない子どももいます。
学校復帰だけでなく、教育支援センターやフリースクールなどの別ルートの可能性を視野に入れつつ、子どもに合った指導をしたほうが結果的に先生にとっても子どもにとっても保護者にとっても良いだろうと思います。
6、決めれることは決めて、教えて欲しいことは教えてもらいましょう
早めに二者面談ができたなら、学校には行くときだけ連絡するとか、家庭訪問は月1くらいでいいとか、生徒からのお手紙はいりませんとか、決めれることは決めましょう。私たちがこれまでに出会った保護者さんからは、「夕方の電話がしんどい」、「朝の欠席連絡がしんどい」とよく聞きました。親切なんだろうけど正直しんどいなと思うことは素直に先生に伝えましょう。
また、受験にあたって出席日数の確保の仕方や進路、あるいは公的な相談先などの先生から教えて欲しいこともたくさん聞いて良いと思います。
7、「この対応おかしくない?」と思ったら、国の答申や通知をベースに議論を
先生は味方だと書きましたが、悲しいことに「こんな対応するの?それはおかしくない?」と思わざるを得ないケースも私たちはこれまでに聞いてきました。もし、納得のいかない対応をされたら国や教育委員会などが出している不登校に関する通知や答申をベースに議論することをオススメします。
これは単純で水掛け論を避けるためです。お互いがただ主張しあうよりも「国の答申にはこうありますけど」と、議論のベースになるものを一つかませたほうが建設的です。もちろん学校にもできないことがあります。あなたの主張が通らないこともあるでしょう。「伝えたけど通らなかった」は、まだ仕方ないと思える余地があります。でも「そもそも伝えれなかった」は悔いが残ります。
ここまでお読みいただいてありがとうございました。何か参考になることがあれば幸いです。最後に、不登校のお子さんがいる保護者のみなさんにお伝えしたいことがあります。一人にならないでください。
お子さんが不登校になったとき。近所のママさんにも相談できず、先生もアテにならなくて一人で四苦八苦されているご家庭のお話をD.Liveは聞いてきました。一人でお子さんと向き合っていると、あれこれと不安な気持ちが顔を出してきます。気持ちが落ち着かない夜もあるでしょう。
福祉の業界ではよく言われることですけど、一人で悩むよりは誰かといる方が絶対いいです。自分が話してて楽しいと思える人だとなお良いです。D.Liveは滋賀県を中心に関西で活動していますが、いろいろな地域からご相談をお受けしています。遠く離れているとできることは限られるかも知れませんが、私たちでよければ一人で悩まずにどうぞご相談ください。
おまけ:先生との関係づくりについてもっと詳しく知りたいかたはこちらの記事をどうぞ。
学校の先生との上手な付き合い方 -モンスターペアレンツと思われたくない私たちはどうすればいいのか-
D.Liveでは不登校の子どものサポートをしています。
D.Liveでは、不登校によって失った自信を取り戻すためのサポートをしています。
フリースクールや個別面談(オンラインでも)をしていますので、ご関心おありのかたはD.Liveのホームページをご覧ください。ご相談、お問い合わせはいつでも受け付けております。