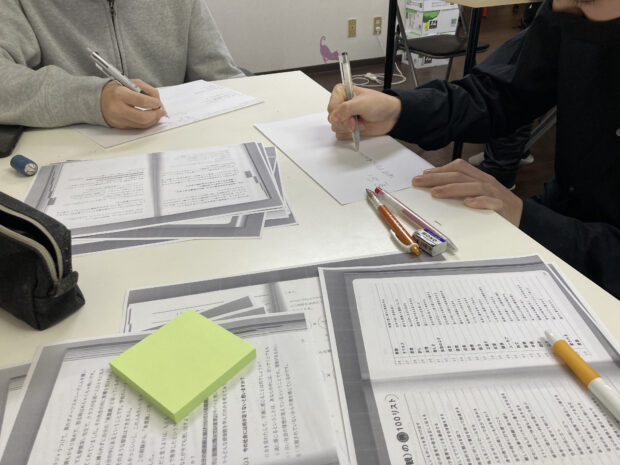文部科学省が、毎年秋に前年度のいじめや不登校などの件数を公表する「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」。今年も先週に平成29年度のデータが公開されました。
この調査結果に関しては昨年も取り上げているのですが、改めて今回のデータがどんなものだったのか、見ていくことにします。
不登校児童生徒数、過去最多を更新
この調査では、「年度間に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒数」のうち、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない 状況にある者」を不登校と定義しています。なので、病気や経済的理由の欠席は除かれています。
平成29年度のデータは、小中高生とも不登校児童生徒数が増加していました。28年度微減した高校生は1000人程度の微増で27年度とほぼ変わらない人数に戻った形になりました。また小中学生に関しては大幅に増加し、特に小学生と高校生の不登校児童生徒数の差が大きく縮まってきました。
このグラフは高校生の調査も始まった平成16年度以降のものを掲載していますが、小学生に関しては平成3年度の調査開始以来最多人数、中学生も過去最多だった平成13年度に次ぐ人数です。小中学生の不登校児童生徒数の合計は144031人となり、過去最多だった前年度を1万人上回っています。
今回のデータが取られた平成29年度はちょうど「教育機会確保法」の成立に向けて機運が高まっていた時期で、不登校支援のあり方が大きく転換し始めたころの数値です。そして今年(平成30年度)は、文部科学省も不登校支援を大きく見直し、学級復帰にこだわらない姿勢を打ち出し始めました。
おそらく来年公表される平成30年度の不登校児童生徒数も過去最多を更新するであろう、と容易に予想できます。それどころか、今後数年は増加の一途をたどり、毎年過去最多を更新し続けると睨んでいます。
最多を数える不登校の子どもたちに、必要なもの
ここからは「小中学生」に絞ってデータを見ていきます。
昨年も取り上げた「学校内外の機関等での相談・指導等を受けた人数」について、28年度と29年度で比較したグラフが上のものになります。要は、不登校の子どもたちがどこで誰の支援やサポートを受けているか、ということです。
また、これは複数回答可の調査ですので、たとえばひとりの不登校の児童生徒が教育支援センターと児童相談所、双方の支援を受けている場合もあります。
不登校の児童生徒数が増えていることを受けて、すべての支援サービスで前年度よりも支援を受けた児童生徒の人数が大きく増えています。しかしながら、養護教諭やスクールカウンセラーなど、学校内の不登校支援サービスに集中している問題点も、ここで浮かび上がってきます。
学校内の不登校支援サービスを受ける子どもたちの人数は、全不登校児童生徒数の半分にあたります。それに比べ、学校外の支援サービスを受ける子どもたちの割合は3割程度と、やや差が見られます。
たとえば、弊団体が運営している不登校の子どもたち向けフリースクールの「昼TRY部」は、毎月何本もの見学や問い合わせを多くいただいています。その「昼TRY部」は上のグラフでは民間団体・民間施設の範疇に入りますが、29年度のデータでもわずか3000人強、不登校児童生徒数全体の2%にすぎません。
さらに学校内外の支援や相談をそもそも受けていない不登校の子どもたちが、29年度は3万人を大きく越えました。たとえばホームスクーリングの形をとる家庭もあると思いますが、なかなか外にすら出ることのできない状態で家族もどこを頼ればいいのかもわからない、という事情を抱える家庭も多いはずです。
前述しましたが、文部科学省が「学級復帰にこだわらない不登校支援の必要性」を打ち出し始めています。おそらく今後学校外の不登校支援サービスを受ける子どもたちや保護者が増えていくと予想できます。しかしまだまだ世の中には「不登校の子どもたちの居場所」が足りていない、と言えるでしょう。
実際、フリースクールや不登校の居場所を運営する人たちと話をすると、どこもかなり遠方から相談を受けたり、実際に新幹線で居場所へ通う子どもも少なくないそうです。そうなれば金銭負担もかなりなものになってきます。もっと身近に、気軽に通える不登校の子どもたちの居場所や支援が求められています。
再び登校できるようになった児童生徒の人数は?
弊団体のフリースクール「昼TRY部」にも、最終的に学校復帰を果たし、登校するようになった生徒がいます。では全国的にこの再び登校できるようになった不登校の子どもたちはどれくらいいるのでしょうか。
こちらは「不登校児童生徒への指導結果状況」を円グラフにしたものです。「指導」って誰がどんなことをしているの?ということにはこの調査では触れられていませんが、なんにせよ諸々の働きかけで再び登校できるようになった生徒の割合を青色で示しています。
小中学生とも、29年度の全不登校児童生徒数の4分の1にあたる割合で学校復帰しています。まさか3つともこんなキレイに似通ったグラフになるとは想像すらしていませんでした。
4分の1、ということは言い換えると「4人に1人は再び登校することができるようになった」ということですが、個人的にはこう書くとかなり割合としては高く感じます。でも、だからといって登校を急かしたり、無理矢理学校復帰させることは絶対にNG、ということは言うまでもありません。
一方で、引き続き不登校が続いている生徒に関してはグレーで示していますが、その中で「継続した登校には至らないものの好ましい変化が見られるようになった児童生徒」に関しては濃いグレーで示しました。学校復帰に向けて一歩ずつ前に進んでいる段階です。
「登校できるようになった児童生徒」「継続した登校には至らないものの好ましい変化が見られるようになった児童生徒」を合わせると、半数近い数字となることがわかります。これは、裏を返せば「本当は学校に行きたいけど、身体が動かない」児童生徒の多さの表れかな、と感じました。
支援が必要なのは、不登校の子どもたちだけではない
最後に、こんなデータをご紹介しましょう。
こちらは、不登校の児童生徒が在籍している小中学校の数を割合で示したグラフです。見て分かる通り、小中学校とも不登校児童生徒数在籍校が過半数を越え、特に中学校に関しては全体の87%もの中学校に不登校の児童生徒が在籍している、というデータが出ています。
これだけでは各学校に何人不登校の生徒がいるかまではわかりません。しかし「不登校生徒がひとりもいない学校のほうが珍しい」というこのデータは、いま教壇に立っているすべての先生方に「不登校の子どもたちと関わるスキル」が求められている時代が来ていることを意味していると思います。
つまり、それほど不登校ということが、もうまったく珍しくなくなったのだと言えます。実際、不登校の児童生徒数はどんどん増えています。しかも子ども自体の数は減少傾向ですので、割合に直せばもっと増えていることになります。
・・・実は円グラフを示して以降ここまで書いてきた文章は、昨年同じように28年度のデータを考察した記事のまとめに書いたことと、ほとんど同じです。
すでに「不登校は誰の身にも起こり得るもの」というのはよく言われていますが、だからといっていざ実際に自分が関わる生徒、担任を持っている生徒が不登校になったとき、私は一体何をしてあげたらいいのだろう・・・と路頭に迷われる先生方も、きっと少なくないはずです。
僕はこういう「先生への支援」も、これから先とても大事になってくると思っています。
学校、いや、先生を異常なほどまで敵視して、どう関わればいいのかほとほと困っている。部活や授業準備に大わらわで、なかなか学校に来れない生徒に対応する時間がとれない。日々かなり追い詰められているそんな先生方への助け舟も、絶対に必要です。
D.Liveでもこの夏開催しましたが、「教員向けの不登校勉強会」の需要がこれから先高まってくるに違いありません。学校の先生が不登校に対する正しい知識や理解を持てないと、子どもたちはもちろんのこと、先生自身も大きく落ち込んだり傷ついてしまうことになります。
子どもたちの支援もさることながら、それをサポートする保護者や先生方など大人への「支援」も立派な不登校支援です。増えゆく不登校の子どもたちを理解し、暖かく見守り、サポートしていくためには、社会全体で「不登校」について考えていかないといけません。
しかし、前述しましたが、こうした支援や機会の場は、明らかに不足しています。
ひとりひとりが不登校という現実を考えるためにも、いろんな形の「支援」の必要性を、もっと大声で叫ばなくてはいけないのかもしれません。
◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。

.png)
.png)
.png)
.png)