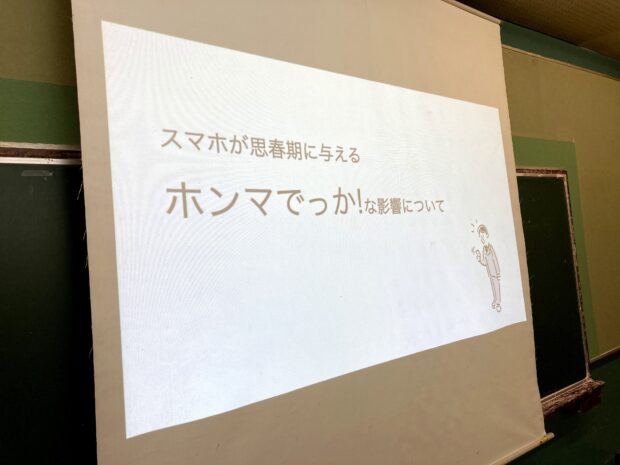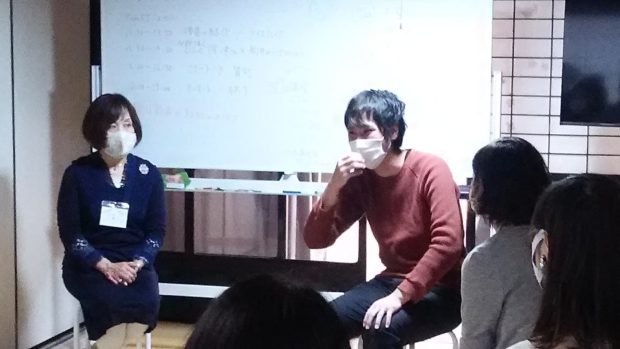こんにちは。
スタッフの得津です。
10月21日(日)に「不登校のおはなし会in滋賀」をおこないました。
2017年から始まったお話会も14回目を数え、
D.Liveがこれまでおこなってきた会の中でも一番のロングランシリーズとなりました。
今回のお話会では4名の保護者さんに来ていただき、
「経験者と話す されて嬉しかったこと・嫌だったこと」をテーマに子どもとの関わりや進路について2時間ほどじっくりお話ししました。
ーー過酷なプレッシャーにさらされていた高校時代
今回は大学1回生の男性に高校3年生のころ、学校に行きづらくなった経験をお話いただきました。
受験シーズン真っ只中の秋頃、受験勉強がうまくいかなくなったことをキッカケに学校にいけなくなったそうです。
先生や家族のサポートもなく、どうして自分の気持ちをわかってくれないんだという気持ちが募っていた彼の心の支えは保健室の先生だけでした。
「先生も家族も、『あと何日休んだら留年やぞ。わかってるか』とか、『とにかく次がんばったらいいやん』とか、『進学に響くぞ。』とか、とにかく学校と勉強に向かわせる言葉ばかりでした。クラス替えのとき、ぼくだけ進学クラスにいったこともあって、高2のときに仲が良かった友だちとは別になってしまいました。相談できる友だちもいなかったから、支えは保健室の先生だけ。でも、保健室にいれる時間は1時間だけと校則で決まっていて、時間になったら担任がむかえに来たんです。」
一般的に不登校になるとカウンセリングを進められることが通例だと思います。彼も同じくカウンセリングを進められましたが、続かなかったそうです。
「正直、カウンセリングの先生は全然合わなかったです。でも、合わなくて成果がなかったらカウンセリングの先生に悪いじゃないですか。だから、カウンセリングの先生にめっちゃ気を遣っていました。『ありがとうございます!楽になりました!』って。でも部屋を出た瞬間にどっと疲れるんですよね。全然楽にもならない、何やってるんだろうって。」
本人の心を支えていた勉強への自信が崩れ、その辛さを理解してくれる人も少ない中で、周りからの進学の期待や成績の向上といったプレッシャーに晒されつづけた高3の彼。
教室にいても手が震えて字が書けない。吐き気がおそってきてすぐに教室を出る。
そんな日々が続き、「自分はダメなやつなんだ」と自己否定感ばかりが募っていきました。
ーー私たちはがんばることばかりを求めてはいないだろうか
なんとか高校を卒業し、大学に進学できた彼は少しずつ落ち着いて過ごせる日が増えてきたそうです。
彼の話が終わり、場の雰囲気は自分自身の子どもへの関わり方を見つめ直すような空気感になりました。
「子どもが学校に行けなくなりだしたときのことを思い出しました。きっと私も期待をかけ過ぎていたんだと思います。」
「難しいですよね。もう私は子どもが学校にいかなくても良いと思っていますけど、本人は高校には行きたいらしい。となるとやっぱり勉強はしないといけないけど、今はそんなそぶりは一切ないんです。大丈夫か?って思うんですよねぇ。」
皆さんの話を聞きながら、私はカウンセラーの高垣忠一郎先生の言葉を思い返していました。
高垣先生は著書『つい「がんばりすぎてしまう」あなたへ―自分のこころを見つめなおすために (新日本出版社)』の中で、今の社会はお互いにがんばることを強要し、がんばることを監視し合う社会になっている。だから、本当は疲れて苦しいのに、苦しい気持ちを吐き出せない子ども達が増えていると述べています。
今回のおはなし会で話題提供してくれた彼はまさしく「がんばることを強要する社会」の中で生きてきたんだと思います。目標に向かってがんばることや努力することは素晴らしいことですが、それが本当に子どもの中から芽生えた気持ちなのかどうか私たち大人は見つめ直す必要がありそうです。
思春期の子どもは特に大人の期待に敏感な年頃です。
例えばテスト勉強中や塾から帰ってきたときに聞いてみてください。
「なんでそんな頑張ってるの?」と。
「だって、やれって言ったやん。」とか「がんばらなヤバイもん。」なんて返事が返ってくると、
ちょっと休んだほうがいいサインかも知れません。
ーー休むのは悪いことじゃないし、むしろ休んでいい
話題提供してくれた大学生の彼の話から、頑張りすぎることや頑張りを求めすぎることが子どもにどんな影響を与えるかを知りました。
D.Liveのブログでも折に触れて子どもに休ませることの大切さを伝えてきました。
(例えばこちら。「皆勤賞」を手放して「休むこと」を覚えよう )
成長の面でも休息は大事です。
成長は適度な負荷と適度な休息によって生まれます。
スポーツ選手も毎日練習ばかりしませんよね。練習メニューの中に休憩を当然はさみますし、まとまったオフもとります。休むことも大事だと知っているからです。
子どもを見ていると、どうにも成績が伸びない。いつになっても教えたことが身につかない。同じ間違いばかりする。そういった様子を見るともっと勉強時間を増やすよう言いたくなりますが、実は本当に必要なのは休憩かも知れません。