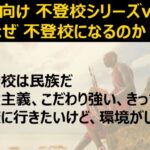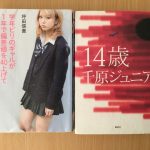「環境が変われば不登校はリセットできる」と言う幻想
「学校に行かないのは、中学3年間だけにしよう」
僕にもそう思っていた時期があった。
当時通っていたフリースクールに、中学3年生は自分含めて3人。ひとりは「料理人になりたい」と調理科がある高校を志し、もうひとりは通信制高校を目指すことで話がまとまった。
そのころの僕は、「中学3年間ほとんど学校に行っていない」ことに引け目を感じていた。そして、大学に入るには全日制の高校にしっかり通わないと絶対無理だと思っていた。だから僕は、とある全日制の私立高校を専願で受験することにした。
そして、合格した。
地元の中学からその高校へ進学するのは自分ともうひとりだけ。しかも全然話したことのない子が一緒。
つまり、まったく知らない生徒ばかりの環境に飛び込むことになった。
僕はこれが好都合だと思っていた。
このころ、僕が学校に行けない原因は同級生の不和だと思っていた。だからこそ、人間関係が一気にリセットできる環境というのは実に最適だと思っていた。実際、新しいクラスメイトにも苦手意識はそんなになかった。
しかし、新たなところで問題が起こる。
「君たちは高校生なんだから、それくらいのことはしっかりしろ」
ちょうど11年前の今頃、新入生ガイダンスで僕らはこんな叱責を受けた。
おかしな話だと思った。
そもそも、卒業式こそ済んではいるが3月末までは僕らは「中学生」と言う身分のはずである。いくら入学が確約されているとは言え、まだ4月じゃないし、入学式も済んでいない。「もうすぐ高校生」と言われるならまだしも、その叱責は何かお門違いではないか、と言う疑念が晴れなかった。
ある程度の関係性が築けているのなら、「それは違うんじゃないですか」と意見することもできた。しかしそれより前に、この学校の教師は「恐怖政治」をもって、生徒を徹底的に管理するという関係性を築きにかかった。こんなことでは良好な信頼関係、いわゆる「ラポール」なんて築けるわけがない。
不登校だった中学3年間、学校の配慮もあって担任はずっと同じ先生だった。先生は定期的に家庭訪問をしてくださり、それなりの信頼関係を築けていた。そのため、学校のことで何かおかしいと思ったことがあれば直接先生に意見できていた。実際それで校外学習のルールを見直してもらったこともある。
しかしこの高校では、何か意見すれば強面の生徒指導教諭に目をつけられるのは明らかだった。ひょうきんなキャラの教師がいないことはなかったが、「僕は高校のころ皆勤賞を取りました」「甲子園に出ました」などと、ただの自慢のような話をする教師が大半だった。
今にして思えば、そういうところから権力を誇示しなきゃいけないくらい、生徒を管理する自信がない教師ばかりだった。だからこそ、生徒を上から押さえつけ、歯向かったら絶対に許さないという態度で臨む恐怖政治を取り入れていたのだろう。
そんな「恐怖政治」から逃れるように、駅の待合室でこの高校の制服を着た女子生徒が、突然ピアスをつけて派手なメイクをし始めた。学校見学の帰り、たまたまその光景に遭遇したフリースクール時代の先生は、「ヤマモトにはこの学校は合わないかもしれない」と直感したという。
あの学校の教師は、とにかく配慮がなかった。
新入生宿泊研修に耐えきれず帰らせてほしいと懇願したとき、旅館のロビーの一角で押し問答になった。別室に呼ばれることもなく、ほかの宿泊に白い目を向けられながら何人もの教師に囲まれた。それは、たいへんに屈辱的なものだった。9割9分教師への信頼を失った。
でも、授業が始まれば何か変わるかもしれない、と翌週も登校した。しかしそこに待っていたのはまた理不尽な説教をする学年主任だった。放課後「部活を見学して先輩と関係性を築いてみよう」という思いは、もう残されていなかった。完璧にこの学校には居場所がないと悟った瞬間だった。
翌日、とうとう家から一歩も出れなくなった。再びの不登校生活へと逆戻り。せっかく購入した学校の最寄り駅までの定期券は、2,3往復しただけで期限が切れた。
僕の不登校の原因は、同級生の不和じゃない。学校という雰囲気や集団生活、教師に絶対服従しなきゃいけない環境が苦しかったんだと気づいたのは、このときだった。
もうすぐ新年度が始まる。
でも、不登校の子どもたちがいきなり学校に通えるとは限らない。
いくら新たな環境で心機一転再スタートを切ろうとしても、それは不登校の子どもたちにとっては大きな負担となる。もちろん、あるきっかけですんなり学級復帰できることもあるが、現実はそううまくいかない。とくに「学校」という環境に苦痛を感じている場合は、復学するのに相当な努力を要する。
それは、いくらクラスを変えても、学校自体を変えても、ハッキリ言って焼け石に水だ。
「学校が変わったら、きっとこの子はきちんと通えるだろう」という期待は、すぐにでも捨て去ってほしい。そんなもの、ただの幻想だと思う。そもそも集団生活の下、一斉授業を展開する全日制のような学校では、ひとりひとりに合った学習環境を提供することはまずできない。
不登校の子どもたちが大学進学を目指して、通信制高校のような生徒ひとりひとりにきめ細やかな対応をしてくれる学校を選ぶのは、とても理にかなっている。この対応が手厚いと、そのぶん先生と生徒の適度な関係性を築くこともできる。僕も通信制高校に転学して、先生への安心感や信頼感を得ることができた。
いまや、通信制高校であっても難関大学にチャレンジできるようになってきた。不登校の子どもたちに大事な学びの環境は「自分のペースでじっくり学べる環境」だと思う。みんな一斉に足並みをそろえる環境はまったく向いていないし、適応できずに卒業するか退学することになるだろう。
不登校の子どもたちは、ただ「学校という場で学ぶこと」が苦手なのだ。だから、無理やり学校に行かせる前にその子に適した学習環境を整えてあげなければならない。
「新年度なんだから、学校に行きなさい」。
こんなセリフで、不登校の子どもたちを追い詰めない日々が来ることを祈っている。
◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。