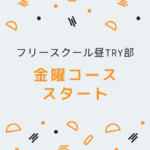子どもを見て感じることVol.2―もし中高生のころにSNSがあったなら
今週のリレーコラムはスタッフが「子どもを見て感じること」についてまとめています。
+-+-+-+-+-
先日、最寄り駅で目が点になった。
ホームの待合室から出てきた女の子。多分小学生くらい。その手に握られていたのは、まぎれもなくiPhoneだった。
え、iPhone?
TRY部にも、最近スマートフォンを持ち始めた生徒がいる。そんなことを言い出したら、僕だって初めて携帯電話を持ったのはまだ小学生だった(祖母との共同利用っていう形だったけど)。だけど、ある程度自分が大人になってから初めて手にしたものを、子どもが普通に持っていると思わず「えっ!」となってしまう。
その女の子がどのようにiPhoneを使っているかまでは分からなかった。もしかすると電車の中で暇だからゲーム機や音楽プレイヤーの代わりに持っていたのかもしれない。でも僕のように、ゲームや音楽を聴くことには全く使わず、主にSNS、人との連絡手段として持っていたとしたらどうだろう。
一体今の中高生は、TwitterやLINEで誰と会話しているのか?
僕は中学で学校に行かなくなり、すぐに居場所をインターネットに求めた。やがて高校の終わりにmixiというSNSが頭角を現し、大学の最初の友達はmixiで見つけた。そして19歳の誕生日にTwitterをはじめた。Facebookもそのうち使いだして、LINEに至っては大学を卒業してからようやくアカウントを作った。
mixiやTwitterの例外もあるけど、「SNS」がぐっと身近になったのは成人してからだった。ところが、今の中高生はもう既にTwitterやLINEが身近にある環境で生きている。実際、TRY部でも「こないだTwitterでなー、」で始まる会話が結構多い。しかも、話を聞いてみるとあることがわかってくる。
どうやら彼らはTwitterやLINEを通して、主に学校の友達とやり取りしているようなのだ。
ここが僕の中高生の頃と決定的に違う。確かに僕も中高生のころからネットで誰かとやり取りしていた。だけどそれは、チャットと言う場で、名前も顔も知らない、しかも年齢や性別も下手をすると嘘をついているかもしれない「画面の向こうの誰か」との文字のやり取り。近所の人に出会う方が逆に難しい世界だった。
その文字でのやり取りが発展して「画面の向こうの誰か」が実際に顔を合わせる友人になる例もあった。が、基本はチャットにログインしていないと会話できない、「一期一会」のやり取りだった。別に家が近所でもないし毎日会うわけでもない、ごくごく弱い繋がりがチャットにはあった。その繋がりが心地よい、という人もいた。
そんな「弱い繋がり」で中高時代を過ごしてきた僕にとって、学校の友達とTwitterやLINEで帰宅後も活発にやり取りする今の中高生に戸惑いを隠しきれない。今でこそ僕もLINEを使うけど、基本的に業務連絡やグループ会話を傍観するくらいで、そんな毎日のようにやり取りするような相手はいない。
そこまでして24時間365日、何かを内輪で共有していたいだなんて、誰かに近づきすぎると離れたがることの多い自分はあっさり脱落していたに違いないし、きっとどうしようもないトラブルに巻き込まれていただろう。そう思うと、自分が中学生くらいの時期にこれらSNSがなくて良かったのかな、と感じる。
もうひとつ、自分が中高生の頃にSNSがなくてよかったと思う理由
僕はたびたび、「自分が書いたもの」を見返すことがある。このブログ、自分のブログ、TwitterやFacebookなどなど・・・。そういえばあんなことあったなあ、と思いながら読むのが楽しいのだが、一応保存してある中学・高校と書いていたブログだけはどうしても読み返せない。理由は、ものすごく恥ずかしいから。
TwitterやFacebookはブログ以上に気軽に何かを発信できるツールだから、もし自分が中学か高校の頃にこれらSNSと出会っていたら、今頃恥ずかしくて目も当てられない発言や写真がたっぷり詰まっていただろう。正直、Twitterを使い始めた5,6年前のツイートを見返してもちょっと恥ずかしい。
そして、今の中高生と思しきTwitterでも、変に目立って、これ10年後絶対に恥ずかしくなるぞー、と感じる発言を結構見る。
「自分に注目してほしい」という思いが特に強い思春期の子どもたちに、気軽に全世界へ発信できるツールを与えたら、そりゃ変わったことで目立ちたい!という思いが暴走するよなあ、と思う。これはごく自然なこと。僕だってそういう行動に及んで、あっさりと自分のアカウントが炎上していたかもしれない。炎上しない自信なんて今もない。
今はSNSとの上手な付き合い方を高校の授業で教える時代である。TwitterやLINEなどを日頃から使いこなす中高生の皆さんには、それと合わせて、きちんと自分なりの使い方やルールを決めて節度ある使い方をしてほしい、と切に思う。