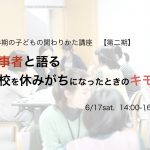「不登校 選んだわけじゃないんだぜ」と叫んだ大学生の気持ちをもう一度考えてみた

できるなら、もう一度彼にあいたい。
もう、今となっては何をしているかもわからない彼に。
聞きたいのだ。
もう一度あのときの気持ちを。
話しあいたいのだ。
本当は欲しかった手助けを。
ぼくが彼と出会ったのは、大学のゼミだった。
4回生になり、ゼミ選択で哲学ゼミを選んだぼくは彼と同じ教授のゼミに配属になった。
この哲学ゼミでは、ゼミ生がそれぞれのテーマに関するレジュメをまとめ、毎回レジュメをもとにゼミ生同士で議論する。ぼくは「大人とは何か?」をテーマに文献研究を進め、同じゼミ生たちとあーだこーだ話した。
彼がテーマにしたのは「不登校の自分の扱い方」だった。
中高と不登校だった彼は、自分が学校に行けなかった期間の意味を見出せずにいた。だから、学校にいけなかった期間をどう解釈すればいいのか自分でも分からず、モヤモヤしていたのだ。
ゼミの時間では、彼がまとめた文献のレジュメだけでなく彼自身についても話が及んだ。
「どうして学校にいけなくなったの?」
「学校に行かずに何をして過ごしてたの?」
「勉強はどうしてたの?」
言葉に詰まりながら、彼は不登校の時期について話した。曜日感覚はほとんどなくなっていたこと。毎週月曜日に発売される週刊少年ジャンプだけが生きがいだったこと。ひどいときは、親ともほとんど話さず部屋にこもりきりだったこと。
この期間にどんな意味があるのか。
どこに意味を見出せばいいのか。
どう意味づけできるのか。
ゼミ生みんなで、それぞれが読んだ文献などからあれやこれやと意見を交わし合った。
けれど、卒論につながるほど的を得た結論にはいたらなかった。
そんなある日、彼がいつもよりもスッキリした顔でレジュメをゼミ生のみんなに配りはじめた。
タイトルには「不登校 選んだわけじゃないんだぜ」。
変わっている。
これまでは「不登校の自分の扱い方」だったのに。
変わっている。
レジュメの内容も、これまでよりずいぶんと整理されて論が組み立てられている。
タイトルとレジュメの大幅な改善により、その後の彼の卒論は一気に進んだ。そして、彼なりに自分の不登校の意義も見出せたようだった。全てはタイトルにもある「不登校 選んだわけじゃないんだぜ」という文献のおかげだと彼は最後のゼミの時間に話していた。
この本を読むことで、ずいぶん楽になったと。
いま、改めて彼に会いたいのは、どうして楽になったのかもう一回説明してほしいからだ。
当時の彼の言葉を忘れてしまった。すっかり。
まさか彼が取り組んでいた卒論がいまになって自分に必要になるとは思っていなかった。
どうして学生時代に連絡先を交換しなかったんだろう。うっかり。
だから想像する。会えないから、とにかく想像してみる。
不登校の期間にどんな意味があるのか見出せなかった彼が、どうして楽になったのか。
そのヒントは、昨年の夏に私たちが講演にお招きした高垣忠一郎先生のお話の中にあった。
自分の気持ちに気づくことが自己肯定感を育てる第一歩
ところが今、余裕のない大人が増えていて、子ども達の声に耳を傾けてあげられていません。心の声をちゃんと聞いてもらえてない。だから、子ども達は自分がわからなくなっています。
子ども達は、自分のありのままの気持ちを表現して、「辛いんだな」、「そんな風に言われて悔しいんだな」、「友達にいじめられて寂しいんだな」、「苦しいんだな」って大人に聞いてもらえて初めて、僕は悲しいんだな、私は苦しいんだな、私は辛いんだなと、はっきり自分を理解します。
自分がわかって初めて、自分を受け入れることができます。わかりもしない自分を受け入れることなんてできるはずがありません。そういう風に自分の本当の気持ちに気付いた時に、初めて自分と出会ったような気がして、「あ、これが自分だったんだ」と気づきます。そういう自分が愛おしく感じられる。愛しく感じる自分をこれでいいんだ、これが私なんだって受け容れられることが、「自分は自分であって大丈夫」という自己肯定感です。だからみなさん、子ども達の声に耳を傾けてください。「よしよし」って子ども達の声に寄り添ってほしいと思います。
(D.Live作成 「子どもの自信白書’16」内 (思春期の子どもを丸ごと認める関わりかた 高垣忠一郎先生講演録)より
不登校だったゼミ生の彼。
彼の気持ちが楽になったのは、もしかしたらゼミの時間に同じゼミ生と話し合った時間にこそあったのかもしれない。高垣先生の言うように、ゼミ生みんなの話し合いが自分の気持ちをつかむキッカケになり、「不登校 選んだわけじゃないんだぜ」という本が最後のひと押しになったんじゃないだろうか。
モヤモヤした気持ちを抱えた不登校の子どもたちに大事なのは子どもの声に耳を傾けること。取りつく島もない、一筋縄ではいかない子どもにも必ず話したいことはある。今はもう何をしているか分からないゼミ生の彼について思い返すことで、こんなことを改めて教えてくれた気がする。