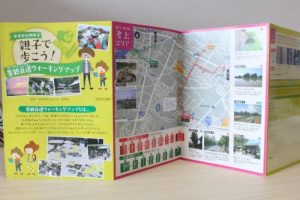新米ファンドレイザーの挑戦vol.3 『基礎から学ぶクラウドファンディング』

こんばんは D.Liveのファンドレイザーの沢田です。
資金調達の手法として急成長している「クラウドファンディング」
言葉は聞いたことはあるけどよくわからないという人のため、
私がこれまで学んだことのなかから、簡単にまとめてみます。
これから始めようと思っているかたの参考になればうれしいです。
クラウドファンディングとは
言葉の意味としては、群衆や大衆を意味するcroudと資金調達を意味するfundingを組み合わせた造語です。クリエーターや起業家、非営利団体などが製品の開発やアイディアの実現といった、自身の プロジェクトのため、インターネットを通じて不特定多数の人から資金協力を募ることをいいます。
そして必要とする金額が集まればそれを元手にプロジェクトを実行します。
クラウドファンディングのサービスを提供している運営会社には手数料を払います。
(運営会社によって違いますが、達成金額の5~20%くらいです。)
例えばあなたが何か新しい商品のアイディアを持っているクリエーターだったとします。
でも資金が十分でないために製作に踏み切れない場合、どうしますか。
まず考えることは次の5つです。
1、なぜつくりたいのか
2、どんなものをつくりたいのか
3、それをつくると誰にどんないいことがあるのか
4、いくら必要なのか
これら元に実現したいことをプロジェクトとして、クラウドファンディングサイトで公開し、
賛同してもらった人から資金協力を得ます。
制限期間内に目標金額を集められれば「成功」ということなり、
支援金額が振り込まれるというのがクラウドファンディングです。
クラウドファンディングのメリット
プロジェクトを行う側、支援する側双方にメリットが多くあります。
プロジェクトを行う側にとっては、なんといっても資金集めと仲間集めが同時にできること。
元手が必要なのは当然のことながら、支援してくれる人は大きな仲間になり、
個人的にはこちらのメリットの方が大きいと感じます。
お店の新規開店を目指すプロジェクトであれば、開店前からすでにファンがいることになりますし
「自分たちがつくったお店」という意識でいてくださる方が多いのは強みになります。
支援する側にとっても
・今後成長していく可能性のある商品やサービスに出資できる
・比較的少額から出資できる
・クレジットカード決済など手軽に利用できる
・支援金額に応じてリターン(お返し)がもらえる
といったメリットがあります。
クラウドファンディングの変遷
クラウドファンディングのサービスは日本よりも海外でのほうが歴史は長いです。
特にアメリカを中心に様々な運営会社によりサービスが提供されてきました。
有名なところでは「Kickstarter」などがあります。
日本で最初のクラウドファンディングサービスは2011年4月に始まった「READY FOR」です。
東日本大震災の直後ということもあり、復興支援などの社会貢献に関するプロジェクトが目立ちました。
はじめは社会貢献のイメージが強かったのですが、最近は新商品や新規開店のプロモーションとして利用するためにクラウドファンディングを使う人も多いといいます。
運営会社は前述の「READY FOR」や「CAMPFIRE」、「FAAVO」などが有名ですが、小さいものも合わせると100を超えてあるそうです。それも『〇〇に特化したクラウドファンディングサービス』という風に、専門化・細分化していく傾向にあるようです。たしかに社会貢献系ならREADY FOR、地域活性化ならFAAVOというように、ある程度運営会社の色もありますので、ご自身のプロジェクトに応じて決められるといいと思います。
まとめ
クラウドファンディングは、資金を集めるための手法としてはとても便利だとは思いますが、その前提としてプロジェクトを行う側の心構えがもっとも大切だと思います。
掲載して待っているだけでは決して成功しない。
これは確実です。
クラウドファンディングという言葉が出てくる前から、海外でも日本でも自分の達成したいことを話して資金を募り、何かを実現させるという方法はとれらていました。これがインターネットが発達して同時に世界中に人に見せることができるようになったのが「クラウドファンディング」です。
しかし「共感したものに支援する」という人間の本質はなんら変わっていませんし、これからも変わることはありません。
- 実現したいと思った原点を忘れないこと
- 分かりやすく伝える努力をすること
- 普段自分たちを応援してくれている人にまず共感してもらうこと
それができればかなり成功に近づくと思います!