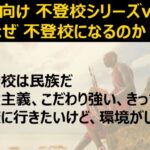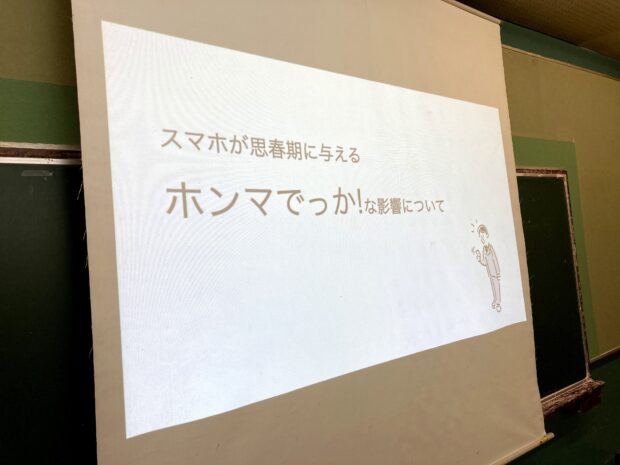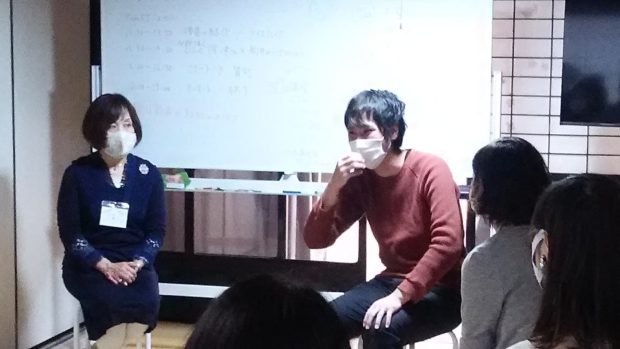こんにちは。
D.Liveスタッフの得津です。
随分と報告が遅くなってしまいましたが、先月の11月23日(土)にウイングス京都にて「子どもの自信探求フォーラム’19」を開催いたしました。
当日は25名の方々にお越しいただき、ゲストの皆様からのお話や、座談会での交流のおかげで、盛況のうちに終えることができました。
ただ、イベント開催にあたって、このフォーラムを子どもの自尊感情の高め方を知る機会にするのか、それともなぜ子どもたちの自尊感情を育てる必要があるのかを問う機会にするのか。企画した自分の中で、どうも中途半端になってしまった感がありました。
最終的には、せっかくゲストの方々に来てくださるのですから、ゲストの活動から見えてきた子どもの自尊感情の高め方を知れる機会にしようと思い、形にしました。
とはいえ、もう片方の気持ちを捨てきれません。なので、このブログでは、選ばれなかった「なぜ子どもたちの自尊感情を育てる必要があるのか」について自分の考えを述べ、当日に足を運んでくださった皆さまが、今回のフォーラムそのものをより詳しく知るための補完になればと思います。
ですから、このレポートではゲストの話が載ることはきっとありません。
子どもの自信探求フォーラム’19で話された内容が知りたいというニーズには答えられません。ごめんなさい。
代表が基調講演した部分は動画になっておりますので、ご興味ある方はそちらをご覧ください。
さて、今回のフォーラムを企画した理由は、「なぜいま子どもの自尊感情を育てる必要があるのか?」を問うこと自体が社会のあり方を問うことになるのではと思ったからです。
NPO法人D.Liveは2年前から不登校支援をスタートさせました。支援をスタートさせるために、不登校について書籍や当事者、専門家から学びました。その中で、不登校支援や不登校を問うことが社会のあり方を問うほどの社会運動性を持っていた時代があることを知りました。
ところが、今は不登校を問うことがそれほど強い社会運動性を持ち得ません。その理路につきまして、詳しくは『「コミュ障」の社会学』をご参照ください。
不登校が強い社会運動性を失いつつあるのなら、自尊感情を育てることはどうなのだろうと私は思いました。
私たちNPO法人D.Liveは、誰もが何度でも前向きに挑戦できる社会をめざして、子どもの自尊感情低下を解決するべく活動しているNPOです。私たちは、子どもの自尊感情が健やかに育つ環境や、自尊感情の大切さを理解する大人が増えることで社会はより良くなると考えています。
ただ、ほとんどの人はこんなことを思って日々を過ごしてはいません。人にはそれぞれ関心が向いている先が違いますから、当たり前です。当たり前ではあるのですが、一方で、関心の違う人たちにも少しでいいからこちらに目を向けてほしい。でなければ、D.Liveがめざす社会の実現は成りません。
関心の違う人たちにもこちらに目を向けてもらうために、法人7周年を迎えたこのタイミングで、改めて社会として子どもの自尊感情を育てる必要性について自分たちで問い直すことで、なにかキッカケが掴めるだろうと考えたのがフォーラム開催の理由です。
あくまで個人的な意見ですが、私は社会として子どもの自尊感情を育てることが、自己責任論のアンチテーゼになるのではないかと考えています。あらかじめお伝えしておきますと、私は自己責任論が好きではありません。
少し考えればわかりますが、持っている人は父親や祖父の代。あるいはもっと前から引き継いできた強力な文化資本や社会関係資本(つながりや人脈)があります。それらを無いことのように扱い、今の立場にいるのは自分が努力しなかったからだ、自己責任だ、なんていうのは話の筋目が通らない。
ですが、自己責任論は社会に広がり、本来なら公的な支援を必要とする人たちまでもが、自己責任的に自分の立場を解釈し、支援を拒否するというケースも耳にします。
物質的な豊かさの時代から、心の豊かさを求める時代に移っている中で、このままでは自尊感情という心の健康までも自己責任論の中に回収されてしまうのではないか。わたしにはこんな恐れがあるのです。
実際、自尊感情や自己肯定感に関する書籍の中で、「自尊感情を伸ばすトレーニング」、「自己肯定感を高める3つのステップ」みたいな本を見ていると、自分の中で完結するものが目立ちます。まるで、「落ちた自信は自分で取り戻しなさい。私たちは関与しないよ。」というメッセージが裏にあるように感じます。
果たしてそれでいいんでしょうか。
人との関わりの中で自信をなくしたり、周りからのプレッシャーに応えきれず自分を嫌いになったりすることだってあります。そんな人たちに、自分で自分の自信を回復させるような努力を求めるのは違うと思うのです。
もちろん、それも必要でしょうけれど、周囲の環境を整えたり、同僚に理解を求めたり、職場全体を見直す機会にしたり、そういうことも必要なはずです。面倒です。面倒だし、コスパも悪いのかもしれません。
けれど、今いるコミュニティの成員が自信を無くしたときに、それはあなたの問題だからと個人の努力に任せるのではなく、コミュニティに瑕疵があると考えて、コミュニティの成員全体で考える方が、コミュニティの後々のことを考えてもずっといい。私はそう思います。
フォーラムに来てくださった皆様をはじめ、このブログをお読みの皆様が私と同じようにお考えだとはもちろん思っておりません。ですが、このフォーラムをきっかけに子どもの自尊感情が下がっていたり、自信がない状態を治療すべきものとして考えるのではなく、子どもや自分を含めた身の回りの社会を捉え直すきっかけにしてほしい。
そのように切に願うのです。