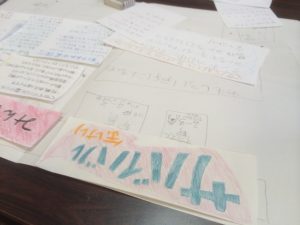ある保護者への手紙 やる気もないし反応も薄い子どもへの関わり

こんにちは。
D.Liveスタッフの得津です。先日、とある保護者さんからご相談のメールをいただきました。
「テスト前なのに勉強へのやる気もなく、こちらが声をかけても生返事ばかり。勉強が嫌いならせめて部活は、と思っていますがこちらも全然です。子どもは中学生です。思春期ですから親にいろいろ言われるのはうっとうしいでしょうが、親の私はついつい気になってしまいます。子どもにどう関わればいいでしょうか?」
以下は、私が保護者さんへお送りしたお返事を編集した文章です。
ご連絡ありがとうございます。
D.Liveの得津です。
勉強も部活もやる気のない姿を見ると親の立場としては不安になってきますよね。今の学校は、私たちが子どものころ過ごしてきた学校とは随分と中身が変わってしまいました。小学校からの外国語学習、プログラミング教育やセンター試験の廃止に伴う定期テストで出題される問題の見直しなど。変化の激しい社会に対応できるようにと、私たちが経験したことがない教育内容がどんどん学校に入ってきています。
他方、友だち関係のこじれがキッカケでいじめられたり、不登校の心配もあることでしょう。これまではニュースの中の話だったのに隣のクラスでは学級崩壊が起こったり、知り合いのお子さんが不登校になったりということが当たり前になってきました。
私たちが経験していないからこそ、将来を見越した学習への不安。
私たちがもしかしたら経験したかも知れなかった、いじめや不登校への不安。
このような不安が心の中から出てくると、ついついなんとかしなきゃと浮き足立ってしまいます。
ですが、私がお伝えしたいのは浮足立たなくていいということです。
もっといえば「驚くけど、驚かされない」態度を心がけると楽になりますよ、というご提案です。「驚くけど、驚かされない」態度と言われると矛盾してるように感じますよね。このことを哲学家の内田樹先生は胆力という言葉で表しています。
胆力というのは、「驚かされないこと」です。危機に臨んで肝をつぶして、白目を剥いて、腰を抜かさないことです。そのためにはどうすればいいか。簡単なんです。こまめに驚いていればいい。
「驚く」というのは能動的な働きです。「驚かされる」というのは受動的な経験です。向きが180度が違います。
「驚く」とは、ほんのわずかな変化の徴候に気づくことです。
「風の音にぞおどろかれぬる」人は、他の人より早く秋の気配を感知して、驚いている。だから、他の人たちが秋の到来に気づかずに薄着のままで過ごして風邪をひいたりしているときには、すでに秋シフトを済ませている。
できたら毎日「おや、こんなことが」と驚いている方がいい。
(中略)
そうやってこまめに「驚いている」と、地殻変動的な変化にはずいぶん早くからそのさまざまな予兆があることに気が付きます。日々のその予兆を見逃さずに備えをしておけば、世間の人が腰を抜かすときに、涼しい顔をしていられる。それが「胆力がある」ということです。
何が起きても何も感じないということではありません。間違えないでくださいね。
ロラン・バルトというフランスの哲学者が「知性とは驚く力のことである」という言葉を残しています。
(内田樹ブログより抜粋)
これまで驚かされることで後手に回っていたこと。かなりピンチな状態になって初めて気づいてなんとか対処してきたことを回避するための作法として自分から驚くことの大切さを内田樹は説いています。
メールにテスト前とありました。おそらく今はテスト2、3日前くらいではないでしょうか。直前になって無理やりテスト勉強をさせるのは親としてもしんどいですよね。付け焼き刃ですから学習が身につかないのも何となく分かるし、子どもは全然やろうとしないし、それでも何とか少しでもやらせるのは苦労がいります。
テスト前なのに勉強していないお子さんの姿に驚かれて、今回メールをくださったことと思います。
このようなことを繰り返さないためには自分から子どもの小さな変化に気づいて驚いていくことです。子どもの変化にこちらから驚きにいくのは発見ばかりで楽しいですよ。
私たちの事業の1つにフリースクールの運営があります。お子さんと同じ年頃の生徒が通っていて、何気ない話をよく生徒たちとします。散髪した生徒がいたら声をかけます。すると、その子は実はいつも2時間くらい美容院にいることが分かりました。寝ちゃうんだそうです。
他にも、ドアの開け方やフリースクールに来る時間が遅れたりしたら「何かあったのかな?」と自分から驚きにいきます。寝不足だという話からサッカーの話になり、今まで知らなかったクラブチームや選手の話になりました。勉強になるんですよ、これが。今までは聞き流していた海外サッカーのニュースにも関心が持てるようになりました。
自分から驚くといっても、こちらからこうしてやろうという意図を持って関わるとうまくいきません。
仕掛けを見破られた釣り人みたいになってしまいます。
テスト前でも何でもないときから、「あれ?」とか「おや?」と思うことを増やしていくと、相手に驚かされることが少なくなります。数日前まで勉強していたのに「やる気なくなったー」と言ってゲームに夢中になっている姿を見ても驚かなくなりました。
驚かなくなったとはいえ、勉強したらいいのにという気持ちが消えたわけではありません。ただ、上に書いたようなギリギリになって慌てて対応するということが減ってきました。それだけでも随分と心持ちが楽なります。やる気がないモードのときはどう過ごそうか、いざその時が来る前から落ち着いて考えられるようになります。
自分の気持ちが1日の中でコロコロと変わるように、お子さんもきっと今日と明日で変わっているところがあるはずです。今はテスト期間なのですぐに頭を切り替えるのは難しいかも知れません。期間中の過ごし方はおってご連絡いたします。
ですので、このメールへのお返事としては、テストが終わったら、「あれ?」とか「おや?」とお子さんの変化に気づくためのアンテナを張るのはいかがでしょうか。
■
文章にあったフリースクールについてはこちらのリンクに詳細を載せています。
距離などの関係でフリースクールに通えない生徒さんのために、オンライン面談や今回の文章のようなメール相談も実施しています。まだ若干名でしたらお受付できます。ご興味おありの方はこちらのリンクから
◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。