先日、Facebook上で友人がこんな記事をシェアしていたのをみつけました。
「どーせ無理」を無くしたい…世界を感動させた町工場のおっちゃんのスピーチ
http://spotlight-media.jp/article/106300900536746109
これは、昨年夏に札幌で開催されたイベント「TEDxSapporo」で発表されたスピーチです。お話されたのは、北海道赤平市にある「植松電機」という会社の常務取締役である植松さん。写真を見る限り、どこにでもいそうで、とても人の良さそうなおじさんです。
植松電機は宇宙開発を主に手がける会社だそうですが、植松さんのスピーチは宇宙への壮大な夢、ではありません。
僕は、小学校に上がってすぐに担任の先生にものすごい嫌われたんです。
僕が信じていたことや、ばあちゃんが教えてくれたことは全部否定されました。僕の夢は「お前なんかにできるわけがない」ってさんざん言われました。じいちゃんが撫でてくれた頭は、先生にさんざん殴られました。とっても辛かったです。
でも、助けてくれる大人はいなかったです。
僕はその先生が言っていた言葉を忘れていませんでした。その先生は「どーせ無理」という言葉をよく使っていたんです。この「どーせ無理」という言葉がおそろしい言葉なんだと思いました。
温かく愛情をもって少年時代の植松さんの頭をなでていたであろう、おじいちゃん。そんなにも愛情をこめて接していた孫が学校で担任教諭に冷たい仕打ちを受けていた事実を知ったら、おじいちゃんや考えを全否定されたおばあちゃんはいったいどんなことを思ったでしょうか。考えただけで涙が出そうです。
この記事を読んで、ぼくはあることを思いました。
自分は、教師との出会いに恵まれていた
ぼくは中学3年間、不登校でした。学校に行かなくなってからしばらくして、担任の先生による家庭訪問が月曜の夜に始まりました。先生は英語科の教諭だったのですが、毎週数学の授業で使ったプリントを持ってきて、からっきし数学が駄目だったぼくに関数や方程式の解き方を手取り足取り教えてくださいました。
高校のときにお世話になった先生は学習面から家族のことまで、幅広く親身に相談に乗ってくださいました。高校時代はフリーペーパーの編集など様々な取り組みにチャレンジしていたのですが、どんどんやって来い、と背中を押してもらいました。この先生に出会ってなければ今の自分はありません。
振り返ればぼくは、素晴らしい先生方との出会いに支えられて今を生きています。上記に挙げた2人の先生も、今思えば「包み込まれ感覚」を大事にしていた先生だったんだなあ、と思います。そして、心のどこかで、「それが当たり前である」と思っていたのも、また事実です。
それに気づくと同時に、中学・高校時代に出会ったほぼすべての先生方がぼくの数多くのチャレンジに何も言わず背中を押してくださっていたその環境に、改めて感謝しようと思いました。
「否定し続けた周囲」と「暖かく接してくれた家族」
この植松さんのスピーチでもうひとつ考えさせられたのは、どーせ無理と口走る教師を筆頭に「できるわけがない」と否定し続けていた周囲と相対するように、家族が植松さんをあたたかく包み込むように接していたことです。
僕は小さい頃から飛行機・ロケット好きでした。でもやったことない人が「できるわけない」って散々言いました。でも母さんは「思うは招く」って教えてくれました。思い続けたらできるようになりました。だから思い続けるってきっと大事です。
「やることを否定し続けた周囲」と「どんなときでも背中を押してくれた家族」、植松さんはどちらを信じて自己実現を達成したか、答えは言うまでもないでしょう。
これがもし、祖父母の接し方が冷たく、母親も「そんなことできるわけがない」と否定していたら、今頃植松さんはどうなっていたでしょうか。まず間違いなく、このような考えさせられるスピーチをされていたとは到底思えません。
ほぼ同時に全く異なる2つの世界を見て育った植松さんのスピーチには、とても説得力があります。特に家族のアプローチの話を聞いていて、あらためて自尊感情とは何か、深く考えるきっかけとなりました。



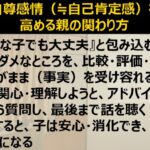
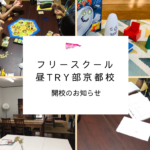















コメント