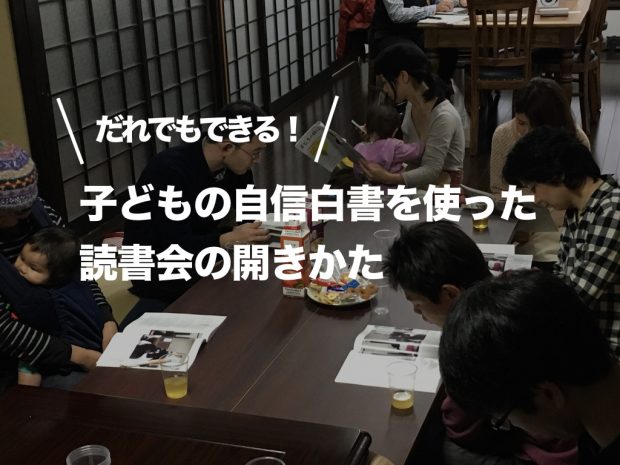ありがたいことに、毎年PTAや地域の民生委員さんに向けて、「子どもの自尊感情の高めかた」とか「子どものに地域でできること」というテーマで講演をさせていただいている。
年に2回くらいは、学校の先生にもお話しさせてもらうことがある。
ある日の講演先で、「自尊感情が低いのは子どもを見ていてよくわかるんですが、具体的に何をしてあげればいいんでしょう?」と、学校の先生から質問をいただいたので、答えたことをここにも書く。
まず、みなさんご存知の通りいまの学校現場は、様々な課題を抱えながらなんとか毎日がんばっている状態だ。貧困や虐待など福祉の領域に関わることも、畑が違うから我関せずというわけにはいかない。多文化理解や、多様な性の理解。同和教育もあるし、もちろんいじめや不登校、学級崩壊だってある。
そんな中で、多方面から数多くの要求を受けながら授業をし、生徒との成長に関わっている先生には本当に頭がさがる。
今でも十分に毎日がんばっている先生方に、さらに新しいことを追加して、「これをやりましょう」なんて私は言えない。
だから、子どもの自尊感情を育てるために何ができるかとの質問に対して私が言いたいのは、いま取り組んでいることを充実させて欲しいということだ。
こんなことを言ってしまうと身もふたもないけれど、学校で自尊感情を育てる方法なんて先行研究や蓄積がいくらでもある。ネットでも書籍でも、その数は本当に多い。自尊感情を研究テーマに据えた学校だってあるだろう。
子ども一人一人の話を丁寧に聞くことも、スモールステップで授業内容を組み立てることも、学級ファシリテーションに取り組むことも、全部筋目は悪くない。やってみて、反応を記録し、改善案を考え、もう一度試してみる。このサイクルを繰り返すだけで、十分価値がある。
今の取り組みを充実させればいいことは分かるけれど、もう一声欲しいというのでしたら、先生にしかできないことをお伝えしたい。
それは物語ることだ。
物語る。ストーリーを語ること。
学校はいろんな生徒がいて、いろんな行事があり、いろんなことを勉強する。
だから同じ日なんて1日もない。毎日何かしら予期せぬ出来事がおこる。
今まで出来なかった鉄棒ができた。
いつもは早く帰る生徒が部活で居残り練習をしている。
興味ないと言っていた文化祭の準備を知らない間にやっている。
なんでもいい。
なんでもいいけれど、できればポジティブなことをクラスの物語として語る。
これは学校の先生にしかできない。塾の先生にも、家庭教師にもできないことだ。
レオ=レオニが描いたフレデリックというネズミの絵本を知っているだろうか。
他のネズミが冬ごもりのためにせっせと働いているのに、フレデリックは何もしない。けれど、長い冬をすごすときにフレデリックはネズミたちに語る。これまでに集めたお日さまの温かさ、色とりどりの草花。みんなうっとりとフレデリックの話に耳を傾ける。
先生がクラスに語るというのは、このフレデリックのようなイメージだと私は思う。
わたしはロマンチックな話をしているわけではない。
実は心理学の中に、集団効力という考えがある。
自己効力感という言葉を耳にしたことはあるだろうか。簡単に言うと、やればできるという気持ちのことだ。集団効力はこの気持ちについて、集団という単位で捉えたものだ、
『自尊感情の心理学』という本に、集団効力について書かれた部分があるので紹介したい。
所属集団を単位とした効力は「集団効力」とよばれ、目標を達成するために必要な行動を組織化し実行できるという集団の能力について、集団内で共有された信念と定義されている。学校場面における集団効力に着目したのがゴダードらである。ゴダードらは、集団のために力を発揮したり意見や考えを表明できる機会を設けること、決定への参加を促すこと、集団として力を発揮できる場面をつくることを奨励している。
人は、集団に影響される。修学旅行は沖縄に行きたいと思っていても、みんながディズニーランドと言えば沖縄と言い出しにくくなるし、いじめはよくないと思っていても周りが見て見ぬ振りだと自分一人では立ち向かう勇気も出にくい。
子どもたちはクラスの雰囲気や、クラスの中の自分の立ち位置をすごく気にする。特に思春期はそうだ。それでも集団効力を発揮するには、担任としての先生の語りが有効になる。
だからこそ先生には語って欲しい。
クラスで起きた小さな喜び事を。行事でがんばったことの価値を。これから教える単元の面白さを。
ホームルームでも、授業の導入でも、終わりの会でもいい。子どもたちはきっと先生の話を聞いてくれる。上手に話せなくてもいい。実際のところ、話の中身なんて相手にはほとんど残らない。残るのは、語ろうとするその雰囲気や姿勢だ。情理を尽くして語ろうとするほど、その姿勢から伝わるものがある。生徒に残るものがある。
行事もなく、淡々と過ぎていくような日々こそ、学級が落ち着かなかったり、ハプニングが起こったりする。そんなときこそ一層先生がたには、クラスのストーリーを語ることでクラスの子どもたちと一緒に、毎日の小さな価値や良さを分かち合って欲しい。
これは、先生だからできる極上の体験だと思うから。
お知らせ
自尊感情について考え、子どもとの関わりのヒントを得られるようなフォーラムを企画しました。
・子どもにネガティブな言葉が増えてきた
・子どもの自己肯定感を育てるってどうすればいいの?
・自信が育つクラスづくりって?
このような、子どもの自信や自己肯定感に関するギモンに答えるフォーラムが11月23日(土)に京都にて開催されます。
先生や思春期の子どもを子育て中のママさんなど、3名の多様なゲストが来られます。ゲストのお話や実践は、きっとあなたが子どもと関わる上でのヒントになります!
子どもの自信探求フォーラム’19
11月23日(土)13:30〜16:30
場所:ウイングス京都
定員:40名