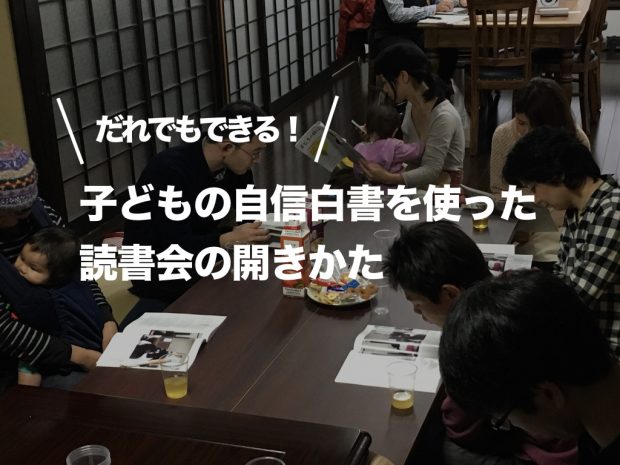どうも、こんにちは。
D.Liveスタッフの得津です。
このwebサイトでは、不登校に関するコラムやイベント情報が多いのですが、今日は私たちが運営する子どもの居場所の実践を紹介します。
私たちD.Liveは、草津市からの委託で「TudoToko(つどとこ)」という草津市内の中学生にむけた居場所を運営しています。簡単にいうと中学生が通える夜の学童みたいな取り組みで、毎週木曜日の18時から20時までおこなっています。
スケジュールは、前半1時間が関係づくりやキャリア教育的なワークショップ。後半の1時間が、地域の民生委員さんたちが作ってくれる美味しいご飯を食べて団欒という感じです。
運営は私たちが担っていますが、子ども達との関わりや毎週の調理などは、草津市内のボランティアさんたちに多大な協力をいただいております。
ここからが本題なのですが、毎週のワークショップがなかなか頭を悩ませるんですよね。
コンセンサスゲーム(「無人島から脱出するために20のアイテムから話し合って優先順位をつけよう」みたいなゲームです)や、グループエンカウンター(簡単なものだとジャンケン列車とか)なんかを、毎週つどとこでは取り組んでいます。
どれだけ準備をしても、話し合いになるとグループから抜け出す子がいたり、参加はしているけど自分の意見を一切言わなかったり、毎週の活動を行うための前提となるスキルや態度が揃っていないことが多々あります。
私や子ども達、あるいはボランティアさんたちと子ども達など、それぞれの関係は良好で、子ども達も毎週つどとこは楽しみにしています。私たちD.Liveが大切にする自尊感情が育まれる場所という点では一定の効果を発揮しているとは思います。
ただ、集団になると難しい。
そんな折、『心理的安全性のつくりかた「心理的柔軟性」が困難を乗り越えるチームに変える』を読みました。
これだと思いました!これこそが、今のつどとこに必要な要素だと。
少しだけ解説しますと、この本では職場や自分が属するコミュニティの対人関係において、下記の4つのリスクがあると述べています。
1、無知だと思われる不安
「こんなことも知らないのか」と思われたらどうしようという気持ち
2、無能だと思われる不安
「こんなこともできないのか」と思われたらどうしようという気持ち
3、邪魔をしていると思われる不安
自分の会議での発言や、普段の仕事が「いつもあの人は邪魔をしてくる」と思われないか不安になる気持ち
4、ネガティブだと思われる不安
「いつも否定する言葉ばかり言ってくる」と思われないか不安になる気持ち
これら4つの不安が高い環境や職場は心理的安全性が低く、属するメンバーはその能力を十分に発揮しない(というか不安だから発揮したくない)という話です。
では、どのようにすれば4つの不安は解消されるのかについてですが、本では4つの要素を挙げています。
・話しやすさ
・助け合い
・挑戦
・新奇歓迎
この4つです。どうして、この4つなのか。そして、この4つの要素を具体的にどのように職場やコミュニティで取り組んでいくのかについては、ぜひ本を読んでいただきたいです。
ここでは、対人関係における4つの不安を、つどとこの中で下げていくために取り組んでいることの途中経過をお伝えします。
・スマホを活動の中で使えるようにしました
これまでは食事が終わったあとにスマホを使うことだけはアリにしていました。それまでは、スマホを出して遊んでいたりしてたら注意していました。学校みたいですね。それを少しだけ緩和しました。具体的には、活動中にスマホで調べ物をしないといけない場面を作ったり、分からない漢字はスマホで調べたりしていいようにしました。無知だと思われたらどうしようという不安を下げるためです。もちろんスマホが持ってきていない中学生もいるので、必要な時間だけボランティアさんのものを貸したりしています。
近々、クリスマスパーティーのレクリエーションを決める話し合いをするので、その日は「クリスマス ミニゲーム」などで調べたアイデアを持ち寄れるようにする予定です。
・字の間違いや汚さはスルー
つどとこでは、勉強嫌いな子どもが多く、中には字を書くのも億劫な子もいます。これまでは、良かれと思って大人も子どもも関係なく、お互いに字の間違いや汚さを指摘してたんですが、それもやめました。無能だと思われる不安を下げるためです。字を書く場面があるたびに「漢字の間違いはどうでもいい」と細かく伝えています。
・話し合いの仕方を細かく伝える
「こんなこと言ってもいいのかなと思うことでも、自分がちゃんと考えたことならまずは言ってください。」「まとまらなくても、大人たちが受け止めてくれます。」「自分が紙に書いたことを見せるだけでもOKだから。」
こんなことを話し合いの場面の前に毎回伝えています。無能だと思われる不安やネガティブだと思われる不安を下げるためです。週1回しか会わないので、これらの話し合いの仕方やルールなんて忘れられてしまいます。毎週、初めて話し合い活動をするときの丁寧さを意識しています。
これらのちょっとした取り組みが功を奏してか、最近はグループから抜け出すことは減ってきました。不安を下げるという観点から活動内容を練り上げることを続けていくことは、自尊感情を育むための集団的アプローチとして有効だと今は考えているので、引き続き取り組んでいきます。
もっと言ってしまえば、自尊感情を育むワークショップのような打ち上げ花火的活動を1回おこなうよりも、日頃の指示を丁寧にしたり、使える道具を子ども達の実態に合わせたりする方がずっと効果的だと実感しています。