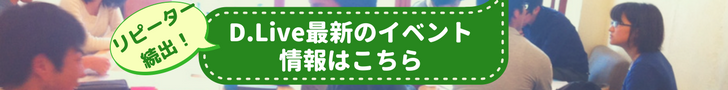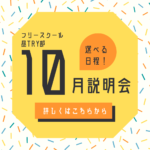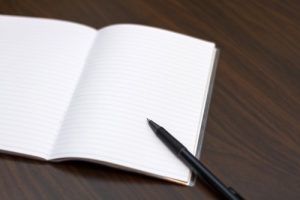高垣先生に学ぶ、子どもの「いま、ここ」に向き合うことで育まれる自己肯定感について
「学校の生活が例えるなら高速道路みたいな生活になっていきました。高速道路の車の流れが自分にぴったりだって人は大丈夫です。でも、生き物ですからそれぞれに自分の一番快適なペースやリズムは違います。だから、オーバーペースで疲れちゃう子ども達が出てきたわけです。ぼくは、不登校の子ども達の姿がそれとダブって見えます。」
「私は私であって大丈夫」高垣先生が語る思春期の子どもを認める関わりと自己肯定感
2年前の2016年の夏に、高垣忠一郎先生をゲストに講演会をおこないました。高垣先生は、かつて不登校が登校拒否や行きしぶりと呼ばれていた時代から思春期の子ども達のカウンセリングをし続けてきた先生です。
高垣先生は、「不登校の子ども達は学校の速いペースに無理やり合わせているから疲れてちょっと休んでいるだけ。今は自分を取り戻す作業をしている時間だ」とおっしゃっていました。
講演会を開いた当時はフリースクールも運営していなかった私たちD.Liveですが、2年が経ち、まがりなりにもフリースクールをスタートして様々な思春期の子どもと関わる中で、改めて高垣先生が言っていたことはもっともだなと実感します。
先日、ある中学生の男子と面談をしていました。
去年頃から学校を休む日が増えて、最近とうとう完全に学校にいけなくなりました。保護者のかたからは、特にきっかけがあったわけではないと聞いていました。
学校や友だちについてどう思っているか聞いてみると、まさしく自分を取り戻す作業をしていることがわかりました。というのも、彼がぼくに投げかけることは、なかなかに物事の本質をついた問いばかりだったからです。
「いろいろ調べて今の自分を正当化しているように思うんですけど、それって良いんですかね?」
「なんか、学校の自分は本当の自分じゃない気がします。本当の自分は何かと言われると分からないんですけど。」
「学校の勉強って、結局点数を取るゲームじゃないですか。それって勉強なんですか?」
いろいろな問いを彼から出されて、その都度ぼくと彼はお互いが納得できる答えを探してあーだこーだと話し込みました。この手の問いはキレイな答えは出ません。だいたい、なんだか納得できるようなそうでもないような答えになります。それで良いんです。大事なのは、お互いが納得する落とし所を見つけることです。
それともう1点。お子さんからこのような問いを投げかけられた時、相手はわかりやすい答えを探しているんじゃありません。相手に聞きながら自分にも聞いているんです。自分で答えを探すために、言葉にして、相手を通して自分が何に疑問を持っていて、何を探しているのかを確かめようとしています。
ボクシングのスパーリング練習と同じです。ぼくたちはただただミットを構えて話を聞くだけでいいんです。
ですから、「そんなん良いから学校いって」とか、「学校って、そんなもの!」と話を打ち切らないで欲しいのです。なぜなら、これらの疑問を口にすることで置いてけぼりになった自分の気持ちを取り戻そうとしているからです。
面談した中学生の男子に話を戻します。どうやら彼は学校に行ってるときは、このような疑問を感じていても口にする余裕もないくらい周りの目を気にしていたことが分かりました。。学校に行かなくなって、ようやく自分に向き合えるようになりました。今は少しずつ学校や勉強することの意味を自分で見つけようとしています。
大人の側からすると、思春期の子どもが口にする問いはすぐに答えは出ないし、めんどくさいです。時間もかかれば、手間もかかります。でも、この手間を惜しんで学校復帰や自己肯定感の回復はありません。
講演会の最後に、高垣先生はこのようにおっしゃっていました。
「余裕のない大人が増えていて、子ども達の声に耳を傾けてあげられていません。心の声をちゃんと聞いてもらえてない。だから、子ども達は自分がわからなくなっています。子ども達は、自分のありのままの気持ちを表現して、『辛いんだな』、『そんな風に言われて悔しいんだな』、『友達にいじめられて寂しいんだな』、『苦しいんだな』って大人に聞いてもらえて初めて、僕は悲しいんだな、私は苦しいんだな、私は辛いんだなと、はっきり自分を理解します。
自分がわかって初めて、自分を受け入れることができます。わかりもしない自分を受け入れることなんてできるはずがありません。そういう風に自分の本当の気持ちに気付いた時に、初めて自分と出会ったような気がして、『あ、これが自分だったんだ』と気づきます。そういう自分が愛おしく感じられる。愛しく感じる自分をこれでいいんだ、これが私なんだって受け容れられることが、『自分は自分であって大丈夫』という自己肯定感です。だからみなさん、子ども達の声に耳を傾けてください。『よしよし』って子ども達の声に寄り添ってほしいと思います。」
よく、思春期の子どもは見守ることが大事と言われます。
確かにそうですが、見守るとは子どもが自分で自分の気持ちに気づける手助けをすることじゃないでしょうか。
※高垣忠一郎先生の講演録は子どもの自信白書’16に掲載しております。詳しくはこちらのリンクから。

◆小冊子『不登校の子が劇的に変わる秘密』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。