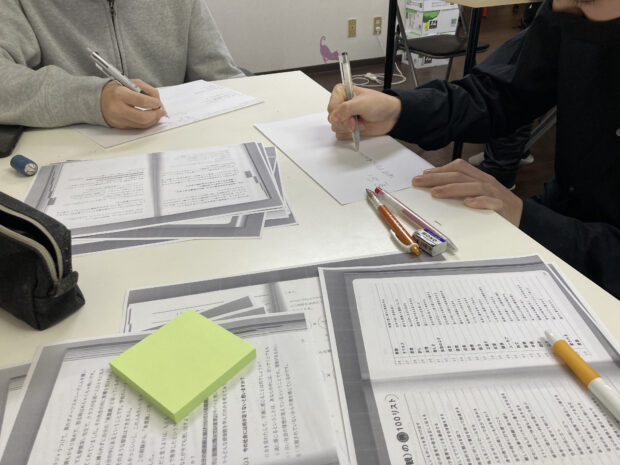先日、YouTube Liveの生配信でメッセージを募った際に「不登校だったことを後悔していますか?」とご質問をいただきました(その配信の様子はこちらからどうぞ)。配信中に僕(と田中)で回答させていただきましたが、今日はもう少し深堀りしてこの質問に答えてみようと思います。
まず前提として、僕は中学3年間のほとんどを学校に行かず過ごしました(中1の秋ごろからフリースクールには通っていました)。そして単位制の高校に入学するも、かなり厳しい指導を目の当たりにして再び学校に行けなくなり、2,3ヶ月後に通信制高校へ転入、そこからは学校に通えました。
で、もうタイトルにも書いているのでここで先に結論を書くと、
「今はまったく後悔していません」
というのが、「不登校だったことを後悔したことはありますか?」と言う問いに対する僕の答えです。
なんでかというと、社会に出たら不登校のことなんて心の底からどうでもよかったからです。
これは当たり前の話なのですが、いかなる業界でも無遅刻無欠席だろうと不登校だろうと「きちんと働くことのできる人材」を求めています。不登校経験があろうと教員免許を取れば学校で働くことはできますし(環境が合うかどうかは別として)、東大卒でも寝坊が多ければ信頼は失墜します。
そういう意味では、社会に出てしまえば学校に行っていても行ってなくても横一線なのです。たとえ不登校経験があったとしても、きちんと専門的な知識を学んだり教養を身に着けられればいかなる職業につくことも可能です。
ただこの話は「今は」というのがミソで、不登校当事者だった中学生のときは「集団に入ることのできない自分」に対する嫌悪感というのが非常に強かったのは事実です。たとえば自分が卒業アルバムに載らないのではないかと、無理ぐり合唱コンや校外学習などの行事に顔を出したりもしていました。
修学旅行は長野県でのスキー実習だったのですが、本隊が出発後にやっぱり行けばよかったのではないかと非常に悔やんで1日だけ参加したこともありました。このために仕事を休んだ両親に車を出してもらって早朝自宅を発ち、帰ってきたのは深夜。日帰り長野往復という強行軍でした。
しかしこの修学旅行は、別にそこまでして行くほどのものではなかったなと今は思っています。なぜなら「無理にでも修学旅行に行った」と言う事実は、その後の人生でなんの役にも立たなかったからです。
正直なところ、行ったはいいもののスキーは素人ですし滞在の数時間で講習が受けられるはずもなく、現地で何をやってたか記憶が大して残っていません。よって早朝から深夜まで車を運転させることになった親にむしろただただ迷惑と負担をかけてしまった、という申し訳ない思い出として残っています。
ちなみに、高校の修学旅行は自由参加方式ということもあり、3年間参加することはありませんでした。これについてもまったく後悔はありません。むしろ僕は集団行動が苦手なので規律を求められる修学旅行など行かなくてよかった、とすら思っています。
話を戻すと、たしかに僕は不登校当事者だった中学生のときには少し後悔をしていました。しかしいままったく後悔していないのは、先述した「社会に出たらどうでもいい」と言う面に気づいたこととともに、「集団に入ることのできない自分」に対する嫌悪感が薄らいでいったという面もあります。
これはどういうことかというと、大学に入ったころからふと、人間関係を築くにあたって修学旅行に行かなかったことはもちろんのこと、もっと言えば「不登校だったこと」すら言わなきゃバレないんだな、ということに気がついたのです。
僕は今こうして不登校支援の現場に携わっているからこそ、こんな文章を書いたり不登校経験を話す場に登壇したりしています。しかし、たとえば電車の運転手とか一般企業勤めなど、要は教育とは関係ないところで働いているのならば、たぶん自分の不登校経験は一切隠して働いていると思います。
それは、別に言いたくないわけではなくて、「働くにあたって別に言う必要がない」からです。
これが、不登校からよくぞうちの会社に来てくれた!特別にキミは基本給に10万円プラスしよう!という話があるならまた別ですが、前述したように社会に出てしまえば学校に行っていても行ってなくても横一線なのです。学校に行ってなくてもやるべきことができなければ怒られます。
何回か書いていますが、学校現場で働くにあたって、僕は自分が不登校だった経験をごくごく限られた人にしか共有していません。よく世間話をする同僚の先生ですら僕が不登校だったことを知らない人も多いはずです。生徒に言えば「えっ!」と驚くことでしょう。
でも、それでも普通に学校で働けています。なんなら、逆に「山本先生、不登校だったからこれができなくても仕方ないですよね」と言われるほうがイヤです。
仲良くさせてもらっている人の中にも、自分に不登校の経験があるかどうかなんてまったく関係のないところでお付き合いさせてもらっている人も多くいます。ただそういう人の多くは自分が不登校だった道を歩んだからこそ出会えた面が大きいのもまた事実です。
ちなみにここまで僕が長々書いてきたことを、同じく不登校経験のある代表の田中は「不登校だったことで失ったものがない」と表現しています。これは本当に言い得て妙な表現です。よくよく考えたら僕も別に不登校を経験した上で失ったものはありません。
いま不登校の子どもたちにとってはこの話は正直響かないと思います。僕も不登校だったころはたしかに後悔していたからです。こればかりは、1度経験しないとたぶんわからないと思います。僕が不登校のころにこんな話をされても「は?」としか思わなかったことでしょう。
でも、社会は基本的にその人に不登校の経験があるからと冷遇するような場所ではないということは確かですし、これは不登校の子どもたちにとってとても大きいことです。そのことに気がつく時期が早ければ早いほど、たとえ不登校でも希望する道をひらくことができます。
この長々とした文章が、質問主の方のお役に立っていれば幸いです。











 PTAで話す不登校入門](http://www.blog.dlive.jp/wp-content/uploads/2018/07/DSC01697-150x150.jpg)