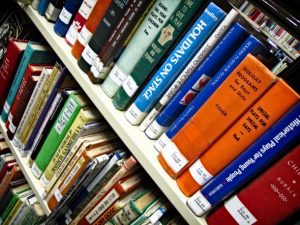ある保護者への手紙その2 子どもの言葉すべてに共感して話を聞かなくても良い

こんにちは。D.Liveスタッフの得津です。
前回に引き続き、ある保護者さんから相談をいただきましたので、
そのお返事をブログ用に補足・編集してご紹介します。
「子どもの言葉に共感できないことがありますが、無理にでも共感したほうがいいのでしょうか?」というご相談へのお返事です。元芸人の島田紳助さんが言っていた「自分にもその思い出があるか一旦探してみる」ことが参考になると思い、ご紹介しました。
ーー
ご連絡ありがとうございます。D.Liveスタッフの得津です。
共感できないことに無理やり共感するのは難しいですよね。ご連絡いただいた、「無理にでも」共感しないといけないシチュエーションを想像しますと、きっと自分の考えていることと反対のことをお子さんが言ったときなのかなとお察しします。
例えば、こちらとしては勉強して欲しいのに「めんどくさいし、勉強したくない。もうテストも点数悪くていいわ。」と言われた時とか。
2010年代はコミュニケーションに共感を求められる時代になったなと私は感じています。子育てや教育系の本にも「子どもの話には共感をもって聞いてあげましょう」という言説が多く見られますし、ビジネスシーンでも共感マーケティングなんて言葉があるそうです。
ご相談くださったということは、きっと保護者さんも共感の大切さについて見聞きしたことがあるのではないでしょうか。
相手の話に共感することが子育てでも求められますが、私は無理に共感しなくても良いと思っています。いくつか理由があるので順を追ってご説明いたしますね。
まず、過度な共感は子どものコミュニケーション能力を低下させると考えるからです。
といいますのも、最近の会話って共感が過剰だと思いませんか?
「うんうん、そうだよね。わかるわかる、そうそうそうそうそう!」という過剰な共感がベースになっている会話は、その集団だけの狭いコミュニケーションを生み出します。狭いコミュニケーションも共感も節度が大事で、これが過剰になると内側にいる人間は会話の内容がだんだん貧弱になってくるし、外側にいる人間は共感できないからその輪に入れなくなってしまう。
難しい話ではありません。実際わたしが関わっている生徒の一人は、周りが自分の知らないゲームの話題ばかりするからクラスが楽しくないと言っています。
私はコミュニケーション能力はできるだけ多くの人と会話できる力のことだと考えています。コミュニケーションの仕方を教える大人が、共感できない話に無理やり共感する姿を子どもに見せることで、自分の態度を真似することはしてほしくので、ぼくは共感できない話は共感しなくて良いという立場です。
では共感できない話をどうするかですが、わたしは共感できなくても似た思い出がないか探すようにしています。
これは元芸人の島田紳助さんが吉本の養成所に通う生徒に話した内容だそうですが、島田紳助さんは番組収録のために事前に知らされたトークテーマの答えを準備しないそうです。「高校時代の思い出というテーマで進めます」と打ち合わせで言われても考えない。一人で考えてもピンとこないからだそうです。
それでも収録が成り立つのは、収録中に相手が話したことと似た経験や共感できることが自分にもあるか心の中で探しているからです。
わたしもこの方法を真似していて、子どもの話を聞いて一旦考えるようにしています。「勉強したくない」と子どもが言ったときに、「自分もそんなときあったかなぁ?」と。これは記憶を頼りにタンスの奥にある服を探す作業に近いです。
子どもが言ったことと合う思い出あったかなぁと、心の引き出しをごそごそと探すんです。
引き出しに無いときもあります。そのときは「ごめん思い出してみたけど無かった」とか、「ちょっとそれようわからん」と正直に言います。
それだけだと愛想がないので、「わからんかったけど、自分にはない部分だから面白い。詳しく教えて!」と言いますね。共感できない代わりに関心を示すようにしています。
子どもの話に関心を示すのは楽しいですよ。D.Liveは思春期の子どもたちと関わっています。思春期にもなると自分の世界が出来てくるので、知らないこともたくさん彼らから教えてもらいます。知らないことを知るたびに自分が打ち開かれていくような感覚です。パソコンのスペックとか、忙しくて見れないニュースのこととか、ユーチューバーのことなど、わたしはたくさん教えてもらいました。
よく「子育ては親育ち」なんて言いますが、これって子どもの世界を通して自分の世界を広げていくことなんじゃないかと最近思っています。
ただ、最後になりますが共感も関心もそれ自体を目的にするから機能するんだと思います。
「ここは一旦勉強したくない気持ちに共感しておいて機嫌がいい時に勉強してもらおう」みたいな下心を持っていると、子どもは見抜いてきます。
わたしたち大人は仕事によって下心や目的のある会話が中心になり、会話そのものを楽しむということが少なくなってきました。ですので、会話を楽しむとか共感や関心を示すこと自体を目的に会話をすることが難しいかも知れません。
ですが、子どもの世界に関心を示して自分の世界を広げるのは本当に楽しいです。
共感できることは共感して、共感できないことは無理にしなくて大丈夫です。
無理をすると健康にも悪いですしね。
ーー
距離などの関係でフリースクールに通えない生徒さんのために、オンライン面談や今回の文章のようなメール相談も実施しています。まだ若干名でしたらお受付できます。ご興味おありの方はこちらのリンクから
◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。