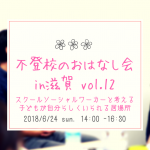大人の都合に振り回される子どもたち―不登校の僕があのとき欲しかった、ひとつの「環境」
この間、自宅の近くを歩いていると、まだ幼い女の子がぐずっているところに遭遇しました。
「足痛いから歩けへん」。
すると、お母さんは、キツい口調でこんなことを返していました。
「足痛いとか、そんなん、あんたの勝手やろ!」
子どもは、大人の都合に振り回されすぎているところがあるように思います。
それは逆に言えば、「子どもの都合」を大人が考えていないところがある、ということでもあります。
そんなことに気がついたのは、『子どもの話にどんな返事をしてますか? ―親がこう答えれば、子どもは自分で考えはじめる』という本を読んでいたときのこと。
この本では、全体的に子どもを「ひとりの人間」として捉えるようなアプローチが書かれています。つまり、たとえ子どもがワガママを言ったとしても、闇雲に叱るのではなく感情に寄り添ったり、その行動を容認したり、ワガママの原因を突き止めるようなアプローチをするのです。
たとえば、楽しみにしていたピクニックが雨で中止となってしまったエリック。こればっかりは仕方がないことなのですが、この怒りは誰にぶつければよいのでしょうか。エリックは、中止の原因とはまったく関係のない父親に怒りをぶつける手段に出ました。
父親からすれば、自分のせいでピクニックが中止になったわけではないので、たまったものじゃありません。しかし「怒るんじゃない」と逆にエリックを叱る前に、父親は冷静に答えを導き出します。
父親はこう考えた。エリックはピクニックに行けなかったことでとてもがっかりしている。だから、自分の怒りを私にぶつけることで、落胆した気持ちを私と分かちあおうとしているのだ。息子には感情をあらわす権利がある。息子の気持ちを理解し、尊重していることを示すのが、いちばん彼の助けになるだろう。
引用: ハイム・G・ギノット(2005) 『子どもの話にどんな返事をしてますか? ―親がこう答えれば、子どもは自分で考えはじめる』 草思社 P27
ここで大事だと思ったのは、「息子には感情をあらわす権利がある」ということ。
「子どもだから」と言って、大人の都合よく感情を押し殺したり表現することを許さないご家庭があるかもしれません。しかしそんな環境を作ってしまうと、大人に気に入られないといけない、自分の気持ちを話すのは恥ずかしいこと、という気持ちが子どもに襲いかかります。
小学生のころ、家族で外食に行ったときに「大人の都合」でラーメン屋へ行くことになりました。でも僕は本当はファミレスに行きたかったのです。そこでラーメン屋は嫌だ、と言うと
「じゃあ食べなくていい」
「ラーメンじゃなくても、餃子とご飯頼めばいいじゃないの」
などと、次々に責められて、まったく楽しくない外食になってしまいました。そこでちょっと、「ファミレスもいいけど、今日はラーメンに付き合ってくれない?」などと、僕の「ファミレスに行きたい気持ち」を尊重してくれていたのなら、まだ楽しかったと思います。
理由も詮索されずに、目の前の出来事や大人が勝手に決めた行動を受け入れられないと嘆く子どもを、大人は軽視しがちです。それどころか、いつまで文句言うの!などと、ふてくされていることを逆に叱られる始末。でも、そのたびに子どもは思うのです。
大人ばっかりずるい。大人は何も分かってくれない、と。
僕の不登校の原因として、思い当たるもののひとつに「子どもだらけの世界に違和感があった」ことが挙げられます。
両親祖父母の5人家族で育ち、親戚を見渡しても同年代がいない環境で子ども時代を過ごしました。すると、どうしても考えや行動が大人に寄ったものになってしまいます。結果、大人に受け入れられないと生きていけないと感じるから、大人寄りの意見でごまかして自分の感情や思いを上手く言えない。
今でも集団のなかでまず「信頼のおける大人(年上)」を探す癖があるのは、そのせいかもしれません。
だからこそ、子どもには「大人に振り回されない」環境が必要なのだと思います。
子どもは、何か問題が起こったり不都合が生じたときの対処が苦手です。大人になって経験を積んだ上では冷静な対応ができますが、対処法を知らない子どもはとりあえず「怒る」という選択肢を取ります。
それが親の癪に障り、「怒ったってしょうがないでしょう!」と怒りに怒りを重ねる。これでは何も解決していませんし、何より不用意に余計なことを口走ってさらにエスカレートしてしまうことだってあります。だからこそ、子どもの「怒り」という感情を尊重するのです。
もちろん、子どもの言うことを1から100まで叶えていたらキリがありません。でも子どもにだって何かを言ったり感情をあらわす権利があるのです。子どもが正しいことを言っているのに、大人が間違った方向に舵を取ることさえままあります。
不登校の我が子が何を考えているのか分からない、という相談をよく受けるのですが、「子どもが学校に行きたくない」「あの場所がイヤだ」という感情を、まずはそっくりそのまま受け止めて、尊重することを大切にすれば、きっと心をひらいてくれることでしょう。
◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。