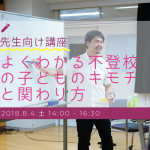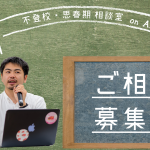「いい子」の正体

最近、「自分のやりたいこと」を口にできない若者と言うのが増えているそうです。
就職試験の面接などで、「これからこの会社でどういうことにチャレンジしたいのか」という問いをぶつけても、途端に口ごもるから結局よくわからず、人事側もほとほと困ってしまう。そういえば「やりたいことが見つからない」と口癖のように言っていた同級生が大学にいたのをふと思い出しました。
では彼らはなぜ「やりたいことが見つからない」のでしょうか。
こんな視点から考えてみましょう。
「いい子を演じる」ということ
- 食事を終えたあとの食器を、子どもたちが黙って流し台へと運んでいく。
- 親がとやかく心配するので、家から通えるA大学を受験する。
今挙げた2つの行動には、ある共通点が潜んでいます。
それは、両方とも「子が親の期待に応える」行動だということ。
もちろん、食べたものは自分で片付ける、という能力を身に着けることは非常に大事なことです。ですが、もしもこの行動が自立への助けではなく「親の機嫌を取るため」だとしたら、実は小さな火種がくすぶっている行動とも言えるのです。
食べたものを自分で片付けないと、お母さんが烈火のごとく怒りだす。怒られるのは絶対に嫌だ。だから、食器を流しへ持っていく。そうすれば、お母さんはニコニコと「いい子ね、ありがとう」と褒めてくれる。つまりただ親にとっての「いい子」「理想の子」を演じているだけなのです。
このサイクルは、ひいては自分の意思ではなく「親の意思」で何もかもを決定してしまう可能性をはらんでいます。
そう、将来のことも。
決定機関が自分ではなく「親」にあるために、本当は下宿して東京の大学に通いたい、けど親が反対するから家から通える関西の大学を受験しよう・・・という思考が働きます。これも結局「親の期待に応えたい」が故の行動。
別に東京の大学を受験してはいけない、なんていう法律も決まりもないのに、親の顔を気にするがために選択肢を狭めてしまうのです。
その結果、「自分の意思」というものを持たない大人に成長し、何がしたいか分からない、自分のやりたいことが見つからない、が口癖になってしまうのです。なんでそうなったかを紐解けば、家庭で親の顔を常に気にしていたり、親の期待に何が何でも応えなきゃいけない、と思って生活していた、なんてことが、実はよくあります。
ちなみに、こうして「いい子」を演じ続けた子どもには長男長女が多く、また「反抗期」と呼べる時期もないことが多いようです。確かに、親の顔を常に意識するということは、その分親への依存度が高いということになるので、反抗することにむしろ恐怖を抱くことでしょう。しかしそれは自立への大きな妨げにもなります。
素直過ぎても、良くない
「いい子」を演じている子どもは、なんでもかんでも素直に言うことを聞こうとします。
親がこう言うのなら自分もこうしなきゃいけない。今宿題で忙しいけど、親がおつかいに行ってほしいと言ってるんだから、優先すべきは宿題じゃなくておつかいだ。
素直でいい子ね、と喜びを感じるかもしれません。しかし、それを続けてしまうと、上記に挙げた悪循環に陥ってしまう可能性があります。
そう、子どもが素直になんでもかんでも聞き入れるのも、問題なのです。
もしも、自分のお子さんが「自分の思い通りに育っている」と感じているのならば、一度胸に手を当てて考えてみてください。果たして、「自分の思い通り」は我が子に悪影響を及ぼしていないのだろうか?間違った方向に進んではいないだろうか?と。
子どもは、いつか必ずどこかで自立するときがやってきます。その自立の妨げにならないように、時には「そんなに素直にならなくて大丈夫なんだよ」と子どもたちにやさしく微笑みかけるのも大切なのではないか、と思います。
(参考)
いい子症候群診断~陥りやすい親子の特徴と新型鬱との関係 – マーミー
親も知らない子どもの顔。いい子症候群の仮面をかぶってしまった子どもの心理とは – Spotlight (スポットライト)