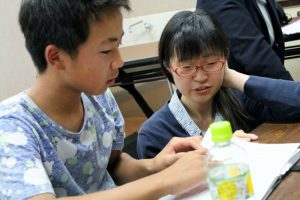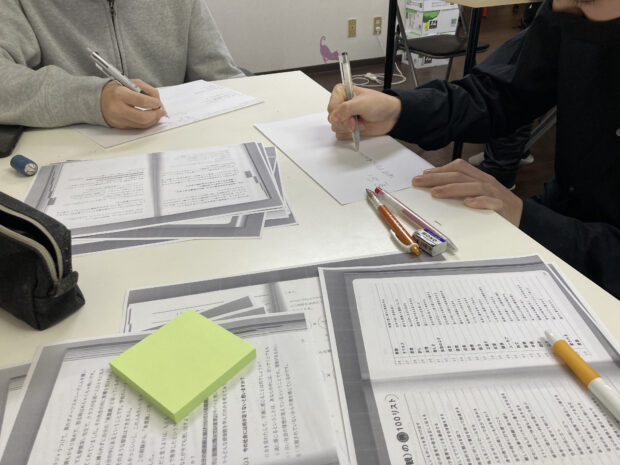「学校に行けない自分は、ダメな存在だ」
「なんで自分だけ学校に行けないのだろう」
「今日も行けなかった。またお母さんが悲しんでいる。自分は生きていていいのかな」
不登校の子どもたちの「自己肯定感」の低さは大きな課題です。親の喧嘩の声が耳に入っても「お父さんとお母さんの仲が悪いのは、自分が学校に行けていないせいだ」と、どういう形であれその責任を子どもが背負い込みます。たとえ喧嘩の原因が違うところにあったとしても。
この「何をやっても自分を否定する」「自分に自信がない」というところに将来を悲観して、「うちの子はこれからちゃんと生きていけるのだろうか」と深く悩む親御さんも非常に多いです。たしかに、子どもたちと日々接していても、こうしたマイナスな言葉を自分自身に投げかけることがよくあります。
そんな子どもたちに、なんと声をかければいいのだろう。
こんなことを考えていた矢先、ある保護者の方が、「もう、うちの子がちゃんと生きていてくれてたらそれでいいや、って最近思うようになったんです」とお話しされているのを耳にして、僕は琴線に触れるような思いをしました。
僕が高校生のとき、父親が大腸がんを患いました。
当時16歳、不登校から通信制高校に通いはじめてやっと1年が経つころでした。当然、将来どうしたいのか、何をやりたいのかなんてまるで決まっていません。なのに、いま稼ぎ頭の父親が万が一いなくなってしまったら、自分の人生はこれからどうなってしまうのだろうか。
そして、その前の年に苦心の末入学した高校をリタイアしたときにずっとそばで支え続けてくれてきた父親がいなくなったら、自分は誰を頼りに生きていけばいいのだろうか。
しかも父親の大腸がんが発覚するわずか2ヶ月前、同居していた祖父が朝起きたら心筋梗塞で亡くなっていたことも、僕の混乱と不安に拍車をかけていました。身近な家族が次々亡くなるという恐怖と切なさが、思春期真っ只中の僕を完全に支配していました。
大腸がんの手術のためにしばらく父親が入院すると、勉強が手につかないほど、頭が混乱に混乱を重ねて、学校へ行くのも億劫になりました。そのとき、はじめて父親という存在の偉大さ、そして「お父さんが生きていることがこんなにもありがたいことなのだ」ということを痛感したのです。
かねて父親は「オレは60で死ぬんや」と豪語していました。その言葉通り、10年間大腸がんと闘い続けて、数え年60歳で父親は2年半前に亡くなりました。臨終の瞬間はやはり「当たり前のように父親がいてくれないことの寂しさ」に、病室で父親の亡骸を囲み家族全員で泣き崩れました。
まもなく平成が終わりますが、この父親が大腸がんとともに生きた10年間、つまり平成3分の1は、僕が死んで父親の下に行ってもなお一生忘れない10年間になるだろうと思います。
たしかに現実として、子どもに元気がない、学校に行けない、ということがあると思います。その様子に直面したら、きっと子ども本人だけでなくてそれを見守る側も辛い気持ちになるでしょう。僕自身も露骨に感情が伝わってきやすいタイプなので、生徒が落ち込んでいるとすごくいたたまれなくなります。
でも、それでもなお、目の前の子どもが「いなくなってしまう」より、全然良いことなのです。
僕は父親に限らず、これまでに何人か友人・知人を亡くしています。「あの人、亡くなったらしいよ」という知らせを聞いたとき、僕はいつも頭が真っ白になって、その生前の様子や「こうすればよかった・・・」という後悔に襲われます。
だからこそ、相手がどんなに苦しんでいても、辛い思いをしていても、「生きていてくれるだけで、それで良い」という考え方が生まれるのでしょう。
「もう、その人との思い出を作ることができない」からこそ、人が突然いなくなる悲しみというものは計り知れないものがあります。とはいえ、人は生まれた以上必ず死ぬことだけはハッキリしているのでどうしようもありません。
でも「生きていてくれるだけで、それで良い」という考え方で救われ、死ぬことからいったん逃れられる人が絶対にいるはずなのです。その接し方で、目の前の辛い思いをしている子どもたちが笑顔を取り戻してくれる可能性があるかもしれない。
あの日の保護者の方のお話で、僕はそんなことを思いました。
前述の通り、もうあと1時間と少しで30年間続いた平成の時代が終わり、新しい元号「令和」を迎えます。
その新しく始まる令和の時代を担っていくのは、いま小中高生の子どもたちであることは間違いありません。僕もどちらかといえば令和の時代を担っていく世代のひとりなのかもしれませんが、同時に若い世代を育てていく必要のある年代であることも言えると思います。
いま、不登校に限らず、自己肯定感が低かったり自分に自信を持つことのできない子どもたちが多くなりました。平成の30年間は、それまでの大正や昭和の時代と比べ、子育てが根本から大きく変わってきた時代だったと感じます。
これからはじまる令和の年代になると、さらにもっと子育てが変わることでしょう。
どれだけ辛い思いをしていても、そのあるがままを認める。「こうして元気に生きていてくれるだけで嬉しい」とメッセージを伝えるのはなかなか照れくさいかもしれませんが、「いてくれるだけでそれでいい」という考え方で子どもたちと接すれば、少し肩の荷が降りるかもしれません。
令和の時代が少しでも、子どもたち、いやすべての人たちにとって生きやすく、希望を持つことのできる社会であることを心から祈ります。そして、僕自身もひとりの子どもと関わる人間として、少しでも子どもたちがほっとできる社会や居場所を新しい元号でも作り続けていきたい、と思います。