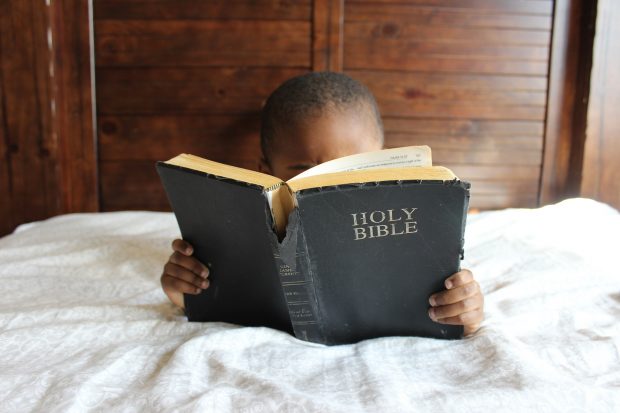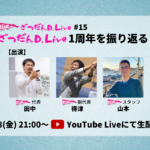不登校の子どもに「勉強してほしい」と願う保護者のみなさんへ。
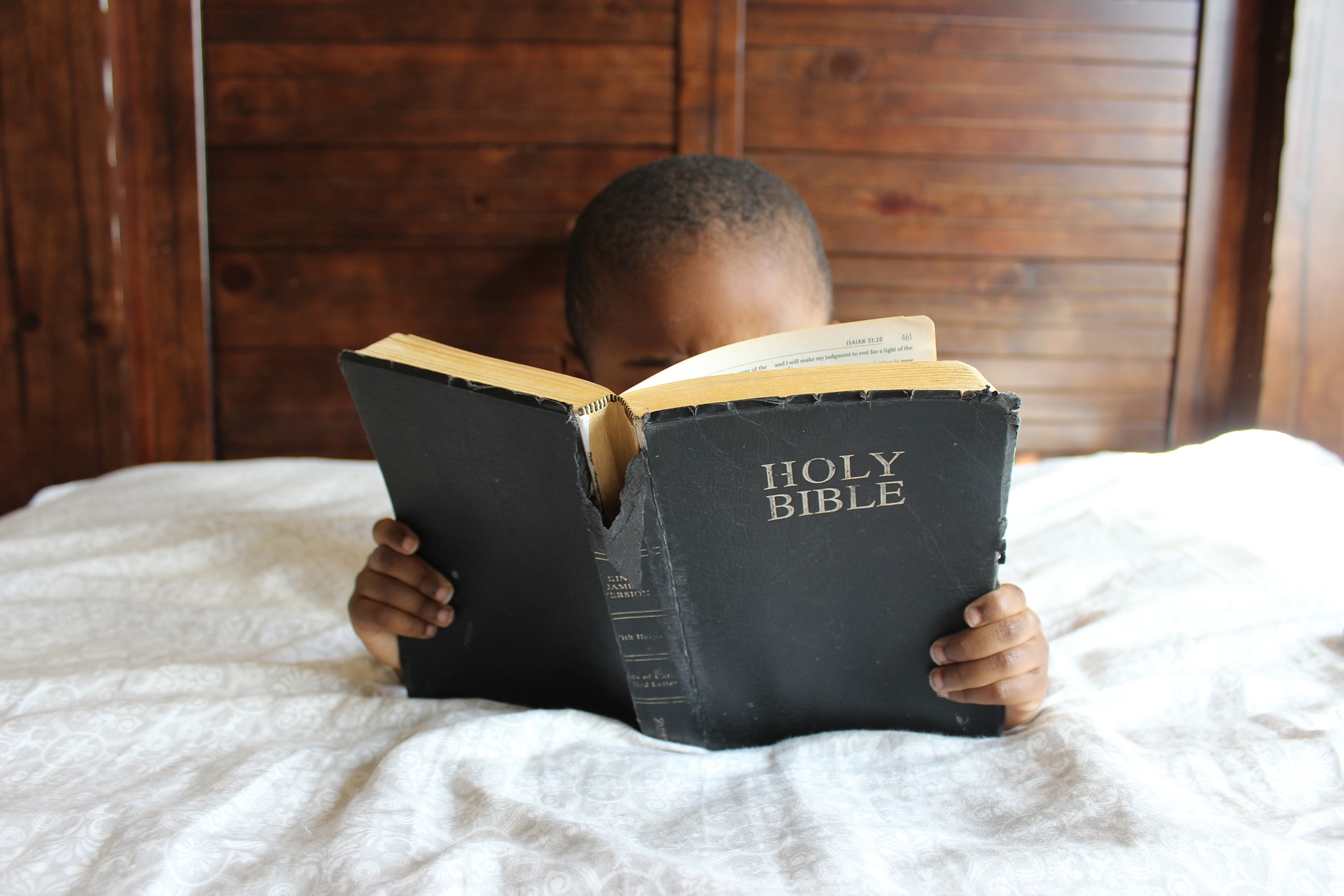
当たり前ですが、不登校の子どもたちは学校の授業を受ける機会がありません。たとえば塾の映像授業を受けているというのなら別ですが、少なくとも教室の一番後ろにビデオカメラを置き、その授業をどこかへライブ配信しているような例はないはずです。
それもあってか、不登校の子どもを持つ保護者の方から勉強にまつわる相談やお悩みをよく聞きます。いや、もしかしたら不登校に限らず「子どもが勉強しない」という悩みは、あらゆる保護者の方がお持ちなのかもしれません。
不登校の子どもに限って言えば、子どもが学校に行かない間もほかの生徒たちはどんどん先へ進んでいきます。そうして置いていかれる「不安」があるのは、当然のことだと思います。ならば家でそれを補うしか方法はないわけです。が、子どもが手を出すのは問題集ではなくスマホ・・・。
この子はこの先どういう人生を歩んでいくのだろうか、と勉強をほっぽり出してゲームやネットに興じる子どもを目前にため息をつく家庭も多いと思います。
では、「(不登校の)子どもが勉強しない」とお嘆きの保護者のみなさんに、ひとつ質問させてください。
なんで「(不登校の)子どもに勉強してほしい」と思うのでしょうか?
教員という職に就いてから、「勉強」という言葉があまりに抽象的で、ボヤッとした言葉であることをものすごく痛感しています。
ひとくちに「勉強」と言っても机に向かって問題集を解いたり授業に出席することだけが勉強ではないですし、なにも「勉強」がすなわち「学力」を獲得するためのものではないということも、日々子どもたちと関わる中で見えてきたことです。
たとえば、わからない漢字や言葉を人に聞くことは、コミュニケーション能力を育む一助になります。その前に自分で調べてみることで、問題解決能力を伸ばすことに繋がります。難しい数学の方程式を諦めずに解くことは忍耐力を鍛えることになりますし、勉強そのものが自制心を高める訓練にもなるでしょう。
これ以外にもまだまだ、「勉強」することで獲得できる力が、たくさんあります。
これまで幾度となく「(不登校の)子どもが勉強しない」と困る保護者の方を見てきました。参考になればと思い、様々な勉強のやり方も提案しました。でも、あらゆる能力を伸ばせる勉強をすることで、子どもにどういった力を獲得してほしいのでしょうか?
不登校の子どもたちがなかなか勉強に手を出さないひとつの大きな原因が、ここに隠されているように思います。
彼らは日々、とにかく「学校から逃げること」に必死です。もしかしたら、問題集1冊を目の当たりにしただけで、学校のことを思い出してしまう子もいるかもしれません。とてもこの先どういう学校へ進み、どういう職に就くかなんて考える余地がない中で、親は「勉強しなさい」と言う。
僕は、勉強に手を出さずして当然だと思います。
なぜなら、勉強に対するゴールや目標があまりにも不透明すぎるからです。
直前に定期試験が迫っているとか、なにかの資格取得やどうしても行きたい学校があるというのならば話は別かもしれませんが、そういうわけでもない、ただ漠然と「勉強しなさい」と言っても、子どもは絶対に動かないでしょう。これは、不登校だとかそんなことは関係ないと思います。
「なんのために」勉強してほしいのか。なぜ勉強しないことがいけないのか。もしも学力を高めてほしいのなら、どうして学力を高めてほしいのか。
このあたりを明確にした上で「勉強しなさい」と言っている親は、どれくらいいるのでしょうか。
そして、なかには子どもがスマホやネットに夢中なあまり、ほかのことにも手を出してほしくて「勉強しなさい」と声掛けする方もおられることでしょう。
前述しましたが、「勉強」と言っても机に向かって問題集を解いたり授業に出席することだけが勉強ではありません。「またYouTubeばっかり観て・・・」とお嘆きの保護者の方も多いと思いますが、もしもYouTubeで観ているのが「世界史の授業動画」だったとしたら、どうでしょうか。
スマホとにらめっこして「また遊んでる・・・」と思っているのが、実はアプリで英単語の勉強中だったとしたら、どうでしょうか。テレビ番組だって、内容によればものすごく勉強になる番組がたくさんあります。
さらに、最近弊団体のフリースクール「昼TRY部」で流行しているのが、全員(スタッフ含む)でジャンケンして負け残ったひとりが、目の前の数学の問題を解く、というもの。こうしたゲーム性を取り入れると、子どもたちはおもしろいくらい数学や英語に興味を示します。
これは僕の偏見かもしれませんが、「勉強しなさい」という人に限って、なにかこう勉強に対する固定概念にしばられているような気がします。本来なら、なんでも教材に早変わりし、いくらでも学ぶことができるものこそが「勉強」なのでは、と思います。
「勉強」という言葉があまりに抽象的で、ボヤッとした言葉である、と先ほど書いたのは、そういうことなのです。
「勉強してほしい目的」「身につけてほしい力」「教科」「勉強する手段」・・・。これらを無限に組み合わせることによって、はじめて「勉強」というものが成立するわけです。
果たして、あなたが子どもに「勉強を通じて本当に身につけてほしい力」はなんなのでしょうか。それをあやふやにして子どもに「勉強しなさい」と言っていないでしょうか。ときには勉強しなさいと口うるさく言うのではなく、あらゆる組み合わせで勉強する意義、理由を説明してみてはいかがでしょうか。
そして、勉強しなさいと言ったところで勉強するのは親ではなく子どもです。これはアドラー心理学で言う「課題の分離」に当たる部分です。果たしてその「勉強しなさい」という声かけが本当に必要なのか、勉強しない子どもを目の当たりにして、親の側からも考える必要があるのかもしれません。
◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。