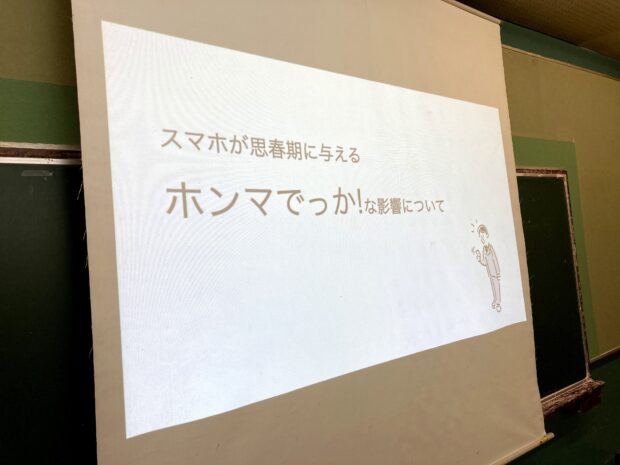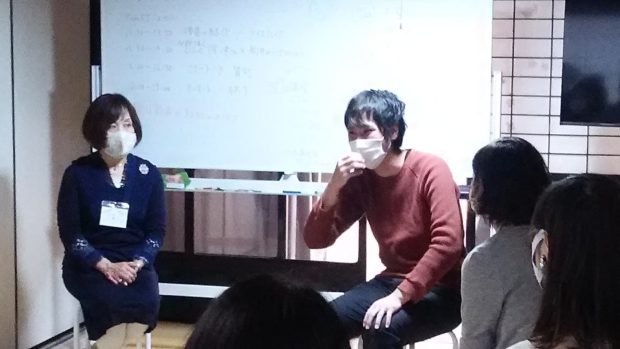先週の予告通り、「みんなの学校ごっこ in 東山」にてワークショップの講師を務めてきました。
今回ワークショップの題材として取り上げたのは、「サザエさん」。
上記のスライドのタイトルの通りに告知もお願いしたのですが、参加された方にどうしてこのワークショップに参加したのか聞いたところ、多かったのが「そもそもサザエさんが理想の家族とされていることを知らなかった」ということ。
僕のほうでも、このワークショップを仕切るにあたって「サザエさんって理想の家族だと思いますか?」とリサーチしたところ、これが意外とそう思われていないんですよね。
上記の「そもそも知らなかった」という意見のほか、多かったのが「あれは昭和時代の理想の家族であり、平成の今はふさわしくない」という意見。これは、教員を目指す人に多い意見でした。
では、なぜサザエさん一家が「理想の家族」と言われるのか?
たとえば子どもがひとりで食事をとる「孤食」家庭も増える中、基本的にちゃぶ台に7人そろって食事する姿が理想だとか、いろんな視点もありましたが、今回は「関係性」に着目して話を展開していきました。
カツオを例にとれば、母親であるフネや友達である中島くんや早川さんに相談しにくいことでも、従兄弟関係になるノリスケには気軽に相談できる。どういうことかと言えば、フネは「タテの関係」、中島くんと早川さんは「ヨコの関係」なのに対し、ノリスケは「ナナメの関係」だから。
つまり、何かを指導したり叱る立場にある上下関係でも仲間意識の強い対等関係でもなく、子ども目線で暖かく接してくれる年上の「ナナメの関係」こそが、サザエさんが理想の家族と言われるひとつの理由ではないか、ということです。
作中、カツオはよくノリスケにサザエや波平の愚痴をこぼすシーンが見られますが、これが「ナナメの関係」の最大のメリットなわけです。家族に対してよく思っていないことでも「ナナメの関係」というクッションを挟むことで適度な関係を築けるのです。
 そして、タラちゃんはこの「ナナメの関係」と4人も同居していることになります。
そして、タラちゃんはこの「ナナメの関係」と4人も同居していることになります。
ナナメの関係、というのは年の離れた親戚でも成立する関係です。タラちゃんから見て波平やフネは祖父母にあたりますが、この2人は上下関係でも対等関係でもありません。「カツオッ!」と怒鳴り散らす波平も、タラちゃんには非常にやさしく接しています。
同様に、叔父叔母の関係であるカツオとワカメも、「少し年の離れた弟」のように普段から暖かく接しています。4人もの「ナナメの関係」に囲まれたタラちゃんにとって、この家庭環境はとてもすばらしい状況にあるのです。
ちなみにこの「ナナメの関係」は、「ちびまる子ちゃん」がものすごくうまい描き方をしています。
母親に叱り飛ばされても、ヒロシ(父)に冷たくあしらわれても、お姉ちゃんと喧嘩しても、まる子は友蔵(祖父)のもとへ行けばすべてを受け入れてもらえます。友蔵はいつでもまる子の味方、まる子が悲しんでいると一緒に悲しんでくれます。これこそが「ナナメの関係」。
この友蔵のフォローにより、まる子の母親は安心して叱ることができます。現代の家庭では両親どちらかが叱り役になればフォロー役もこなさなければならないのですが、ちびまる子ちゃん一家ではこの分担がかなりスムーズにできています。
正直なところ、僕はサザエさん一家よりちびまる子ちゃん一家のほうが「理想の家族」だな、と思います。
「ナナメの関係」は親戚のみならず、サザエさんでいう伊佐坂先生や三河屋のサブちゃんのように、地域に住むおじさんやお兄さんでも成り立つ関係です。しかし、今地域で学校から帰ってきた子どもに「おかえり!」なんて声をかければ、すぐに不審者として扱われてしまいます。
そんなこともあり、近所どころか隣人がどんな人かも知らない、地域とのつながりが希薄な家庭も多く増えています。ところが、本来子どもは家庭で育てる存在ではなく地域で育てる存在であり、地域のおっちゃん・おばちゃんの付き合いから得るものも多いはずです。
子どもの成長にあたって「ナナメの関係」というのはどうしても必要不可欠な存在なのです。
「ナナメの関係」が不足していれば自己肯定感もはぐくまれにくく、何かを相談するにしても相手の選択肢が限られてきます。多様な価値観に触れることもままなりません。「ナナメの関係」が多ければ多いほど、子どもたちがより安心して成長できることにつながるのです。
最初講師控室に案内されて名札を手に取ったときに「先生」という敬称だったので思わずたじろぎましたが、非常に貴重な経験をさせていただきました。「サザエさんってワークショップになるんですか!」と他の講師の方から驚かれたりして、このテーマやってよかったなあと思います。
末筆ですが、今回参加して下さったみなさん、そして「みんなの学校ごっこin東山」を主催された東山いきいき市民活動センターのみなさん、本当にありがとうございました!