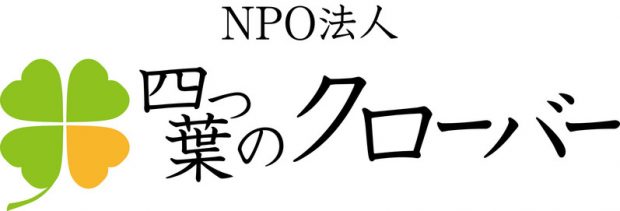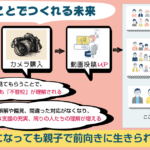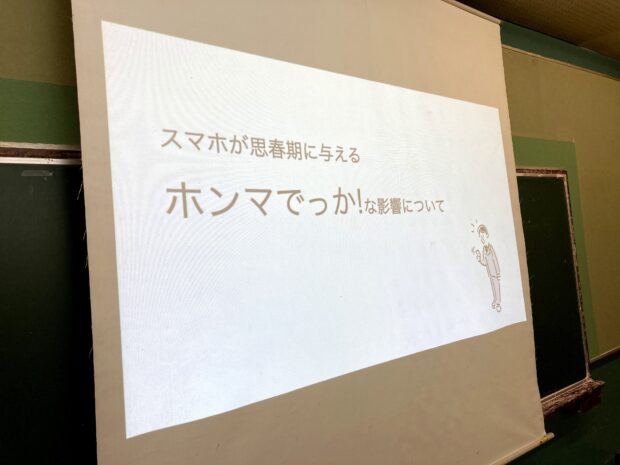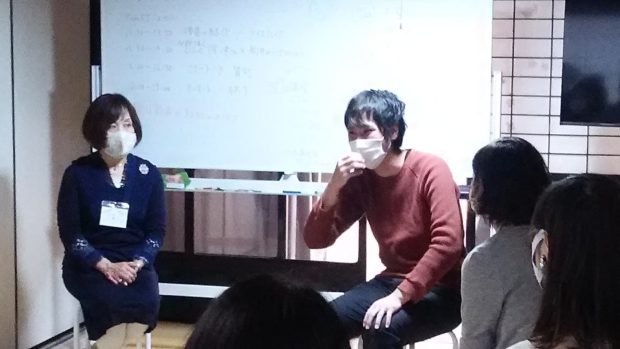児童養護施設を出た青少年が就職してから3か月で離職する割合をご存知でしょうか?
認定NPO法人ブリッジフォースマイルの調査によりますと、
13%だそうです。
数字だけみると少なく思うかたもおられるでしょうが、10人に1人が3か月で退職するというのは非常に高い割合だと私は思います。
退職した子どもたちは、また別の仕事についてもすぐ辞めてしまうことをくり返すそうです。
施設を出た子どもたちが定職につき、自立していくことをサポートする団体が滋賀県の守山市にあります。
認定NPO法人四つ葉のクローバーです。
http://www.yotubanokuroba2013.com/
施設を卒業した子どもたちが一緒に暮らすシェアハウスを運営しているのが、団体の大きな特徴です。
代表の杉山真智子さんに、立ち上げた想いやどのような活動をしているのかお答えいただきました。
——まずは、団体を立ち上げたきっかけを教えてください。
杉浦さん:私は、児童養護施設のボランティアを4、5年前から週一回していたんですね。そしたら、子ども達が私が来るのを待つようになって、当時幼稚園の子が「帰りたくない、おばちゃんの子にして」っていうんです。
だから里親の資格をとりました。子ども達に「おっきな家作って待ってるね」と約束をしたので、物件をさがして法人の申請もしました。これがきっかけですね。
施設の先生は本当にしんどい状況です。子ども達は、これだけやってもいけるだろうと安心するから先生にぶつかってきます。でも、受け止めきれないと先生も警察を呼んじゃうんですね。それに子どもはショックを受け、信頼感をなくしてしまいます。
子ども達はというと、根はすごく優しいです。ボランティアをしていたときだって、一緒に四つ葉のクローバーを探してたら「何回も見つけたから、どこにあるか知ってるでー」って言って、見つけたクローバーを私にくれるんです。私が「あんたが幸せになってほしいから、もっとき」って言っても、「いいねん、すぐ見つけられるし」っていって、私にくれようとするんです。
施設の子ども達は、原則として18歳で施設を出ないといけません。でも、施設を出てからの困りごとはたくさんあります。18歳になったから、もう自立しているだろうと思われるでしょうが、自立というのは小さいことから愛されてこそ少しずつ育まれるものです。18歳だからポンと施設を出されても、愛情のタンクが空っぽなんですから、自立した生活なんて難しいです。仕事に就いてもなかなか続きません。一ヶ月や三ヶ月でやめることもたくさんあります。長くても1年続いたらいいほうですね。
——シェアハウスを運営されているそうですが、具体的にどんな活動をされていますか?
シェアハウス外観
杉浦さん:シェアハウスは7部屋あります。もちろん、自立の支援として行っていますので、最長3年(大学生は4年)を原則としています。ただ一緒に住むだけじゃ無くて、イベントを考えたりパソコン教室や高卒認定試験の学習会をしたりもします。
リビング
今年は、このシェアハウスを出た人の次のステップとして「みかんnaカボス」というサテライトハウスも始まりました。ここには最長5年まで住めます。ここには、シェアハウスを卒業した人が住み、自立に向けた支援を行なっていきます。「みかんnaカボス」はハイツなんですが、このハイツは支援者のかたが紹介してくださったんです。
あとは、守山市の社会福祉協議会の要望をうけて「ひきこもり支援 あすか」を二ヶ月に一回行なっています。ヨガをしたり、パソコンをしたりしています。やることはきた人と相談しながら決めています。
——単純にシェアハウスを運営するというわけではなく、イベントの開催や就職に向けたスキルを養うなど、たくさんのことされているんですね。それらの活動の中で、子どもと関わるうえで特に気をつけていることって何ですか?
杉浦さん:聞くことですね。私たちは素人ですけど、相手の話を聞くことならできます。無口な子でも、話を聞けばしゃべります。自分がいいたくないこともしゃべってくれます。聞くことを大切にするのは、子ども達自身が自分のルーツを知る必要があると思うからです。自分の使命や自分の人生についてが腑に落ちてないと、社会のことにも目が向きません。それを深掘りし、子ども自身がきづくためにも聞くことを大切にしています。
——聞くためのポイントなどはありますか?
杉浦さん:気になる子は、ピックアップしてしゃべるようにしています。呼び出すこともあれば、何か用事を作ってドライブいこうって声をかけたりもします。車の中だと横並びだから話しやすいですよね。
あとは、自分が人の役に立ってると感じられることが自尊心につながるとも思います。一緒にイベント準備をしているときも、シェアハウスの子ども達が私のことを気遣ってくれて、自分たちで準備をすすめることもありました。自立して力がついていくのが見えるのがおもしろいですよね。やりがいもあります。
——最後に保護者や先生などへメッセージをお願いします。
杉浦さん:自分の根っこにある力を引き出して生きることですね。子どもに何か言っても、それが自分にできていなかったら子どもは聞きません。すぐにバレます。自分がどう生きていこうとしているのか、それを示していくことで子どもが変わります。だから自分のエネルギーを出していくんです。
子どもは鏡です。自分はOKとおもっていても、子どもに対して「なんなん?」と思った時に自分を振り返ってみてください。実はOKじゃない部分に気づくチャンスだと思います。
ーーなかなか知る機会のない児童養護施設を出た子ども達の実態や、子ども達を支える杉山代表の力強い思いをお話から感じました。貴重なお話をありがとうございました。
四つ葉のクローバーさんに取材させていただいた記事は、子どもの自信白書’16にも掲載されます。
ご期待ください!