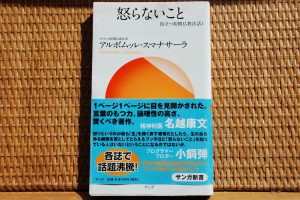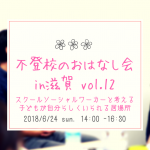こんにちは、NPO法人D.Liveの得津です。
「ねえ、明日学校休んでもいい?」
さっきまで元気にしてた子どもがちょっと俯き加減で、こんな風に言ってきたら保護者の立場としてはドキッとしますよね。
「え、学校でなんかあった?」
「イジメられた?」
「見た感じ体調不良でもなさそう。いいよって言ったら、このままずるずると休んで不登校に…?」
いろんな不安が頭をよぎります。
今日は、フリースクールの運営や不登校支援をしている立場として、「ねえ、明日学校休んでもいい?」と言われたときの関わり方、学校や子どもの理解についてお話しします。
●ポイント1:休みたいと言った子どもは何もおかしくない
まず最初にお伝えしたいのですが、学校を休みたいと言ったお子さんは何もおかしくありません。後述しますが、再開した学校はこれまでの学校とは違っています。子ども達の現状としては適応すべきことが多すぎて学校がストレスを感じやすい場所になっています。
そんな場所から、ちゃんと危機回避センサーが働いて「休みたい」と言えたことは良いことだと私は考えます。このセンサーの働きを無視して無理やり学校に行ってうつになるとか、休みたいという声に全く取り合わず学校に行かせて知らないうちに信頼を損なうとか、そっちの方が後々大きな問題になります。
それに、この状況下で休みたいという子どもはおこさんだけではありません。みんなそれなりにストレスや疲れを感じていますし、D.Liveの教室から卒業した生徒達からも、学校行けなくなってきたと連絡をもらいます。お子さんだけがおかしいのではありません。(みんなしんどいんだから行きなさいというのもまた違います。みんなしんどいのなら更に問題は深刻なので、いっそご家族みんなでリフレッシュするとか、それぞれが日替わりでストレス発散に出かける方がずっと健康的です。)
●ポイント2:学校はこれまでの学校ではなくなってしまった。
先ほどもチラッと言いましたが、学校はこれまでの学校とずいぶん違っています。マスク着用が基本ですし、毎日検温している学校も多いでしょう。中にはフェイスシールドや机を一つ一つ段ボールで囲う学校もあるようですね。程度はどうあれ、感染防止の観点から、新しいルールや新しい過ごし方が加わりました。
ですから、この4、5ヶ月を
休校前(これまでの学校)→休校中だから一時的にこの生活に適応する→学校再開(これまでと同じ)
のような、自粛期間中だけ新しい生活に適応しないといけなかったよね、という捉え方では子どもの気持ちや学校の理解を誤ります。
実際は、
休校前(これまでの学校)→休校中だから一時的にこの生活に適応する→学校再開したけどこれまでとルールや様式が違うのでまた新しく適応しないといけない
こんな感じです。休校から学校再開までの3ヶ月くらいの間で新しく適応しないといけない環境に2回も変わってしまった。社会人でいうと業種の違う会社を短期間で2度転職したようなものです。ルールは違うけど小うるさいことだけは共通する自治体に短期間で2回引っ越したと考えてもいいです。
かなりストレスが掛かりますよね。更にいつも通りストレスがかかる事柄もこなしているんです。
●ポイント3:今は四、五月にやることを一気にこなしている時期。
四月から六月までの学校行事や学校生活って、だいたいこんな感じです。小中高をひっくるめているので関係ないものは省いておいてください。
・入学式/始業式
・部活の勧誘や先輩後輩の付き合い
・家庭訪問
・遠足
・実力テストや定期テスト
・委員会や学級委員などを決める
・新しいクラスに馴染む
・新しい先生たちに馴染む
・春実施のところは運動会
このうち、遠足や運動会など楽しいものだけがカット/延期されて、代わりに感染防止策への適応や積み残した学習を進めるなど、楽しくない物が入ってきます。
元々新しい始まりの四月は、みんな慣れるのにしんどくてゴールデンウィークをめざしてなんとか頑張ろうって感じだったのにそれもない。分散登校が若干の助走期間として機能しましたが、おそらく不十分でした。かといって、助走期間を長く取れるほどの余裕もないですし、結果として先生も子ども達も少しずつスピードに乗るのではなく、一気にトップスピードまでアクセルを踏むような生活になってしまいました。
●ポイント4:体力の低下と暑さ
あんまり言う人いないんですけど、体力の低下も登校し続けることのしんどさに影響しています。本来なら毎日登下校して、体育や部活もして保たれていたはずの体力が、この休校期間で一気になくなってしまいました。加えて、初夏のこの暑さです。単純にしんどいですよね。
●ポイント5:休ませていいです
さっきから子どもや学校の現状ばかりを書いてきましたが、やっと関わり方の話です。お待たせしました。
「休んでいい?」と聞かれたなら、「いいよ」と答えてあげてください。
休むのはいいけれど保護者の立場としては理由が気になると思うので、「なんで?」と聞くと思うんです。きっと。そこで、これといった答えが出なかったら上記に書いてきたことが原因だと思います。お子さんの発達段階にもよりますが、「適応すべきことが多い3カ月だったのでちょっと疲れました。」なんて言えるくらいに、この休校期間と自分を客観的に理解したり、時間感覚をもったりするのは大人に近くないと難しいです。中学生でもここまで言語化するのはまだ無理だと思います。
他方、いじめられているとか、イヤな子がいて…とかでしたら子どもを守るためにもお休みさせて、学校の先生と一緒に今後のことを考えていきましょう。
ここで休んだからといって不登校一直線にはなりません。子どもだって行かなきゃいけないことはわかっています。言葉にできるかはまた別ですが。
●ポイント6:休みかたを考える
もし話せるなら、次からも同じような休みたい気持ちが出たときにどうするかはお子さんと一緒に考えてもいいかもしれません。六月は学校行くのは週4にするとか、自分一人でもできる宿題なら家でやるとか、お子さんの負担にならない形で。
「風邪でもないし熱があるわけでもないのに学校を休んでみんなと違うことをしている」
こんな後ろめたさを感じているお子さんもいるでしょうから、そんなお子さんには「有給制度ってことにしよっか!」と、お休みすることに名前をつけてもいいかも知れません。
●ポイント7:学校の先生に相談する
学校を休ませて数日。休みが一週間、二週間続きそうな感じがするなと思ったら、早いうちに学校の先生に相談した方がいいと思います。何を話すかですが、午前中だけ来たらいいとか午後から来るなどの登校の仕方や、スクールカウンセラーさんの利用の仕方についてですね。
スクールカウンセラーなんて言われると「いよいよ大変なことになってしまったんじゃ…」と思われるかも知れませんが、早期に心のケアをすることや、子どもが気持ちを吐き出せることは、それこそ大変なことにならないようにする大事なことなんです。
子どもの心のケアは、学校再開前後からカウンセラーや不登校支援の専門家から言われてきました。スクールカウンセラーを始め、学校の先生も、私たち不登校支援に関わる人間も、早期に心のケアをしなければと思っています。
制度的、物理的に予約がなかなか取れないなどはあるでしょうけど、皆気持ちとしては力になりたいと考えています。
※トピックがずれるのでここでは書きませんが、休みが続いたし「明日学校行くわ」と言って当日に行けなくなって学校を休んでしまうことも、ままあります。これも同様に専門家に早めの相談が望ましいです。D.Liveでもお力になります。
最後に
「明日学校休んでもいい?」って言われたら、ドキッとしますよね。なんなら自分も休みたい。休んでいいと言ったものの。家でゆっくりしてる子どもを見たらイラッとすることもあります。でも、そこは、どうかお子さんと自分を分けて考えて欲しいのです。仕事もして家事もしてたら一日の時間なんて待ったなしです。
保護者さんも子どもと同じく新しく適応しないといけないことがあるんですから疲れます。そういう点では、社会全体が疲れの時期に入ってると考えられます。何気ない毎日でもご褒美3倍。自分も休む。これは、不登校支援に携わる中で保護者さん達から教えてもらったことの1つです。
私たち大人は小さい頃に、頑張ることはたくさん教えてもらいましたけど、休むことは習いませんでした。けど、休むことも頑張ることと同じくらい。いえ、もう今の社会では頑張る以上に重要なことです。私たち大人もこっそり休みましょう。手を抜けるところは抜きましょう。全然悪くないです。