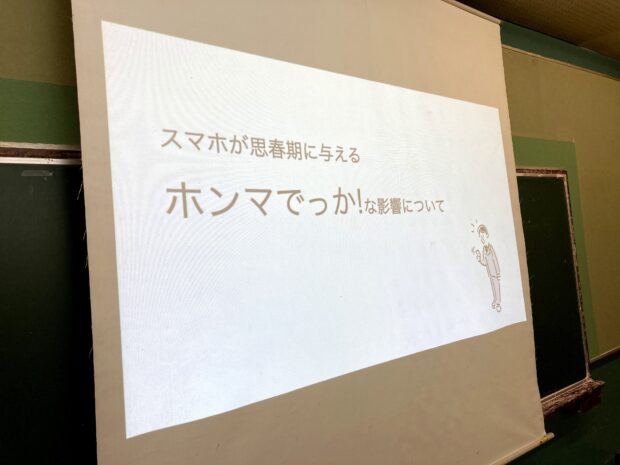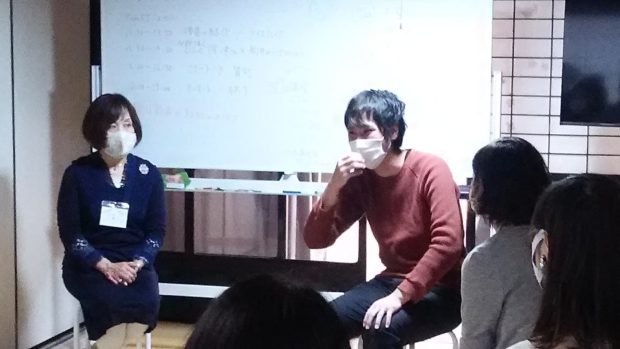こんにちは。
D.Liveスタッフの得津です。
先日、大阪府岸和田市の生涯学習課さまからご依頼をいただき、「放課後子ども教室」を担当されている地域の方々へ、「子どもの褒めかたと叱りかた」というテーマで講演をしてきました。
「放課後子ども教室」というのは、学校の空いている教室で、放課後に子どもたちが地域の人に宿題を見てもらったり、休日には昔遊びや工作をしたりする大阪府の事業のことです。
事前の打ち合わせでは、昔と違って叱っても全然子どもが言うことを聞かないから困っている、という声をいただきました。だからこそのテーマを「子どもの褒めかたと叱りかた」にしたのですが、もっと根っこには、どうしたら子どもたちが落ち着いて勉強できるのかという問いがあるだろうと思い、褒める・叱ると全然違う話をしました。
ウケないだろうと思ったら、予想以上にウケが良かったのでブログにも掲載します。
あとは、子どもの話の聞き方などいつもの話をしました。
みなさん、こんにちは。得津と申します。
今日はお声がけいただきまして、ありがとうございました。
子どもたちが落ち着いて勉強するために、私たちは何ができるのか。
放課後子ども教室と似ている事業を私たちD.Liveはしております。
「つどとこ」と言って、中学生向けの事業です。これは子ども食堂みたいなもので、一緒に勉強したり、地域の方々が作ってくれた美味しいご飯を一緒に食べたりして過ごしています。
今日は、つどとこでどんな苦労があって、どんな方法で改善していったかをお話しすることで、みなさんの教室に生かしてもらえればと思います。
まずスタートしてすぐにピンチがやってきました。子どもたちに指示が入らない。どうも雰囲気がふわふわしているんですね。
お客様気分のところもあり、これではダメだと思い、大人たちで対策を考えることにしました。褒めるとか、叱るなんて話も出たのですが、そもそもつどとこがどんな場所か共有できていないところに問題があるのだと気づきました。
ですから、大人と子どもとみんなでつどとこをどんな場所にしたいか、スローガンを話し合って決めることにしました。すると、途端に落ち着いてすごせるようになりました。
みなさんの教室は、どんな場所でしょう。
どんな風に過ごしてほしいと思っていますか。
また、それは子どもたちに伝わっているでしょうか。
これが意外と伝わっていないんです。毎日通っている自分のクラスの学級目標さえ、言えない子どもたちもいるんですから、週1回くるだけの教室のスローガンなんてなかなか理解できません。
つどとこでは、新しい生徒が来るたびに繰り返し繰り返し説明しています。もう長くいる生徒は飽きています。それはわかっているんですが、やっぱり何度も繰り返し語る。口にすることもあれば手紙にすることもあります。あの手この手でスローガンを浸透させるようにしています。
けれど、3年目に再びピンチが訪れました。
全然生徒が勉強しないんです。3年目にもなると、生徒も増え、中には長く勉強から遠ざかっている子もいました。このような子達も含めて、勉強できるために4つの視点で改善できる部分はないか探すことにしました。
・場所 (使う部屋、机、椅子、それらの配置について)
・内容 (勉強や特別活動など、その場所でとりくむこと)
・関係性 (学年、男女、一人、ペア、グループなど)
・道具 (プリント、筆記用具など)
この4つの視点で考えて、以下のような変更をつどとこでは行いました。
つどとこの場合
・場所
→活動時間だけ借りているので、変更は不可能。
・内容
これまで:決まった時間まで勉強させていた。一人で取り組む人と、教えて欲しい人に分けていた。
かえたこと:勉強が苦手な生徒が多いので、大人一人につき、三・四名程度を見るような個別指導や少人数指導の塾に近い形にしました。一から教える気持ちで関わっています。勉強の時間も「10分勉強・2分休憩」を4セット取り組むようにし、細かく集中できるようにしました。休憩中も何をしてよくて、何をしてはダメかを伝えています。
・関係性 (学年、男女、一人、ペア、グループなど)
これまで:自由
かえたこと:特に勉強したがらない生徒は、自分が引き受けることにしました。この辺りはみなさんで相談された方がいいと思います。
・道具 (プリント、筆記用具など)
これまで:勉強の日は各自で持参。
かえたこと:そもそも問題集などを持っていない生徒もいるので、こちらで用意しました。最初は数学と漢字プリントだけでしたが、それもしないので、本人が興味のある教科のプリントや、パズルのようなプリントを用意しました。プリントを置く位置も、生徒が使う机に直接置いてみるなど、何か変化をつけるようにしました。
理想はマクドナルドのように、誰もが店に入ったら何をすればいいかわかる状態をつくることだと、ぼくは思います。図書館のテーブルにあるような過ごし方について書いた紙を置いてもいいし、学校の先生が使うような、生徒一人一人の名前が書いたマグネットを使って、誰がいま何をしているのか分かるようにするのもいいです。
褒めたり叱ったりして、子どもに勉強してもらうのも悪いとは思いません。
でも、なかなかにエネルギーを使いますし、言われる側も次第に慣れてきて効果が薄くなってきます。
だったら、道具の配置や座る位置など環境を変えたり、あらためて皆さんが担当されている教室がどんな場所かを共有したりするほうが有効だと思います。
地域の皆さんが、こうやって子どもと関わってくれるというは、先生にとっても家庭にとっても本当にありがたいことです。今日お話ししたことが明日からの取り組みに生かしてもらえるなら幸いです。ご静聴ありがとうございました。
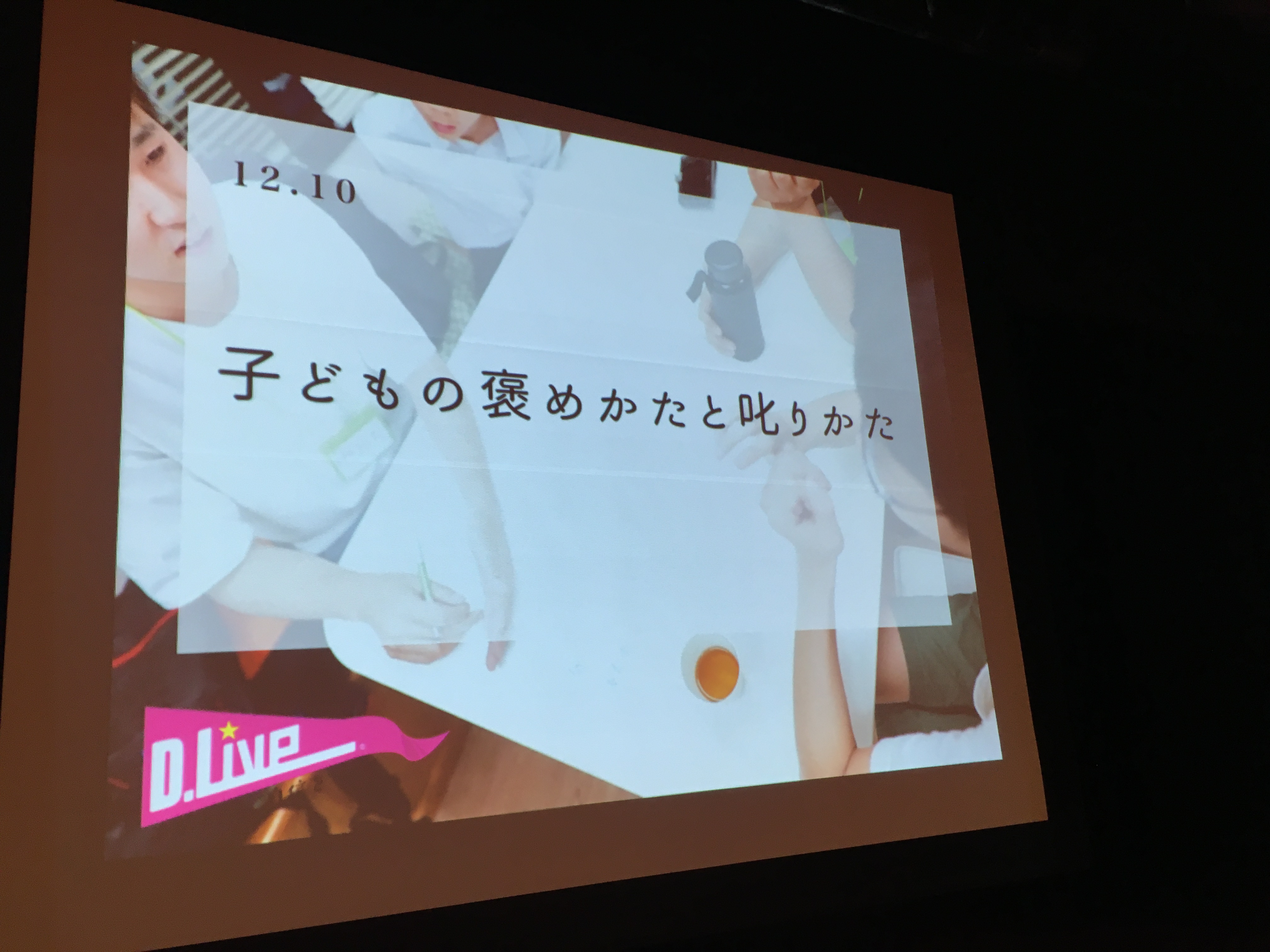





![[東京開催!]講座を受けたら、不登校の我が子との会話が増えた件について](http://www.blog.dlive.jp/wp-content/uploads/2018/05/kouen2-150x150.jpg)