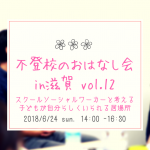2019年の4月に日本財団が「不登校傾向にある子どもの実態調査」を発表しました。
日本財団が、中学生6500人を対象にインターネットでおこなった調査で、学校に通っているけど教室には入らない子ども達や、教室で過ごしているけど心の中では通いたくないと思っている子ども達の割合が全体の10.2%いることが明らかになりました。
推計すると約33万人の中学生が、「教室にいるけど学校が辛いと感じている」「本当は授業に参加したくない」「登校はするけど、教室には入りたくない」といった思いを抱えている「不登校傾向」にあると日本財団はHPで発表しています。(日本財団の調査内容はこちらから)
不登校(年間30日以上欠席している状態)である中学生は全国で約10万人。今回の調査ではその3倍の約33万人の中学生が、不登校傾向にあると示されたことになります。
初めてこの調査結果を読んだとき、「まあ確かにそれくらいの人数はいるんだろうな。学校に行ってるけど本当は楽しくない子ども達には自分たちが運営する居場所に来て欲しいな」くらいに思っていました。
ですが、この調査結果をリアルに実感する出来事が、つい先日にありました。
私たちD.Liveは、日中や夜に子どもの居場所をいくつか運営しています。
そのうちの一つで、一学期のふり返りをおこないました。
ふり返りと言ってもカタいものじゃなくて、4月〜7月までの一学期間で不満に感じたことや失敗談をざっくばらんに話そうというものです。
『ふまんがあります(ヨシタケシンスケ著)』を導入で紹介し、
「みんなもこの絵本みたいに『どうして〜なの?』と思う不満が、一学期の間にあったと思います。今日はそんなことを一緒に吐き出しあいましょう。イメージは居酒屋。今日はお茶とか飲みながらでいいから、話そう。」
こう言って、大人も中高生も混じったグループを4つくらい作りました。
それぞれが思い思いに話せる時間を取ると、不満が出るわ出るわ。
「成績わるくて親とケンカしたー。」
「勉強が分からん。自分がアホっていうのもあるけど、数学の先生はみんながまだ問題解いてるのにすぐに答えゆうねん!」
「部活で合奏の練習中に指揮者を見てないやつがおって、そいつ先生から指揮棒投げられてた。」
「女子のグループうざい!なんか陰口ゆうてくるやん。こっち見たりヒソヒソしたりさ。あぁゆうのウザい。」
「宿題忘れてばっかりやって、ある日先生にめっちゃ狭い部屋に連れていかれて『アホ!』とかめっちゃ言われた。」
「友だちとかあんまり作りたいと思わん。だって騒がしいの好きじゃないねん。でもクラスはうるさいやつばっかやねん!どう思う?」
中には、「今の時代、それはもうパワハラなんじゃないか?」と思うような話も出てきて、子ども達の中には学校が安心して過ごせる場所じゃない子がいることを改めて実感しました。日本財団の調査にあるように、心の中では学校が辛かったり、通いたくないと思っている子ども達が約33万人いるだろうという結果にも納得です。
不登校の調査(年間30日以上欠席している状態の生徒の調査)は毎年行われていて、その数の推移も記録されています。ですが、今回のような毎年の調査には上がってこないような子ども達の声や実態をキャッチするには、友だちと行く居酒屋みたいに安心して話せる場所が大事です。
いろんなところでくり返し話していますけど、安心して本音を話せること自体が思春期の中高生にとってすごく価値のあることです。
不満を言い合った中高生の一人も言っていました。
「おれ、学校ではこんなんじゃないで。もっとおとなしいねん。」
私たちが運営する居場所ではいつも楽しそうで、大人に甘えたり、同い年の子と遊んでたりする姿を見ただけでは想像しにくいですが、彼がそう言うのだから、きっと本当に学校ではおとなしく過ごしているんだと思います。
私たち大人はついつい子ども達に何かを足そうとします。
成績が下がったら塾を進めてみるし、進路が決まってなかったらオープンキャンパスの予約もするし、部活で思ったような結果が出なかったら厳しく指導もします。
なかなか味の決まらない料理みたいに、塩を足したり、醤油を加えたり、みりんを回しかけたりしていまいます。
それらが悪いとは言いませんが、時には子どもが日頃感じている不満に耳を傾けたり、ただただ話を聞いたりする時間も必要です。
子どもたちの不満を聞くと、「そんなことがあったの!学校に連絡しなきゃ」とか「そんなことされてたのか!先生が今度そいつと話してみるわ」と、何かを加えたがる自分、欠けているものを補いたくなる自分がで顔を出します。
しかし、その場は子どもの話を聞くことに集中してほしいですし、子どもが何かして欲しいと思っているのなら話を聞き終わった後に自分でして欲しいことも言います。
子どもの話を聞いて、何か勧めたいことがあるなら、話を聞き終わった後に「なるほど、そんなことがあったんやな。何か自分にできることやして欲しいことある?」と聞いてください。
子どもにとってはただ話を聞いて欲しかっただけのときもあります。
気の知れた友人と行く居酒屋や、カフェでの女子会の会話にオチはつけないでしょう。そろそろ会計でもというときに、「じゃあ今回の話を受けてネクストアクションを決めて終わりましょう。」なんてことも言わないでしょう。そういうのは粋じゃない。
ご紹介した一学期のふり返り会でもオチはつけませんでした。アドバイスもしていません。ただただ、お互いに不満を言い合っただけです。それだけでも価値があるんです。
毎日子どもと顔をあわせる家庭や学校では、なかなか難しい部分もあるかも知れません。
そういうときは地域にある子どもの居場所(塾や習い事でも)を活用するのも一つの手です。
日本財団の調査で指摘されたような、隠れ不登校や不登校傾向にある約33万人の中学生とそのご家庭や学校のお役に立てていただければ幸いです。