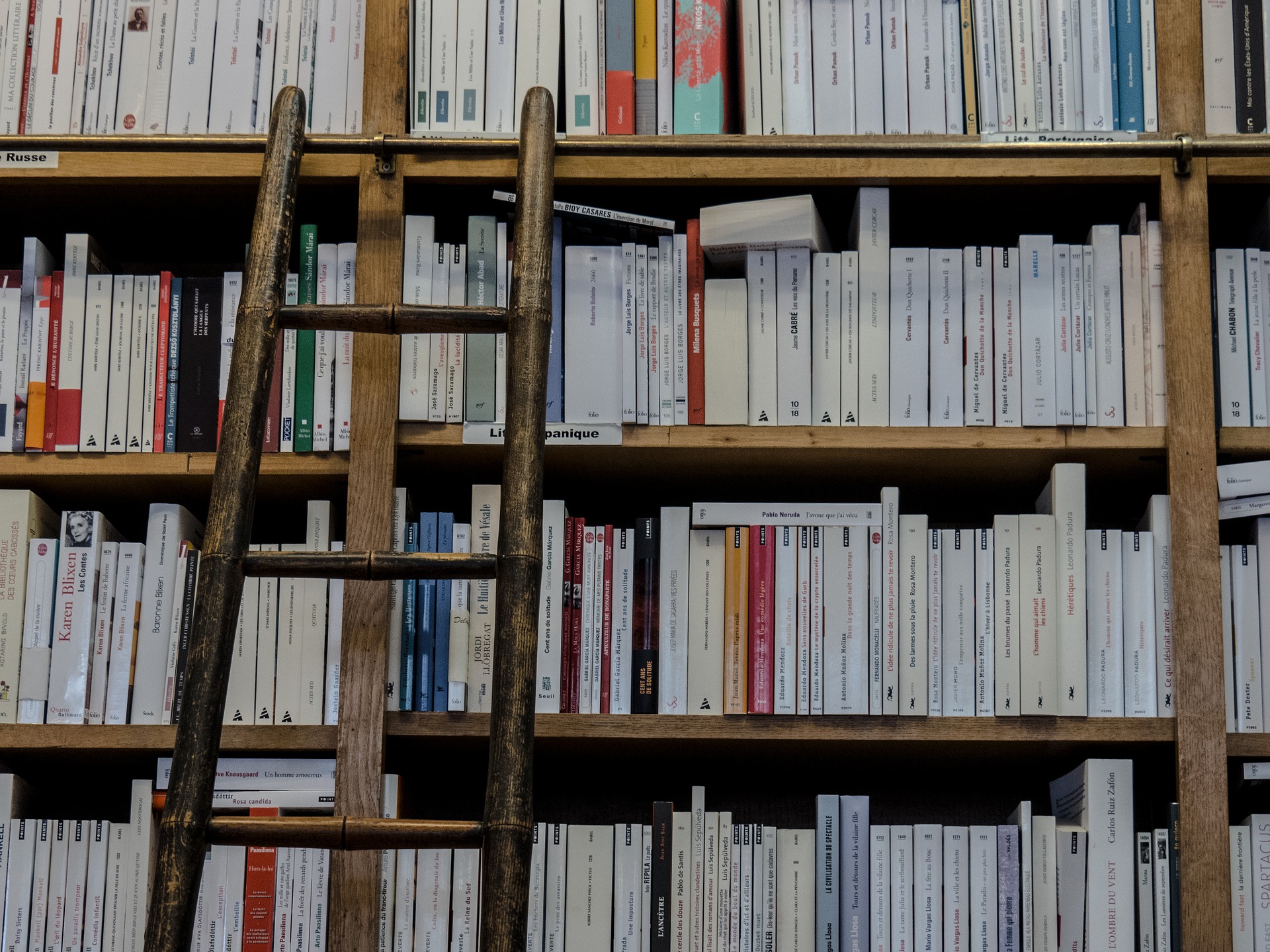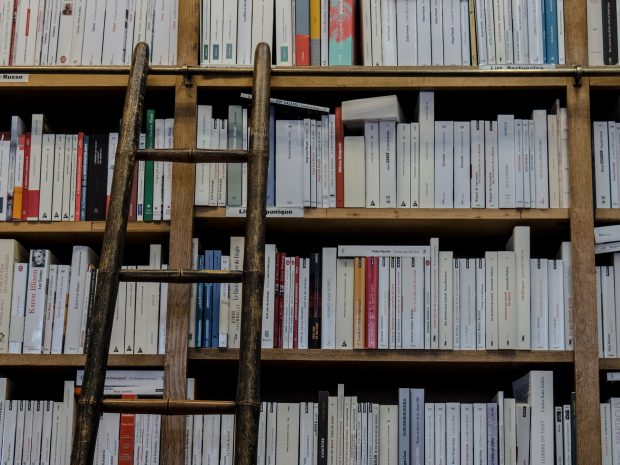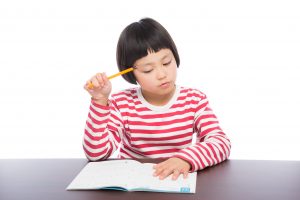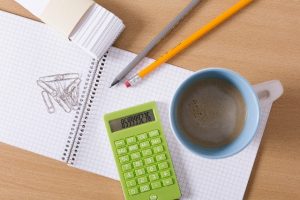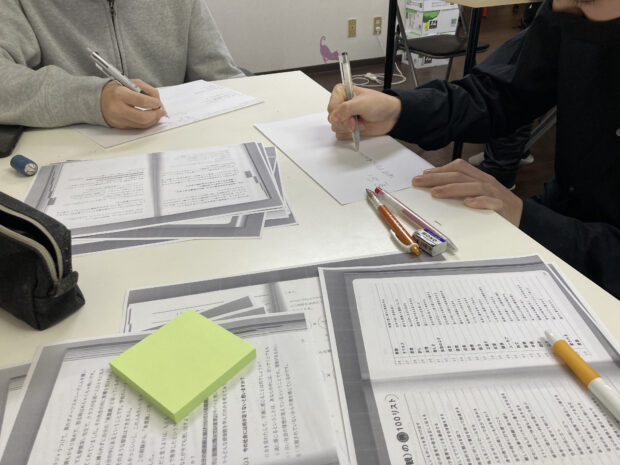最近、「知らない」ということは良くないなあ、と思うことがあります。
実は、弊団体が運営するフリースクール「昼TRY部」も、出発点は「知らない」ことでした。今だから言えますが、僕はそれ以前から夜の教室「TRY部」に不登校の生徒が多く通っている現状を鑑みて、フリースクール事業を何度か提案したことがあります。しかしそのたびに返ってきた結論は「NO」でした。
それは、団体として「滋賀県内にフリースクールなど不登校の子どもの居場所は数多くあるだろうから、わざわざうちがやる必要もない」という誤解を持っていたからです。余談ですが、後述する滋賀県内のフリースクールの少なさはフリースクール事業を言い出した僕も把握していなかったことでした。
やがて保護者の方から要望を受けて改めて調べたところ、滋賀県内には(市町村で運営する教育支援センターをのぞいて)不登校の子どもたちが昼間に過ごせる場所が片手で数えられるくらいしかない、という事実に気づき、方針転換してフリースクール事業を開くに至ったのです。
いまでは常時5人程度、多い日だと10人もの不登校の子どもたちが、この昼間の居場所で過ごしています。
このように、不登校について日々発信していたり、興味関心を持っている我々ですら、不登校のことをまだまだよく知らないのです。まだまだ知らない不登校の世界があるのです。
たとえば、Twitter。
正直、もう10年間使い続けているこのSNSに、こんなにも知らない「不登校の世界」が広がっているなんて想像すらしていませんでした。不登校の子をもつお母さんが、日々の子どもの様子や自分が感じていることをつぶさにツイートされているのです。
僕は保護者面談の席につくことはめったにないので、こうして不登校の子をもつお母さんが日々何を思い、どう子ども、そして学校と接しているのかを知ることができる貴重な手段になっています。もしかしたらこういう情報をお届けするといいのかもしれない、と記事の参考にすることもままあります。
その一方で、こんなツイートもよく見かけます。
「胡散臭いカウンセリングにだまされないように」
「不登校ビジネスはすごく怪しい」
残念ながら、これらは「事実」なのだろうと思います。
おそらく、これをツイートした保護者の方は、過去にとんでもないカウンセリングを受けたり、フリースクールでひどい目に遭ったり、まずい対応を受けた経験があるのでしょう。過去にあった出来事や事実を否定することはできません。
実際、代表の田中は、「詐欺などが多い」という東京近郊における不登校の支援の状況に閉口して、6月末まで「バースデードネーション」としてYouTubeにアップする動画を編集する機材の支援を募っています。これも田中自身、東京で見聞きした事実を「知らなかった」ことが発端になっています。
不登校の保護者が詐欺に遭うような社会を許していいのだろうか?
僕がこうして書いている文章も、これまでD.Liveで配信している不登校に関する動画の数々も、人から見れば「胡散臭い」「怪しい」と見られるのでしょう。僕はそれはそれでいいと思っています。
しかし、逆に言えば「カウンセリングが胡散臭い」「不登校ビジネスは怪しい」といったツイートは、胡散臭いと言われながらも、怪しいという目で見られながらも、なお真摯に保護者の方をなんとか救いたいという気持ちで活動している不登校支援団体や個人を「知らない」という見方もできます。
そして、「真摯に活動している不登校団体を知らない」からこそ、カウンセリングやフリースクールを運営している不登校団体すべてを否定して、真面目に不登校に向き合う人たちの心を折ってしまうことだけは、絶対に避けなくてはいけないのではないでしょうか。
確かに、悪質な不登校支援団体はいると思います。きっとそうした団体の中には、悪い言い方をすれば「食い物にしている」ような感覚があるのでしょう。極端なことを言えば、何をやっても不登校支援って胡散臭いものなのかもしれません。しかし不登校支援団体はみんながみんな悪質なわけではありません。
自分が見たこと、聞いたこと、そして知っていることだけが全部、ではないのです。
その胡散臭いカウンセリングでも「本当に救われました!」と感激する保護者の方もいます。怪しいフリースクールでもその場所を心から楽しんでいる子どももいます。訝しむのは自由ですが、不登校支援にはこんな世界もあることだけは、忘れてはいけないと思います。
そういう意味で、不登校のことをもっともっと「知る」必要があると思います。
それは、この文章を書いている僕自身もいっしょ。
このブログ上で何度も自分の体験談、そして不登校に対する思いや考えを発信していますが、だからといって僕は不登校に対するすべてを知っているとはひとつも思っていません。前述したようにTwitterなどからまだまだ不登校について学んでいる身です。
ここのところ不登校についてよくテレビ番組で取り上げられています。そのたびに不登校の有識者がコメンテーターとして招かれ解説しているのをよく目にしますが、きっとそんな人でさえまだまだ不登校について「知らない」ことがいっぱいあると思います。
ひと月ほど前より始まった、日本財団によるTwitterキャンペーン「#ミライの学び」で、僕はあえてこんな視点でハッシュタグを使ってみました。
Shun on X (formerly Twitter): “先々週から日本財団が展開しているハッシュタグ #ミライの学び 、ここ何日かいろいろと考えていたのだけど、今すぐに環境を激変させることは難しいかもしれないが考え方を変えることでミライの学びに繋げることはできると思う。具体的に言えば、自分が見た、経験したことが全てだと思わないでほしい。 / X”
先々週から日本財団が展開しているハッシュタグ #ミライの学び 、ここ何日かいろいろと考えていたのだけど、今すぐに環境を激変させることは難しいかもしれないが考え方を変えることでミライの学びに繋げることはできると思う。具体的に言えば、自分が見た、経験したことが全てだと思わないでほしい。
Shun on X (formerly Twitter): “世の中には、どんなに忙しくとも、不登校の子どもたちに真摯に向き合う先生もいる。自分の身の回りの経験だけで「世の中の先生全員が不登校の子どもに冷たい」と決めつけたとき、不登校に真摯に向き合っている先生方はどんな思いをするだろうか。 #ミライの学び / X”
世の中には、どんなに忙しくとも、不登校の子どもたちに真摯に向き合う先生もいる。自分の身の回りの経験だけで「世の中の先生全員が不登校の子どもに冷たい」と決めつけたとき、不登校に真摯に向き合っている先生方はどんな思いをするだろうか。 #ミライの学び
「こんな学校なら通えた」「こういう授業をしてほしい」など、学校環境に関する声が上がる中、あえて「知ることの重要さ」を取り上げたのは、言葉の裏を読めば「知らない」という4文字が浮かび上がってくる、そんな批判や要望ツイートが多かったことがひとつの大きな要因でした。
もちろん、先述したように僕もまだまだ知らないことばかりです。お前が言うな、と言われるかもしれません。でも、「実情はそうじゃないんだけどな」、とひどくがっかりしたツイートが多いのも事実なのです。そしてそれに対する同意のいいね!が多いことも、また複雑な気持ちにさせてしまうのです。
たとえば「いじめられた経験のある教師なんていないから、いじめられる側の気持ちなんてわかんないよね」というツイートがありました。しかし僕はその「いない」と断言されたいじめられた経験のある教師です。たぶんもっとひどいいじめを受けてもなお教壇に立つ人もいるはずです。
つまり、これをツイートした人は、いじめの経験を受けた教師がいることを「知らない」のです。にもかかわらず、「いじめられた教師なんていない」というその人の主観でしかない情報がもとになって議論が進んでいくことが、本当に残念で仕方ありません。
正しい情報を知ることで、間違った議論を回避できるかもしれない。怪しい不登校支援団体を撃退できるかもしれない。田中の言う「不登校の保護者が詐欺に遭うような社会」が解決するかもしれない。
だからこそ、僕はこれからもいろんな教育を、いろんな不登校の現状を知りたいのです。
そして、たとえ「胡散臭い」「怪しい」という声が多くとも、本当に必要な不登校支援を届けていきたいと思っています。そのためには、現状を「知ること」を、ひとりでも多くの不登校に関わる人間が意識してほしい、と心の底から強く願っています。
◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。