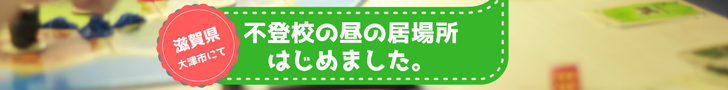誰に話しても、「それは考えすぎだよ」と言われる出来事がゴールデンウィークの初日にありました。
角が立つのはイヤなので少しぼかした言い方になりますが聞いてください。
ゴールデンウィークの初日。
仕事に関するとある勉強会が開かれる予定でした。自分も関心があり、参加しようと思っていたのですが、当日が近づくにつれてだんだんと行きたくなくなってきました。
理由は3つあります。
1つはその勉強会が、参加者同士の交流がメインだったこと。ぼくは人見知りの気質があります。
ぼくは中高生向けの教室を運営しているので、多くの子どもたちや親御さんたちと関わります。人と話すことに抵抗があるわけではないんですが、初対面の人がたくさんいる場で交流をするのは苦手です。
知り合いの少ない結婚式や二次会に出席したら絶対すみっこの方にいて黙々とご飯を食べているタイプだし、初対面の人が5、6人のグループになってワークショップをする勉強会では同じテーブルの人たちが考えている事が気になってしまい、何をしゃべれずに黙っていることも多いです。
ゴールデンウィークの初日の勉強会では知り合いが一人か二人くらいしかいなさそうだったので、「あぁ、他の人たちと話さないといけないのか」と憂鬱な気持ちでした。
理由の2つ目は、1つ目と同じく参加者とのコミュニケーションに関することです。交流するときに、良いことを言わないといけないと思っていました。交流メインの勉強会といってもどんな話をしてもいいわけではなくて、そこで交わされるトピックは自ずと今回の勉強会に関する話題になります。
見栄を張るというわけではないのですが、D.Liveについて紹介したときに、「しょーもない団体だなぁ」なんて思われたくはないんです。初対面の人が多い場所で、今回の勉強会のテーマについて話すことが自分の団体の中にどれだけあるだろうかと考えたときに、全然ないことに気づいたんです。
聞き役に徹するという逃げ道もあるんですが、1つ目の人見知りも重なって、余計に行きたくない気持ちが高まってきました。
最後の理由は、会いたいような会いたくないような人がこの勉強会に参加されるかもしれないこと。個人が特定されてしまうのは避けたいので、さらに曖昧な書き方になるのですが、お目にかかったことは無いけれどお名前は聞いたことがある方に、会いたいような会いたく無いような複雑な気持ちがありました。
前日まで。
いや、なんなら当日まで行こうかどうしようか悩みました。奥さんにも当日の2、3日前から「どうしよう、どうしよう」と答えを出す気もない相談のようなグチのような話を聞いてもらいました。
一番ひどいときは、
「どうして自分はこんなに行きたくない気持ちがあるんだろう?その原体験は何だ?」
「今回の勉強会はその原体験と何が違うのか?」
「行ったらどんな良いことと、しんどいことがあるんだ?」
などなど自問自答のループにはまっていました。
当日まで悩んだくらいですから、頭のエネルギーを使い果たしてしまって、結局ぼくは勉強会には行きませんでした。そんなにイヤだったのかと言われれば、イヤではありません。実りの多い勉強会だっただろうことも十分に理解しています。だって元々は参加するつもりだったんですから。
でも、足が向かなかった。
良いとか悪いとかでもないし、好きとか嫌いとかでもないし、イヤだとかイヤじゃないとかも違う。
ただただ足が向かなかった。
皆さんもそうだと思いますが、ゴールデンウィークがすぎて、いろんな人と連休の過ごし方について話しました。
ぼくがこの話をしたらだいたい笑われるんですよ。
「考え過ぎやって(笑)」って。
深刻な面持ちで聞かれるとぼくも困るんで、笑ってもらって全然構わないし、たしかに考え過ぎです。
ただ、この出来事を通して、「もしかして学校に行きたくても行けない子も同じように、悩んだり考えたりして疲れているんじゃないか」と思ったんです。
友だちからの目線が気になる。
勉強の課題が多過ぎてしんどい。
歌のテストがどうしても行けない。
あの人に会ったらどうしようって思う。
学校に行けない子どもたちと話す中で、いろいろな理由を彼らから教えてもらいました。その理由を思い返して、言葉にできない奥の気持ちを想像してみたんです。
例えば友だちからの見られ方が気になると言った子の奥には、
「『なんで休んでたん?』と聞かれたらどう答えよう。変な人に思われたらどうしよう。担任が『よう来たな』と言ってきたらいやだな。特別扱いはされたくないな。授業で当てられて答えられなかったらどうしよう。」
なんて気持ちが隠れているかも知れない。
言葉にできないたくさんの「どうしよう」があるかも知れない。
「どうしよう」で頭が埋まって心がまいっているかも知れない。
そう考えると、「嫌いじゃないやったら行ったらええやん。学校なんて行くだけやん」なんてやっぱり言えない。
心理カウンセラーの高垣忠一郎先生が、講演の中で「悩みの相似形」という話をされたことがあります。
自分が不登校を経験していないのに不登校の子どもの気持ちに共感するにはどうしたらいいかという質問が会場から出たときに話されていた言葉です。
「同じ経験をすることはできないけど、似た経験から気持ちを想像して共感することができる。悩みの相似形で関わるんだよ。」
ゴールデンウィークの初日。
ぼくは勉強会で学ぶことはできなかったけれど、これから出会う子どもたちと分かち合える経験ができた気がする。もし分かち合えるなら、この経験を補助線にして子どもが自分のホンネに向き合う手伝いができればと思う。