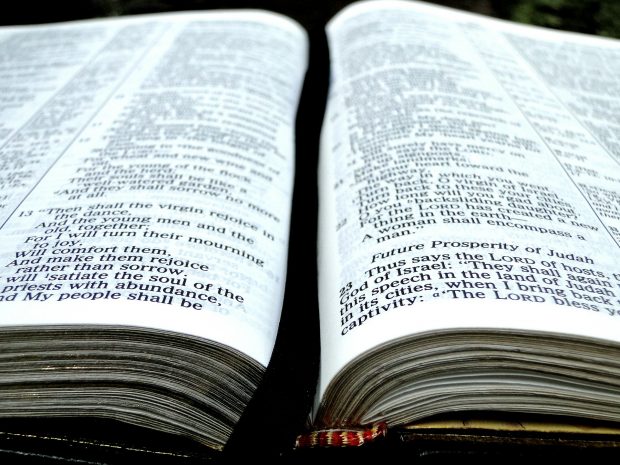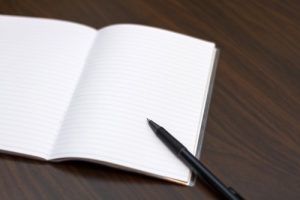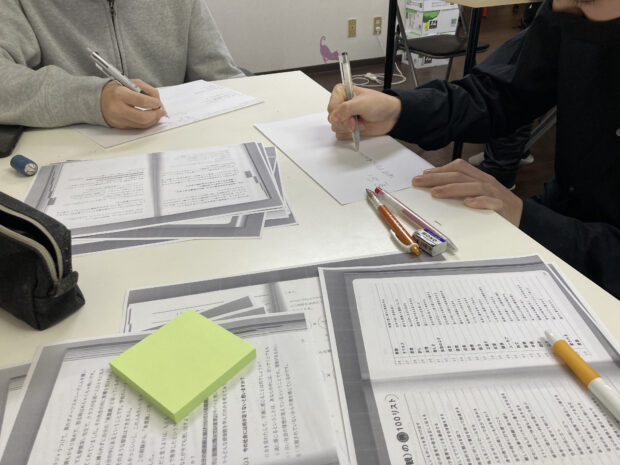この間の日曜日、大阪城近くのドーンセンターで行われた「君の居場所はきっとある」(主催:NPO法人フリースクール全国ネットワーク、協力:ふりー!すくーりんぐ)というイベントに参加してきました。
このイベント内で3つのシンポジウムが行われ、2部では大阪のフリースクールに通う生徒の座談会が展開されました。その名もズバリ「勘違いしている大人たちへ」。なかなかドキッとさせられるタイトルですが、これは実際にハッとさせられた保護者の方もおられるだろうなあ、と感じた40分でした。
というのは、表面上は会場から笑いが出るほどとてもひょうきんに話している生徒たちの話の中身が、まったく他人事ではない、もう少し言えば中学3年間不登校だった自分自身もしょっちゅう経験していたことばかりだったからです。
どうして、不登校の子どもたちは質問攻めにあってしまうのでしょうか。
いや、たぶん答えは明白なのだと思います。
「なんで学校に行きたくないの?」
「わからない」
「なにがしんどいの?」
「わからない」
「これからどうしたいの?」
「わからない」
こんなやり取りが続いたら、きっと親は大爆発してしまうでしょう。
「『わからない』ばかりじゃ、なにもわからないよ!」と。
でも、これは残念ながら、事実なのです。
不登校の子どもたちは、本当に自分の気持ちが「わからない」のです。何がやりたいのか「わからない」のです。この先、学校に行かずにどうやって生きていくかも「わからない」のです。そう、諸々出た質問に対して、子どもたちはきちんと答えているのです。「わからない」と。
決して、質問から逃げているわけではありません。これからの将来や学校からも逃げているわけではありません。ただひとつ、子どものほうから明確な「わからない」という答えが出ているにもかかわらず、そのメッセージに親の側、大人の側が気がつくことができないだけなのです。
僕はこの「わからない」という5文字には、いろんなパターンがあると思っています。
たとえば、いろんな感情が混じり合って「わからない」というパターン。
担任の先生が苦手だ、クラスの雰囲気がしんどい、隣の席の男子が鬱陶しい・・・などなど、不登校の発端にはいろんなものがあります。十人十色と言っていいでしょう。「あれも嫌だ」「これも嫌だ」という感情がぐるんぐるん混ざって、最終的に「わからない」という言葉で片付けてしまう。
同様に、いまの自分の感情を的確に言い表してくれている言葉が「わからない」というパターンもあります。このとき、なにも考えていないから「わからない」というわけではないのです。黙っているのは、ひたすらに自分の持つボキャブラリーの中から、いまの気持ちを表現できる言葉を探しているだけなのです。
にもかかわらず、「黙っていてもわからない」とそれを一蹴されたり、あまりに言葉を待っているのでとりあえず「わからない」と言えば、大人はその「わからない」という答えを受け付けてくれない。これは大人側の配慮があまりにも足りていないと言わざるを得ません。
では、「わからない」と言われたとき、どうすればいいのか。
まず、何度も書きますがこちら側の問いに対する答えはすでにもう「わからない」という形で出ているわけです。ということは、逆に言えば同じような質問でそれ以上掘り下げたとしても、「わからない」しかでてこないわけです。つまりそれ以上同じ質問をぶつけてもなんの意味もなさないわけです。
「わからない」と言うのなら、まずはそれが現時点での回答だと認識して、それを受け容れることです。
その上で、「わからない」ことを掘り下げる必要があるでしょう。
簡単な選択肢を作って「どっちの気持ちに近いか」聞くと答えてくれるかもしれません。先述した言葉が「わからない」場合は、いっしょに最適な言葉を探すことも有効でしょう。「わからない」ことをいっしょに紐解いていく作業をしていくと、お互い気付いていなかった本当の気持ちがわかるかもしれません。
ただし、無理に「わからない」ことを掘り下げてはいけません。あまり強く聞きすぎると結局「わからない」に戻ったり、「わからない」の言葉すら発さず黙ってしまうでしょう。聞いてくるのが面倒くさい、という思いに変わります。
冒頭のシンポジウムでは、この次々繰り出されて「わからない」と答えざるを得ない質問が本当に苦痛だった、という話題になりました。僕もそうでした。黙っていたら早く答えを言うように催促されるのは本当に苦痛でした。自分のペースを乱されているような感じがしました。
どうして、親というものはこう自分の都合で答えを受け付けようとするのか。
そんなことすら思ったこともありました。
「わからない」という言葉を受け入れてくれなかったときは大いに失望しました。こちらとしてはきちんとした回答を導き出した、しかも悩みに悩んだ末に結論を出したのに、それじゃだめだと違う答えを要求してくる。子どもの側からすれば、こんな理不尽なことはありません。
子どもが「わからない」と言うのなら、その時点での回答はもう、それなのです。
もしかしたら時間を置けば「わからない」以外の言葉を引き出してくれるかもしれません。でもそれに納得せずにどんどん聞こうとすると、しまいには言葉すら発しなくなるでしょう。こうなれば、本当に子どもが欲しているものや人、支援がいよいよわからなくなり、事態が泥沼化してしまうことも考えられます。
「わからない」という言葉を受け入れる勇気を、持ってください。

◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。