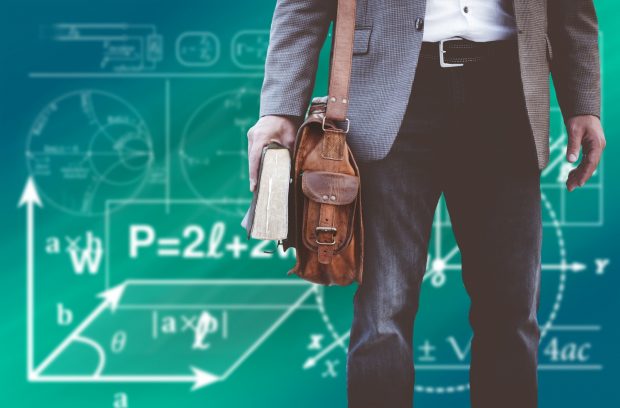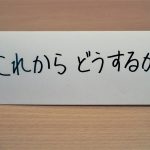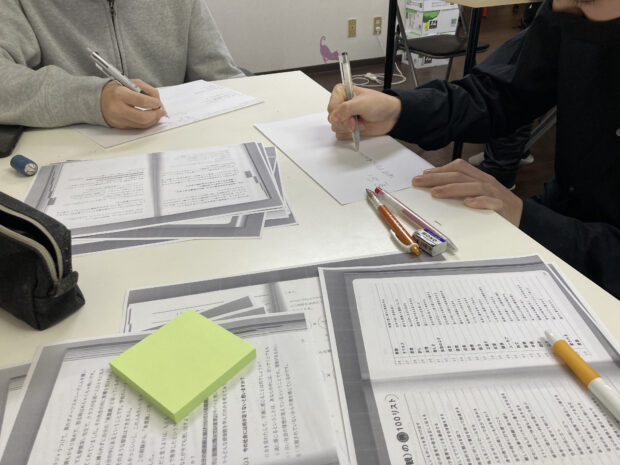我が子が不登校になったとき、「どうして?」「なんで?」と思うことはたくさんあると思います。
この子は何を思っているの?なんで学校に行けなくなったの?どうすればいいの??
そんなときに、おのずと「我が子が不登校になった責任」を、学校の側に求めたことはないでしょうか。たしかに、日々不登校支援に携わっていると、「学校に対する愚痴」というものを聞かないことは、まずありません。
もちろん、こういった経験は僕にもあります。不登校になった当初、両親はよく夜の学校へでかけていました。そこでどういう押し問答があったのかは今も知りません。ただ、学校の対応によって僕が傷ついたり、なにかショックを受けたときは、親はほぼ必ず学校に文句というか、苦情を伝えていました。
当然、家庭の側がそうした不快な思いをしたというのは紛れもない事実です。それに対して何かを言う必要があるのは当たり前だと思います。しかしながら、学校もまた苦慮しているということを、不登校の子を持つ家庭の側は知っておくべきなのではないか、と同時に思うのです。
先日、こんなニュースを読みました。
増加する小中学生の不登校 「死にたい」とまで思う教師たちの現状
http://news.livedoor.com/article/detail/15669249/
不登校の児童生徒数が増加している、ということを、僕は割と好意的に捉えているところがありますが、もちろんみんながみんな好意的に捉えているわけではありません。中にはこのニュースに出てくる先生のように、不登校の子どもがいることで思い詰めるところまでいく先生もいらっしゃいます。
不登校の生徒の保護者との関係にも、さらに心をそがれました。
離れて暮らす生徒の親に代わって、朝が苦手な生徒のために、自転車で下宿先を毎朝訪問。それでも起こせず生徒の母親に電話すると、「あなたの技量が足りない」と叱責されました。
「もっと先生から言ってやってください」。でも、女性はできる限りのことはしているつもりです。親の思うように事が進まず、しまいには「子どものいないあなたに何がわかるの」と言われ、泣いて過ごす日々を送りました。
引用:増加する小中学生の不登校 「死にたい」とまで思う教師たちの現状 – ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/15669249/
普段、学校側のまずい不登校対応に眉をひそめることも多い僕でも、さすがにここまで来ると先生側の立場に共感してしまいます(もっともこのケースは母親側が子どもに無関心なところもあるんじゃないかと思いますが)。
僕自身、教員になっていろいろと気付かされることがあるのですが、久しぶりに生徒の顔を見ると「おおー!」と、ちょっと嬉しくなるものなのです。僕の勤務先はとりわけ不登校を経験した生徒が多いのもあるかもしれませんが、「久しぶりやん!」と先生の声が弾むことは、1日に何度もあります。
もしかしたら、先生の側からすれば、「不登校の子どもの顔が見れない」ということは、ものすごく寂しいことなのではないか。
そんなことすら思う瞬間もあります。
一番しんどいのはほかならぬ不登校の子ども自身です。それを側で見ている家族や保護者もしんどいでしょう。でも、待つ側である先生自身や学校側もしんどい思いをしているということは、不登校の家庭では意外に頭がまわらないのかもしれません。
以前も書きましたが、ただただその子が学校という場に合わなかった、集団行動が苦手だった、こうしたところから不登校になるケースでは、そもそも誰かに責任を押し付けること自体が間違っています。それはもう、誰のせいでもない。学校が適切な教育をしなかったなどと言っても話は進みません。
そういったところも、先に紹介したニュースに取り上げている、不登校生徒の担任経験がある教員全員が「不登校の生徒対応で困ったことがある」と回答しているところにつながっていると思います。
また、たとえば先生のちょっとした一言や、学校側の不手際で不登校になったとしても、大事なのは少なくとも怒りに任せて学校を責め続けることではないはずです。その腹立たしい気持ちはわかりますが、それではこの問題を解決することなんてできるわけがありません。
不登校支援には冷静さが必要不可欠です。時に冷静さを欠いた親の行動が不登校の我が子を傷つけます。
先述したように僕も不登校だった中学生のとき、何度も学校に傷つけられてそのたびに親が学校に怒っていましたが、学校への腹立たしさと同時に必要以上に怒る親の姿に学校への申し訳なさも感じていました。僕は中学3年間同じ担任の先生にお世話になりましたが、きっと先生も深く深く悩んでいたと思います。
やや話はそれますが、僕はもう不登校支援や対応を学校「だけで」カバーするのは限界に近いんじゃないかと思っています。
それは昨今叫ばれる教員の長時間労働問題とも深く関わっています。先日も平日の深夜23時に近所の中学校の校門から車が2台出ていって、非常に驚きました。ただでさえこんな状況なのに、さらに不登校の生徒がいるとなるともはや勤務時間内に気にかける余裕など微塵もないことは容易に想像できます。
共働き家庭が多いため、昼間の時間帯は保護者には連絡がとりづらく、家庭訪問をするとなると土日に行う場合もあるといいます。内田准教授は「必然的に勤務時間外で対応せざるをえなくなっている」といい、その残業代は、教員に適用されている法律(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)によって支払われることはありません。
引用:「教室にいる生徒でさえ…」不登校対応に影を落とす教師の長時間労働 – withnews(ウィズニュース)
https://withnews.jp/article/f0181130003qq000000000000000W06910801qq000018426A
こういう状況を見ていると、なかなか不登校の生徒対応に手をかける余裕もないのがよくわかります。学校側の対応が甘い、担任の先生が不登校のうちの子をおざなりにしている・・・と感じるのは、それくらい担任の先生が目まぐるしい日々を過ごしているから、という理由も考えられそうです。
だからこそ、不登校支援に関わる外部団体やスクールソーシャルワーカー、臨床心理士と言った人々がいま、とても大切な存在なのだと感じます。弊団体で開催している「不登校のおはなし会」など、不登校関連の各講座が満席になるのも、こういう場を求めている人々が多いことを意味している気がします。
家庭側も学校側も、お互い「だけで」目の前の不登校問題を解決しようとするのではなく、どんどん外部を頼って支援していくことが大事なのではないでしょうか。それが教員の長時間労働問題や、不登校の責任を押し付けられている先生方を救うひとつの足がかりになると思います。
◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。