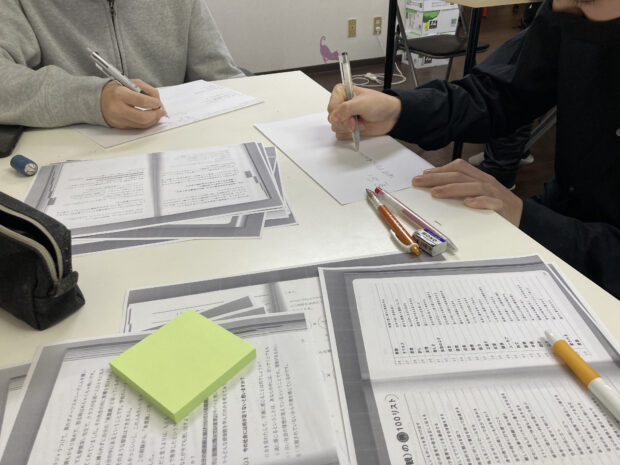この20年、不登校の子どもの在宅環境は間違いなく大きく変わっています。
いまや現実世界に居場所を求めず、インターネットで日本、いや世界各地の人々と関係を築く子もいます。家に居ながらにして他人と、しかも顔を合わせず文字だけで簡単にやり取りできる環境は、まず一昔前にはなかった世界です。
もはや夕方とも呼べる時間にのこのこと起きだし、食事と風呂、トイレに立つ以外はインターネットやテレビゲームなどにのめり込む子も多いと聞きます。
画面と対峙し続ける子どもの姿を見て、ネットやゲームばっかりやっていてこの子は大丈夫なのだろうか、と眉をひそめる親。実際にこういった相談はよく受けるのですが、果たして本当にネットやゲームにのめり込むことはいけないことなのでしょうか。
僕が不登校だった時期はもう10年以上前になりますが、僕もまたインターネットにのめり込む生活でした。当時はSNSなんてまだ普及していない時期だったので、よくチャットで画面の向こうの人たちと会話していました。何回かその画面の向こうの人たちと会ったこともあります。
この間はその「画面の向こうの人たち」に平気で会いにいく我が子が心配、という話も耳にしました。僕の場合、幸い悪いことに巻き込まれることはありませんでしたが、自分の親、また「画面の向こうの人たち」の親もそんなふうに心配していたのかもしれない、と思うと少し反省すべき点もあります。
しかしこの「インターネットにのめり込む生活」が当時はなによりの救いでしたし、10年経た今でも役立っている面があります。今こうして毎週コラムを続けているのも、「ブログ」というサービスがまだ黎明期だった10年以上前から毎日くだらない私生活を書き溜めていたことが礎になっています。
正直な話、不登校生活であんなにインターネットにのめり込んでいなければ、今自分がどこで何をしているのか、はたまたそもそも生きているのか、まったく想像できません。
ネット依存、ゲーム依存に陥る子どもを見守る心境というのは、「ネットやゲームに1日を費やす生活を続けていたら、将来はどうなってしまうのだろう」という不安感もあることと思います。
しかし、こんな考えはできないでしょうか。
いちいち解説するのもおかしな話だが、「サッカーに没頭する」という体験がもたらす可能性は、「プロのサッカー選手になる」ことだけじゃない。
もしかしたら彼は、途中でサッカーグッズの開発に興味をもつかもしれない。
サッカー漫画にハマって漫画家を目指し始めるかもしれない。
サッカー部でできた友達と、何か関係ない仕事を始めるかもしれない。
10年後にはサッカーにまつわるまったく新しいビッグビジネスが生まれており、彼のスキルがたまたまそれに生きるかもしれない。
こんな想像は、いくらしてもきりがない。まさに無限大だ。引用:堀江貴文(2017)『すべての教育は「洗脳」である 21世紀の脱・学校論』(光文社)P122
ホリエモンこと堀江貴文さんは、「没頭」こそが学びであるという持論を様々な著書で展開しています。
上記の引用はサッカーを例に挙げていますが、僕は「ネット」でも「ゲーム」でも通用すると思います。
ゲームに関わる職業を志すのはもちろん、「桃太郎電鉄」で地理に興味が湧いたり、「パワプロ」で野球に関する仕事をやってみたいと思うかもしれない。「みんなのゴルフ」で実際にゴルフクラブを握る可能性も、それこそ今で言うなら「ユーチューバー」に憧れる可能性も、ゼロではありません。
車のゲームで自動車に興味を持ち、いつかベンツに乗るために一念発起してなにかしらの職業に就く、なんてこともあるでしょう。とくに多岐なジャンルが揃っているゲームという世界では、そこから飛び火して何か違うものに興味が湧くことも有り得る話です。
堀江さん自身も、中学のときに買ってもらったコンピュータに文字通り「没頭」した結果成績が急降下し、親にコンピュータをゴミ捨て場に置かれて慌てて取り返した、というエピソードもあります。しかしそこで得た知識やスキルが後の「オン・ザ・エッヂ」(ライブドアの前身の会社)設立につながっています。
「没頭」するには自らにきちんとルールを課すことが必要であることも、堀江さんは同時に説いています。ゲームなら1日○時間とか、様々なルールが設定できるでしょう。しかし「何かにハマる」経験は、特に生きる希望を見いだせない不登校の子どもたちにとっては、何よりも貴重なものです。
こうして考えると、ネットやゲームにのめり込むのも要は「使い方次第」なのだと思います。
たとえばYouTubeはおもしろ動画やバラエティだけのものではありません。歴史を事細かく解説したり、英語の授業をそっくりそのまま動画としてアップしているチャンネルもあるわけです。「YouTubeは悪」と眉をひそめるのは、こういうためになる授業動画さえも否定していることになります。
また、ちょっと刺激的な動画やゲームをやっていることに頭を悩ます方もおられると思います。うちは父がガンシューティングゲーム好きの人間で、ひとりゲームセンターに通ったり生前よく「コール・オブ・デューティ」というゲームを家でずっとやるほどだったのですが、実生活ではまったく穏やかな人でした。
ネットやゲームの世界に溺れない使い方やルールを示しながら、何かに「没頭」する姿を暖かく見守ることが、ネットやゲームにのめり込む不登校の子どもを尊重することになるのかもしれません。
ちなみに、不登校だった10年前、僕はネットに没頭すると同時に「テレビっ子」でもありました。食事の時間でもテレビがついてる家庭で育った人間なので、毎日深夜2時3時までたっぷりとテレビを観ていました。自分の部屋にテレビがないことを何より不便に思っていました。
しかし今、自分の部屋の机にテレビを置くようになりましたが、1日中電源をつけない日なんてごまんとあります。まったくテレビを観ないわけではないですが、あのころに比べてテレビの視聴時間は半分以下になりました。
あれだけ熱中していたものでも、ブームが去るときは意外と「あっさり」なのです。
◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。