スタッフの得津です。
いま、八月に控えた高垣先生の講演会のために先生の著書を読んでいるのですが、
大変興味深い話がありましたのでご紹介します。
読んだのは『生きることと自己肯定感』です。
高垣先生があるお父さんのカウンセリングをしていた時の話です。
以下、引用です。
高校の娘が不登校になった、あるお父さんのカウンセリングをした。カウンセラーから「さぼっているわけではない。どうしても行けないのだから、まずは受け容れてあげましょう。」と言われる。お父さんは言う。「朝からテレビを観て、ダラダラと過ごしている娘を受け容れたら、私のいいところがなくなってしまいそうな気がします。」お父さんは大企業の部長さんである。同期の出世頭でもある。がんばって、がんばって、競争に勝ち抜いて今の自分がある。それが自分の「誇り」であり、生き方を支えて来た価値である。
「ああそれなのに、それなのに」である。娘はレースから脱落して、だらりだらりとすごしている。何も頑張っていないように見える娘を受け容れたら、この俺様の価値を否定してしまうことになる。だから、自分のいいところをなくしてしまうような気がしても当たり前だと思う。それは本当によくわかる。
それに、お父さんはこうもおっしゃる。「娘を受け容れようとしたら心を緩めないといけない。そんなことをしたら、明日から会社に行って、がんばれなくなってしまうのではないですか……。」
お父さんと同じではないですが、自分自身も先生時代に不登校の子どもと関わる時に、ある葛藤を抱えていました。
私は学生のときから、関西にあるいくつかのオルタナティブスクールやフリースクールを知っていました。その意義についても、不登校の子どもにとっての居場所になれることも知っていました。だから、(別に学校に行く事にこだわらなくても……)と思うことだってありました。
でも、とはいえ先生という立場があり、(やっぱり学校にくるようにしなければ)という気持ちもあったので、自分の中でどう気持ちに折り合いを付けていくのかすごく悩みました。
高垣先生は、不登校の子どもとまともに向き合うことは、まさに自分の生き様や価値、それを支えてきた価値観と真っ向から向き合って格闘しないといけないほどの大変な事であると述べています。
本当におっしゃる通りだと思います。今までの自分の価値観では太刀打ちできない事がたくさんあります。
もしかしたら、このブログを読んでくださっている方の中にも、先生や保護者の立場などそれぞれの立場から不登校の子どもと向き合い、自分の価値観と向き合っている方もおられると思います。だからこそ、どうしたら良いんだろうと悩む事も多いのではないでしょうか。
8月4日(木)は、30年以上不登校の子どもに関わって来た高垣先生と一緒に、子どもと、そして自分とどのように向き合っていくのかを見つめる機会にしませんか。 ※このイベントは終了しました
8月4日(木)14時〜16時半
「思春期の子どもをまるごと認める関わり方 高垣忠一郎先生講演会」
場所:紫明会館 (京都市営地下鉄鞍馬口駅 徒歩7分)
定員:50名
参加費:3,000円
お申し込みは下のリンクからお願いします。
http://kokucheese.com/event/index/403035/



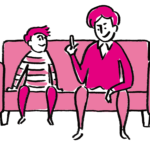








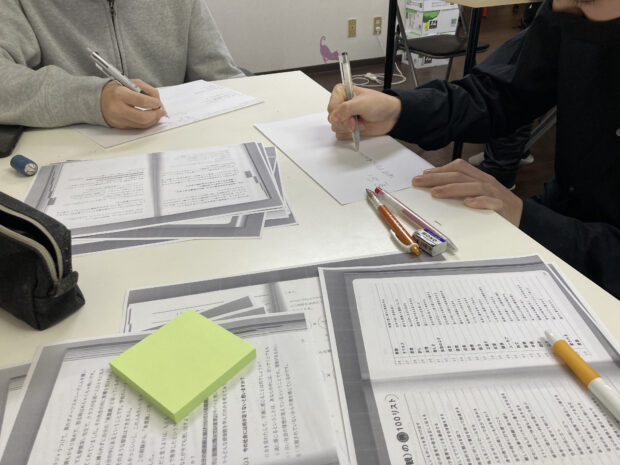






コメント