今、写真を使う機会って多いですよね。
団体の活動はもちろんのこと、SNSでどこかへ行ったことなどをレポートすることもあります。
今回は、誰でも簡単に使える活動写真のポイントについて書いていきます。
1. 撮りたいものを決める
写真を撮るとき、意図をもっていますか?
「この様子を伝えたい!」というのを決めて写真を撮ると、今までよりもずっと写真の撮り方が変わります。
デジタルになって何枚でも撮れるから、なんとなくで撮ってしまうことも多いハズ。
でも、それではなかなか伝わりずらい。
「楽しんでいる様子を撮りたい」「この笑顔が欲しい!」
そうやって決めて撮ると、写真のクオリティが格段にあがります。
僕は、「この表情が撮りたいな」と思って、数分間カメラで狙いを定めていることがよくあります。
2. 視線の先を空ける
顔が横を向いている写真では、視線の先になにかありそうと思ってもらうために空けるのがコツです。
3. 全体を撮る

参加していない人に雰囲気を伝えるには、全体の写真が効果的。
参加者の人数や場所の様子もわかります。
これをしないだけでちょっとオシャレな写真が撮れる!
日の丸構図を使わない
家族写真でよくあるのが、このように正面に被写体をおくパターン。
安定して良いけれど、活動の楽しさは伝わりにくいです。
出来るだけ、真ん中ではなく少し横に配置することで違った見え方がします。
ジャマなものは映さない
余計なものは、入らないように。
ジャマなものは、撮影のときに避けるか撮るときに自分が動いて入らないように気をつけましょう。
さいごに
しっかり狙いを定めて撮るのも大切です。
しかし、子どもの表情などは「ここっ!」というときにしか撮れません。
だからこそ、とにかくいっぱい撮るのも大事です。
写真は、少しのコツを知っただけでステキにとれるもの。
デジカメやスマホでも撮れます。
ぜひ、参考にしてご自身の活動に活用してみてください。









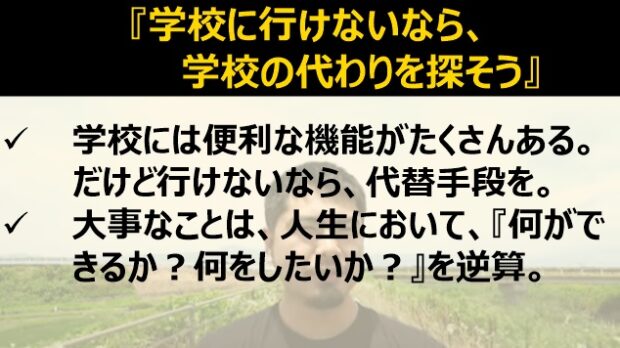

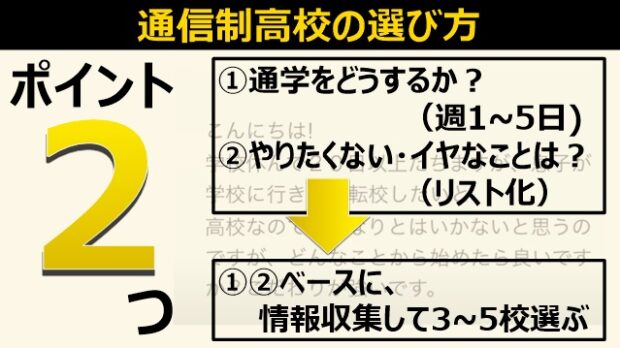
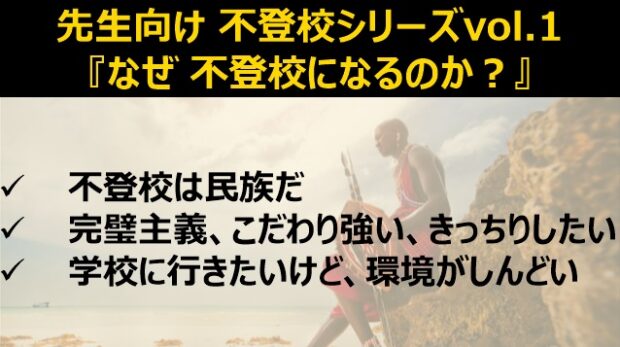
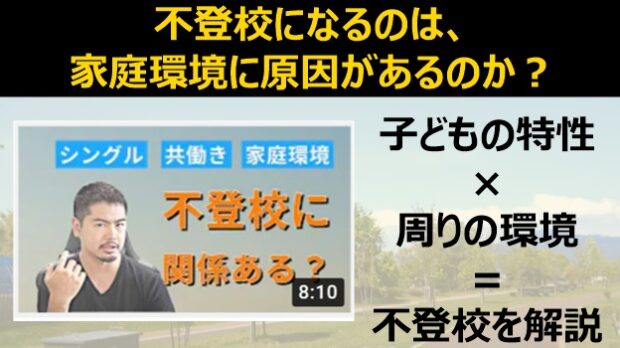
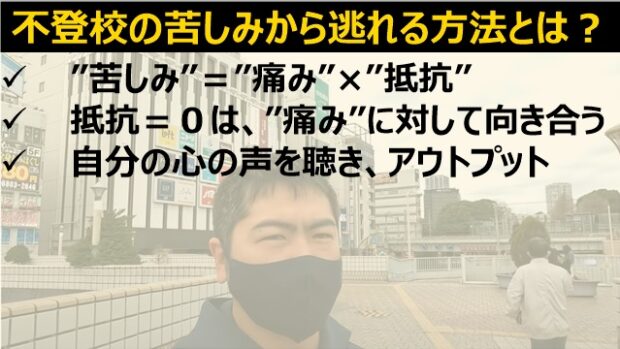
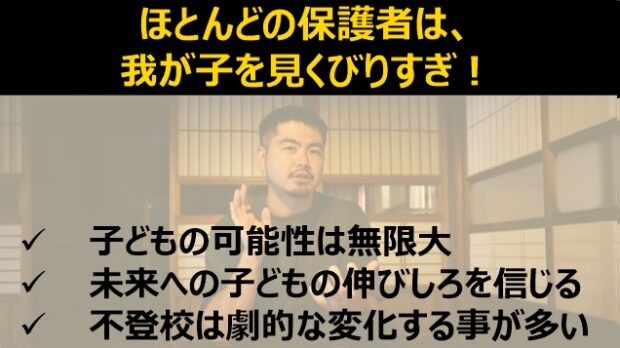




コメント