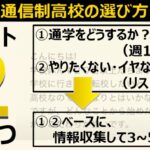2年ほど前に、ホリエモンこと堀江貴文さんが「寿司職人になるのに10年も修行するのはおかしい」と発言し、ちょっとした広がりを見せたことがありました。
私個人は、寿司職人になるための修行の期間についてどうこういうつもりはありませんが、誰かにならうことは大切だと考えます。「学ぶの語源は真似ぶ。まずは真似をすることからはじまるんだ。」なんて学生のころに教えられた私からすると、寿司職人だけじゃなく芸事や職人技が求められるようなことは特に見て学ぶことは大切だと思っています。
ちょっと話は飛びますが、私はTRY部という教室を運営しております。小学生から高校生までが毎週通って、一週間の生活のふりかえりや、チームワークを高める活動を授業としておこなっています。
写真のように、話し合いながらおこなう授業が中心なので体験的に子どもたちは学んでいます。
体験的に学ぶ場をつくっているといえば聞こえはいいですが、これがまた難しいです。
さっきまでめちゃくちゃノッていたのに、次の活動に進んだら一気に熱が冷めてやる気がなくなったり、話したそうにしている子をほっておいて次々話を進める子がいたり。
予定通りに進まなかったり、体験の質があがらなかったりすることもしばしば。
よりよい授業をつくるために、スタッフはよく本を読みます。ネタも増えるし理論も学べるので、本を読むたびに「次はこうしよう」という気持ちになります。ですが、本からの学びでは限界があります。寿司職人と一緒です。やはり学びの場をつくる技術が一番高まるのは、上手な人の進行をみるときです。
想像してみてください。
「では、いまからペアになって話し合いましょう」と促したときに、同じことを言っても相手に伝わる人と伝わらない人がいますよね。
その差はどこにあるのかは、いくら本を読んでも身につきません。上手な人をみて、表情、声のトーン、立ち位置など自分と何が違うのかを比べて見て初めてわかります。そして、上手な人と同じようにやってみて上手くいったことやいかなかったことを自分で点検することで、技術が上達していきます。
だから、本を読むだけでなく体験的に学ぶ場が催されていると、そこへ出かけることもあります。以前、自分も「京都市のまちづくりについて声をあげよう」みたいな趣旨のイベントに顔を出したことがありました。場づくりのプロと言われる人たちがゲストで登壇したり、進行をつとめている会だったので、思いっきりその人たちの所作や言葉の選び方、事前にどんな準備をしていたのか、などなどをつぶさに観察していました。
体験的に学ぶ場をつくる技術を高めることは、寿司職人になるのと同じです。
上手な人をみて、やってみて、ふりかえる。
とはいえ、地域や職場で子どもたちが学び合う場をつくっている皆さまからすると、「わかっとるわい。けど、手本見せてくれる機会なんてそうそうないやん。」と不満を持っている人もいるのではないでしょうか。
だからこそ、D.Liveでは6/28(水)に「”子どもが学び合う場”をつくりたい人が知っておきたい子どもを見るポイント」という講座をおこないます。
私がおこなった授業の動画をみながら、みんなであれやこれやと話し合いながら、子どもが学ぶ場をつくるためには子どもの何に注目すればいいかをみなさんで考えます。
こんなかたにオススメ
・ワークショップというものをしてみたいけど、どうした
・活動はさせているけど、思ったような成果が上がらない
・ファシリテーターについて勉強したい
・子どもが学び合う授業や場所をつくりたい
イベント詳細
日時
6月28日(水) 19:00~20:00
参加費
500円 (資料代)
定員
10名程度
会場
ひとまち交流館 第2会議室(会場名)
京都府京都市下京区梅湊町83−1
アクセスはこちら
お申し込み
お申し込みはメール、もしくはフェイスブックからお願いします。
・メールでのお申し込み
件名を「6/28 公開研修参加」とし、
本文に、お名前・ご住所・ご所属・ご連絡先を明記のうえ、info@dlive.jp にメールをお送りください。
主催
NPO法人D.Live
お問い合わせ先
info@dlive.jp