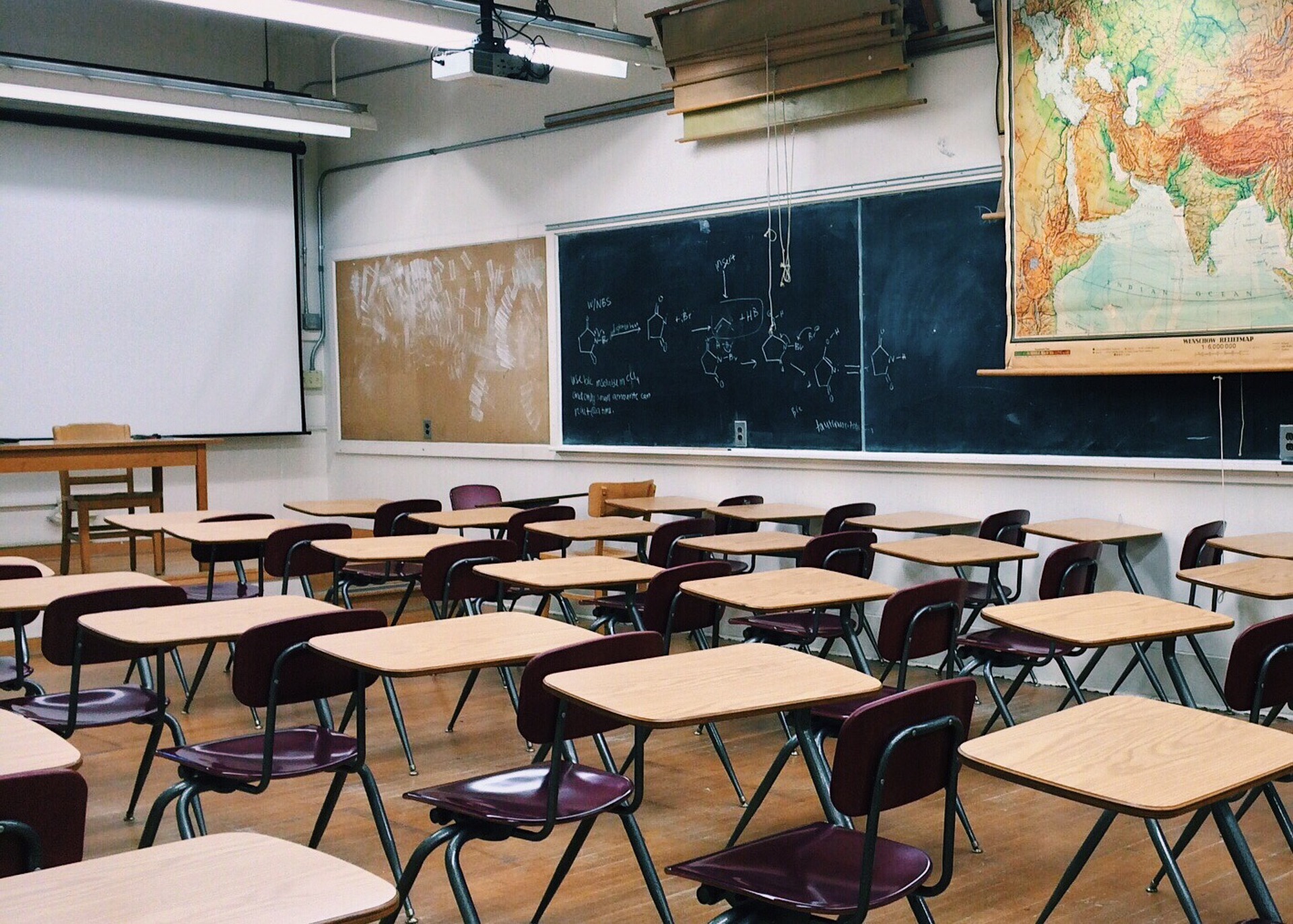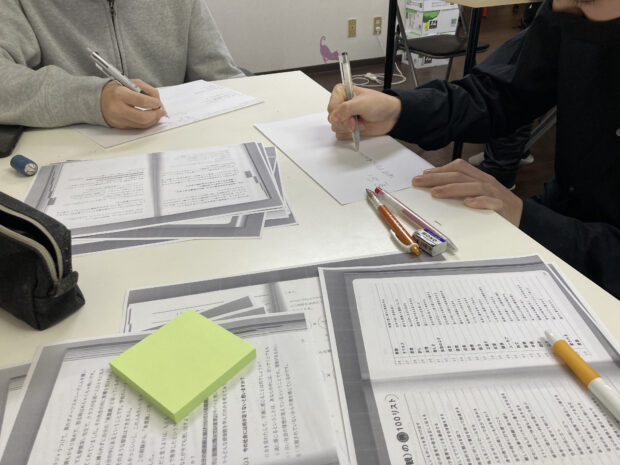先日、インターネットでこんな記事を見つけました。
「学校は必要か問題」才能ある人の意見が参考にならない理由/ひろゆき
このひろゆき氏の文章、一部「それは違うんじゃない?」と思うところも正直あるのですが、学校が必要なのかどうか、というかなり根本的な部分を問うているという点に着目したいと思います。
たしかに僕は中学3年間学校へ行っていませんでした。そしていまだに「集団教育」など画一的な行動を要求する、などといった話を聞くと、無意識のうちに眉をひそめてしまう自分もいます。
しかし、だからといって僕は学校という場所をなくしてほしい、とは微塵にも思いません。別にいま教員という立場で学校で働いているからこうした意見を言っているわけではありません。
世界的に見て、国民に最低限の教育を受けさせることは国力を高めるために必須であり、国の教育水準がそのまま国の経済レベルと比例しているのは間違いない。もし義務教育がなくなれば、日本社会は崩壊してしまうのではないだろうか……。
(中略)
学校は必要だ。それは間違いない。しかし、今の教育システムに合わない人がいることも事実。多様性を受け入れ、一人ひとりが自分に向いている形で学べるような社会になればいいと思う。
引用:小幡和輝(2018)『学校は行かなくてもいい ――親子で読みたい「正しい不登校のやり方」』エッセンシャル出版社
不登校経験者であり、「#不登校は不幸じゃない」発起人の小幡和輝さんは『学校は行かなくてもいい ――親子で読みたい「正しい不登校のやり方」』という本の中で、上記のように学校や義務教育が必要な理由を論じていますが、僕はまったく同じ意見を持っています。
ただここで大事なのは、小幡さんの言葉で言えば「今の教育システムに合わない人がいる」ということ。
先週も少し触れた不登校の情報を発信されているTwitterの数々を見ていると、「不登校の子どもたちが来れるような学校に変えないといけない」という意見が多々見受けられます。たしかに不登校の子どもが増えている現状を鑑みれば、それは自然な意見なのかもしれません。
しかし僕は、別に学校の環境を不登校の子どもに寄せる必要はない、と思っています。
なぜかといえば、仮に不登校の子どもたちが楽しく通えるように工夫したとしても、その「不登校の子どもたちが楽しく通える学校」が嫌で不登校になる子どもが出てくるからです。
これは、「学校」という場所がある以上は、根本的な制度を大きく変えるということでもしないかぎり、絶対に出てくる子どもたちです。
たとえば学校ではおなじみの光景である画一的な一斉授業。確かに僕もこれがなければもしかしたら楽しく学校へ通えていたかもしれません。実際にこうした一斉授業はもはや時代遅れなのではないか、という意見もあります。
ただ、仮に一斉授業をやめてしまうとなれば、今度は一斉授業でないとしんどい、という子どもたちが行き場をなくしてしまうわけです。そこに人数の多い少ないはあるかもしれませんが、それでもなお「不登校の子どもたちがいる」ということに変わりはありません。
これに限らず、そもそも教室の雰囲気、学校の構造、という面がネックで不登校になった子どもたちがいたとして、そういう子どもが通えるようにたとえばファンシーな雰囲気の学校に改造したとしても、そのファンシーな雰囲気が受け入れられずに不登校になる子どもが出てくることでしょう。
そんなわけで、僕は常日頃から「学校という場所がある限り、不登校がなくなることはない」と思っています。
大学で教職課程に在籍していたころ、「不登校をなくしたいんです!」と宣言する学生さんの話も聞いたことがありましたが、現実的にそれは無理だよね・・・という感想しか出てきませんでした。
「学校に通うのが楽しくなるクラスにしたいです!」という声も聞いたことがあります。たしかにそんなクラスがあれば僕も学校という場所に違和感なく通えたかもしれませんが、僕はついつい仮にそんなクラスがあったとしても「楽しくない子どもたち」の心情を慮ってしまいます。
どれだけ楽しく、ということを意識しても、100%全員が楽しむことのできるものを作るのはすごく難しいです。そこで、いかに「楽しむことのできていない」子どもたちに注意を払うのか。ここに気を使うことのできる先生を、僕は心から尊敬しています。
話をもとに戻しましょう。
前述しましたが、僕は「別に学校の環境を不登校の子どもに寄せる必要はない」と思っています。学校という場所がある限りは、たとえ不登校の子どもに寄せた学校に変化させても、その学校が受け入れられずにまた新たな不登校が増えるだけ、というのは間違いないと考えています。
だからこそ、「学校がしんどい子どもたち」に向けての支援だけはきっちりと充実させておかなくてはならない、と思います。
「学校がしんどい」原因がワンパターンであれば、容易に学校という場所を改造することができるかもしれません。しかし、授業、友達、人間関係、そもそもの雰囲気・・・学校に通えなくなる原因というものは千差万別、人それぞれの理由があるのです。
これを学校を通してすべて解決しようと思えば、途方もない労力が必要です。
小幡さんの言う「今の教育システムに合わない人」というのは、どんな教育システムであっても一定数存在します。繰り返しますが、学校という場は必要ですが、そこに馴染むことのできない子どもたちをどのようにして支えていくかが大事だと僕は考えています。
◆小冊子『不登校の子が劇的に変わるヒミツ』をプレゼント中◆
下記フォームでお申込みいただくと、メールにファイルを添付し、お送りいたします。