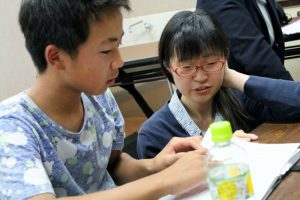「え、こんなん何ゆっても意味ないやん。もうこの話し合いの場に関わることはやめよう。」
そう決めてからのぼくは心のシャッターをピシャっと下ろして、
早く時間がすぎることだけをじっと待っていました。
こんにちは。D.Liveスタッフの得津です。
これは、以前ぼくが参加したイベントでの出来事でした。
そのイベントの途中のことです。
ある社会課題について広く知ってもらう方法について、4人グループを組んで話し合う時間がありました。
こういうとき、ぼくは最初は自分から話して、途中から聞き手に回るというスタンスをよく取っています。
周りの出方を探っているうちに時間切れになるのがイヤなのと、自分から意見を出せば相手も言いやすくなるかなと思っているからです。
幸いにも今回のグループでは話し合うテーマに詳しい人がいました。
彼が「何でも意見言ってください!」と話し合いの前に言ってくれていたので、
ぼくのエンジンは最初から最高潮でした。
司会の合図で話し合いがはじまり、ぼくは早速手を上げて言いました。
「こんな方法はどうですか!」
『いや、ぼくはそういうの好きじゃないんですよね。』
ぼくは耳を疑いました。
「何でも意見言っていい」といったあなたがそれを言うのかと。
しかも話し合いのはじめから。
確かにぼくが言ったアイデアは素晴らしいかと言われれば、全然そんなことはありません。
それは自分もよく分かっているけど、まずは案を出すことが大事じゃないの。
笑点だってトップバッターには座布団くれるじゃない。
思わずこんなことが口に出そうになりましたが、グッと我慢しました。
初対面の人だし、こんなこともあるかと気持ちをきりかえようと努めましたが、
他のメンバーのトーンが下がっていくのを感じました。
そこからの話し合いはもう話し合いではなくて、意見の品評会でした。
誰かが意見を出す。それについての評価が先ほどの人から言い渡される。
アイデアを出す3人(ぼくはこっち)と、評価を出す1人。
こんな構図になってしまった。
だからぼくは諦めてしまいました。「何を言ってもダメだ」と。
この人は自分の話を聞いてくれないと思うと、話そうという気持ちが全然わいてこない。
当たり前のことをあらためて実感させられた日でした。
ぼくは小5〜高3の子どもたちに向けた塾を開いています。
塾に通う子どもたちもよく言います。
「先生、全然はなしきいてくれへん!」
「お母さん、ぼくが悪いことした時すぐ怒る。悪いのは分かってるけど、ぼくの聞いて欲しい。」
聞いてくれないという経験が積み重なると、話そうと言う気持ちは枯れていきます。
大人も子どもも同じです。
「自分の意見を言えるようになって欲しい。」
「うちの子、コミュニケーション能力が無いんです。」
保護者さんから、このようなご相談をいただいたら、
お子さんん最後まで話を聞いてくださいとぼくたちは伝えています。
もう本当にこれなんです。
子どものコミュニケーション能力を伸ばすには、最後まで相手の話を聞くことに尽きます。
この姿勢について最高のお手本がいます。
ちびまる子ちゃんの友蔵です。
友蔵が最後まで話を聞いてくれるから、まる子は安心して学校やお母さんのグチが言えるんです。
まる子がおしゃべりだから友蔵が聞き手になっているのではありません。
順番が逆なんです。友蔵という聞き手がいるから話すことができるんです。
コミュニケーションは聞き手が先なんです。
相手の話を聞くのに特別な技術は必要ありません。
ただ、最後まで聞くだけでいいんです。
けれど、ぼくたち大人は相手が意見を言い終わる前に自分の意見を言うことに慣れてしまいました。
バラエティー番組ではひな壇の芸人が、政治の番組ではパネリストたちがこのような振る舞いをしています。
コミュニケーションはキャッチボールなんてよく言いますが、これでは相手が投げ終わる前にこっちがボールを投げているようなものです。
まずは子どもが言い終わるまで話を聞く。
自分の意見は子どもが言い終わってから言えばいい。
それだけで子どものコミュニケーション能力は育ちます。
ぼくたちは自分の教室でこのことを実感してきました。
自分のことをコミュ障と言っていた生徒は教室に通ってから、学校で友だちとの会話を楽しめるようになりました。
スタッフが話しかけても「うん」か「いいえ」しか話さなかった生徒は、自分からスタッフに話しかけてくれるようになりました。
子どもの話を最後まで聞くようになると、子どもの学力も育ちます。
ぼくたちの授業では話し合いの前に、プリントに自分の意見を書かせることがあります。
学校の授業でもよく行われている方法です。
話し合いに参加しない生徒は、そもそもプリントに自分の意見を書きません。書いてもせいぜい一文くらい。これでは考える力も育ちません。ですが、こちらが話を聞く態度を示し続けるとプリントにも自分の考えを書いてくれるようになりました。
自分で考える力が戻ってきたんです。
子どもの話を最後まで聞くことで、子どものコミュニケーション能力は大きく育ちます。
・自分の意見を言えるようになって欲しい
・同じクラスの子と話すのが苦手そうだ
・子どもが大人になった時、コミュニケーション能力が大切だと思っている。
このようなことをお考えの保護者さんは、
子どもの話を最後まで聞くということを始めてみてはいかがでしょうか。
「でも具体的にどうするの?」
「それは分かっているんだけど、やっぱり難しい。」
子どもの話を聞いてあげたい。コミュニケーション能力が育って欲しい。そうお考えの保護者さんこそ、こんな気持ちもきっとあることと思います。
ですから、2月24日(土)にこんな講座をおこないます。
<
div class=”_4-u2 _3xaf _3-95 _4-u8″>
<
div class=”_2qgs”>
「子どもが積極的に話し合いに参加する方法 -授業参観で物足りなさを感じたあなたへ-」
<
div class=”text_exposed_root text_exposed”>この講座では、ぼくたちがどんな授業をしているから子どものコミュニケーション能力がつくかをお伝えします。スタッフが大切にしていることとその実践をご紹介し、教室でおこなっている授業も体験していただきます。
■ この講座で得られるもの
・思春期の子どもがどんなことを考えているかわかる
・子どもへの具体的な関わりかたが学べる
・子どもの自信や自尊感情について学べる
・どうして授業で子どもが話し合いに消極的なのか分かる
・学校の話し合い活動に参加しやすくなるための関わり方が学べる
日時: 2/24(土) 14:00 – 16:30
場所: コワーキングスペース Mag House (JR瀬田駅3分)
滋賀県大津市大萱一丁目9−7ワイエムビル202
人数: 7名ほど
対象: 小5〜高3のお子さんがいる保護者さん
参加費:1,000円
お申し込み:https://peraichi.com/landing_pages/view/dlive2
こちらのHPの一番下のフォームからお願いします。
プログラム:
・自己紹介
・話題提供
1、話し合い活動が学校で重要視される背景
2、子どもが安心できる話し合い環境とは
3、学校で求められている対話的コミュニケーションの伸ばし方
・体験TRY部 私たちが子どもにおこなっている授業を体験してもらう時間です!
・親として子どもにできることは何かを考える時間
・ふりかえり