先日、こんなニュースが報じられました。
2014年度の全国における「不登校」(病気や長期欠席以外の理由で学校を年間30日以上欠席している児童)の小中学生は12万2655人。これは前年より3300人多く、特に小学生の不登校児童数2万5866人は過去最多の数字となったようです。
これを受けて書かれた、紀伊民報の8月10日分に掲載されたコラムが、僕の気になる教育ニュース。
なんでも、紀伊民報が発行されている和歌山県は、小学生の不登校率が一番高かった都道府県だそうで、このコラムではとにかく不登校の児童数の多さを悲観する内容が書かれています。冒頭の「意気消沈する数字」にはじまり、頭が痛い、ビリ・・・とにかく後ろ向きな言葉が並んでいます。
最後の段落から察するに、このコラムを書いた記者は毎日学校が楽しかったようです。しかし、みんながみんな「学校が楽しい」と思いながら生きていた訳ではないことは確かだと思います。
学校に行かないと言うことは本当に「悪いこと」なのか?
学校環境から考えると、不登校児童数が多いという現状は確かに「悪いこと」なのかもしれません。
しかし不登校の児童数を0にするというのは、まず間違いなく不可能だと思います。忌引きや病欠は仕方ないとして、例えば日本全国の6歳から12歳の子どもたちが全員毎日小学校に通うという社会は何一つとして面白くない、ということは先日も書きました。
人間はロボットではありません。すなわちひとりひとり違う性格を持っています。国語が好き、理科が嫌い、休み時間は校庭でドッジボールするのが大好き、図書館で一人で本を読むほうが落ち着く・・・そんな個性のなかのひとつが「学校に行きたくない」ということだと思います。
学校に行く、という「マジョリティ」から、学校に行かない、という「マイノリティ」へ。両親の教育方針ということも最近は多いようですが、自らの意志で「学校に行かない」というマイノリティを選択することが、僕には悪いことだとは思えません。
何よりも不登校で一番苦しい思いをするのは本人(と保護者)です。マイノリティを選択、とさらっと書きましたが、「学校に行かない」と言うマイノリティを選ぶのは相当に覚悟がいることです。この世の中に自分の居場所がどこにもない、という感覚は、本当に「地獄」です。
「学校に行かない」選択によって救われた命もある
僕ももしかしたらその選択によって救われた命を今生きているのかもしれません。僕以外にも「学校に行かない」と言う選択によって助けられた命を生きている、と考えている人は多いと思います。
以前にも書きましたが、温かく見守ってくれる大人がいて、自分の個性を伸ばせる場所があったら、それがその人にとっての「学校」だと思います。フリースクールについても義務教育化に向けた動きが高まっています。これもまた、不登校の児童にとっては大きなニュースです。
「不登校」が悪いことだ、という目で見られることのない社会を目指すのも、もしかしたら不登校問題を解決する一歩になるかもしれません。「不登校はだめなこと」と言う概念がきれいさっぱり消える社会が来ることを願うばかりです。




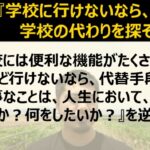
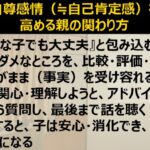
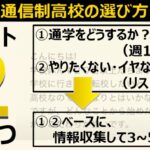











コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 「不登校は悪いことなのか?」という疑問に関しては以前コラムを書きました(最近気になる教育ニュースVol.2―不登校は「悪」なのか?)。そんな折、1月末に小中学生の不登校の生徒数が6万5000人いるという調査結果が報じられました。 […]