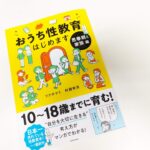思春期の子どもたちの発達課題の1つに、アイデンティティの獲得があります。
アイデンティティは、「自分はこういう存在なんだ」と自分で認識することをさします。思春期になると、心も体も発達しますし、交友関係も広がります。自分自身を客観的にとらえるようにもなります。その成長の過程で、「自分っていったい何者だろう?」と悩むようになります、というのが教育心理学で言われいてることです。
昨日、「耳をすませば」が金曜ロードショーで放送されていましたが、この映画はまさしくアイデンティティ獲得のお話です。バイオリン職人をめざす男の子に恋をした主人公(しずく)が、受験を控えながらも男の子のようになりたいともがきながら自分とは何かを見つけていきます。
作中のクライマックス、主人公のしずくが初めて書き上げた物語を男の子の師匠に読んでもらう場面があります。ここでしずくが、物語を書きながら実力不足に気づき、それでもなお書き上げた心情を泣きながら師匠に話します。アイデンティティ的にはここで物語が完結します。自分が何者であるのか、自分で気づいた瞬間です。
しばしば、私たちD.Liveは子どもたちと関わる中で「耳をすませば」の師匠的な役割をします。子どもたちの頑張りを認め、励まし、自分が何者であるのかを自覚するお手伝いをします。
「耳をすませば」を見ながら改めてD.Liveが果たす役割について考えていたら、ふとこんな考えが頭をよぎりました。
父親も現代社会において、父親としてのアイデンティティを獲得することが困難ではないのか。
なぜ、このように私が感じたのか。そして、なぜ父親としてのアイデンティティを獲得するのが難しいのか。
世の男性はどうすればいいのか。今日はそういうことについて私の考えをお話しします。長いまくらでした。
まず、私がどうして父親のアイデンティティ獲得が困難だと考えたか、その理由についてお話しします。私たちD.Liveは、中高生の教室運営や講演活動をしていますから保護者さんから相談を受けることもあります。そのほとんどがお母さんなのですが、たまにお父さんからも相談を受けることがあります。
お父さんからは、お母さん同様に子どもとの関わり方がわからないというお話もありますが、「父親」としてどうすればいいかわからないというお話もいただきます。この、「父親」としてどうすればいいかわからないということが、お父さんならではの悩みであり、父親としてのアイデンティティに関わる悩みだなと思うのです。
教育学では「父性」とは、ルールや規範を子どもに教える役割とされています。「遊具は順番に並んで遊ぼう」とか「友達をたたいてはいけません」とかですね。このような決まりはお母さんももちろん子どもに伝えますが、子どもだってルールを破る時があります。そんな時にルールや規範を強化する存在として呼び出されるのが父親です。サザエさんの波平がカツオくんを叱る場面を思い浮かべてもらうとわかりやすいかと思います。
ですがどうでしょう。いまの時代に波平的な役割を果たす父親は、もうほとんどいないんじゃないかと私は思います。その理由は二つあります。一つは、仕事をしてお金を稼ぐことに必死にならざるを得ない状況にあること。
哲学者の内田樹さんは、GQのコラム「2013年、「父親の不在」を文学は告げている──内田 樹×高橋源一郎」のなかで、父親の不在についてこのように述べています。
どこかで家父長の権原を「金を稼いでくること」に限定して、それに甘んじていたのがいけなかったんだろうね。金さえ稼いでくれば父や夫でいられるわけじゃない。そんなの副次的なことであって、家のなかで父性原理を体現するのが父親の仕事だったんだけど。
確かに、父親の役割を金を稼いでくることに限定して考えている人もいるでしょうけど、今の時代を生きる父親は必ずしもそうじゃないと思うんです。関わりたいけど、忙しすぎて関われない状況の父親も多いと思います。だから、自分なりの父親をさぐることができない。
もう一つは、父親が「父性」を担う風潮が破壊されたことです。「イクメン」という言葉があります。「イクメン」とは「子育てする男性(メンズ)」の略語で、積極的に子育てを楽しみ、自らも成長する父親のことです。
2010年ごろからこの言葉が流行りだし、父親の育児参加を促す風潮が強まりました。いいことだと思うんです。お父さんも子育てに参加することって。ですが、父親の育児参加を促す流れに乗っかって波平的な父性も破壊されたのではないかというのが私の考えです。
だから、世のお父さんは子どもに母親のように関わることが多いと聞きます。しかし、お父さんはその関わり方を自ら選んだのではなく、イクメンブームような風潮によって選ばされたんじゃないか。
父性的な役割を果たしたいけれど、その仕方がわからない。ロールモデルもいない。だったらお母さんのように優しく子どもに関わってみようか。でも、これが父親なのか。自分の父親はこんな風に自分には接してくれなかったぞ。というような、片付かない気持ちを抱えているだろうと私は推察します。そして、こんなことを話すこともないから父親としてのアイデンティティを獲得することができない。
ここまで、自分なりに父親のアイデンティティ獲得の難しさについて述べてきましたが実際のところはどうなんでしょうね。実は全然的外れなことをベラベラと話しているのかも知れません。ただ、はっきりしているのは「父親としてのあり方」に悩んでいるお父さんがいるということです。
ですから、父親としてのあり方や関わり方ついて考える場をつくることにしました。「思春期の子どもを持つ父がはたす役割とは?」というイベントです。
個人的には、思春期の子どもにとって父親は「超えられるべき壁」として存在するべきだと考えています。子どもの自立のためにはいつまでも父親にべったりしてもらうのではなく、超えてもらうべきだろうと。
みなさんは、どうお考えになりますか。
父親の役割や父親としての関わり方について考える機会が少ないだろうと思うので、この機会に一度一緒にお話ししませんか。
ちなみにこのイベントは父親限定ではありません。
なんとなく考えてみたい学生さんも、本当はお父さんに言いたいことがあるお母さんも大歓迎です。みんな平等な立場で話し合い、父親としてどう関わっていくのかを探り、自分なりの答えが見つけられる場を作ります。
今回の「思春期の子どもを持つ父がはたす役割とは?」というイベントをどのような場にしようかと考え、先行事例を探していた時に似たようなイベントをされたレポート記事を見つけました。このレポートには
「父親としてのありたい姿」を考えていく中で、各父親たちの子育ての悩みが徐々に解消されていきました。
とありました。
確かにありたい姿を考えることは大事ですけど、もう1つ踏み込みたい。具体的に何をするかがわかる場にしたい。そのために、「子どもの自信白書」にある子どもの声を考える材料にします。
つまり今回のイベントで得られるものは
・父親の役割について学べる
・父親について相談できる
・思春期の子どもの悩みがわかる
この3つです。下記に、イベントの詳細とお申し込みについてまとめました。ぜひふるってご参加下さい。
////// イベントの詳細 ///////
「思春期の子どもを持つ父がはたす役割とは?」
◎日時:2月12日 14:00 – 16:30 受付13:30
◎定員:10名程度
◎参加費:1,000円
◎場所:守山宿・町家「うの家(け)」
JR守山駅から徒歩10分(滋賀県守山市守山一丁目10
http://www.unoke.jp/
◎特典:子どもの自信白書’16 をプレゼント!
「子どもの自信白書’16」は小中高生210人に聞いた
<白書を読んだ感想>
・この白書を読んで、自分の子育てが間違ってなかったん
・子どもの声が載っているのがすごくいい。知ってるよう
////// イベントのお申し込み ///////
1、info@dlive.jp に、件名「2/12イベント申し込み」、本文にお名前・ご連絡先・参加人数を明記のうえご連絡。
2、D.Liveのフェイスブックページからお申し込み。ページはこちら