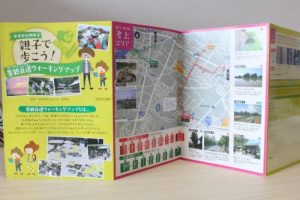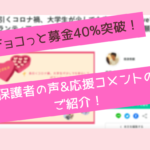こんにちは。スタッフの得津です。
突然ですが大学生は悩んでいるそうです。
就職活動を目前にして「やりたいことが見つからない」と。
僕自身、そんな学生の相談に乗ったこともありますし、ニュースなどでも就職活動の時期になるとやりたいことが見つからなくて悩んでいる学生の特集がされていることから、結構メジャーな問題のようです。そんな話を聴くにつけ、子どもを持つ保護者さんとしては「就活で悩むことなく、自分の好きなことや、やりたいことを見つけて仕事について欲しい」と願うのが親心ではないでしょうか。
では、子どもが将来やりたいことを見つけるために何ができるのでしょうか。
お稽古事をさせてみることでしょうか。
好きなことや得意なことを小さい頃から見定め、それを徹底的に磨くことでしょうか。
高校生頃から自己分析や適職診断をさせてみることでしょうか。
多分どれも違います。
僕は子どもに役割を与えることだと強く確信しています。
僕は内田樹さんという人の本が好きでよく読みます。内田樹さんは大学の先生をしていたので、先ほど述べた「やりたいことがない」大学生の悩み相談をよく受けるのでしょう。いくつかの本で、「天職」についてこう述べています。
仕事というのは自分で選ぶものではなく、仕事の方から呼ばれるものだと僕は考えています。
「天職」のことを英語では「コーリング(calling)」とか「ヴォケーション(vocation)」と言いますが、どちらも原義は「呼ばれること」です。
僕たちは、自分にどんな適性や潜在能力があるかを知らない。でも、「この仕事をやってください」と頼まれることがある。あなたが頼まれた仕事があなたを呼んでいる仕事なのだ、そういうふうに考えるように学生には教えてきました。(中略)
歯科医によると、世の中には「入れ歯が合う人」と「合わない人」がいるそうです。
合う人は作ってもらった入れ歯が一発で合う。合わない人はいくら作り直しても合わない。別に口蓋の形状に違いがあるわけではありません。自分の本来の歯があった時の感覚が「自然」で、それと違う状態は全部「不自然」だから嫌だという人は、何度やっても合わない。それに対して「歯がなくなった」という現実を涼しく受け入れた人は「入れ歯」という新しい状況にも自然に適応できる。多少の違和感は許容範囲。あとは自分で工夫して合わせればいい。
結婚も就職も、ある意味では「入れ歯」と同じです。
自分自身は少しも変わらず自分のままでいて、それにぴったり合う「理想の配偶者」や「理想の職業」との出会いを待ち望んでいる人は、たぶん永遠に「ぴったりくるもの」に出会うことができないでしょう。
「どんな相手と結婚しても、そこそこ幸福になれる人」は「理想の配偶者以外は受け付けられない人」より市民的成熟度が高いと僕は思います。
親族というのが「それが絶えたら共同体が立ち行かないもの」である以上、 「大人」とはそういうものでなければ困る。
仕事だってそうです。
「どんな職業についても、そこそこ能力を発揮できて、そこそこ楽しそうな人」こそが成熟した働き手であり、キャリア教育はその育成をこそ目指すべきだと僕は思っています。
自分にどんな能力があるかなんて、実際に仕事をしてみなくちゃわからない。分かった時にはもうけっこうその道の専門家になっていて、今さら「別の仕事に就いていたら、ずっと能力が発揮できたのに…」というような仮定の話はする気もなくなっている、というものではないでしょうか。
本当にこの通りだと思うんです。子どもがやりたいことを見つけるために必要なことって。
だから、僕は子どもたちに役割を与えることをどんどん推奨します。お家だったら、家事の手伝いをどんどんさせてください。それだけで変わります。
役割を与え、そこで経験したことが子ども自身の「おれって、こんなことできるんだなぁ」という自己理解につながります。さらにお手伝いのうまいところは、やってくれたら「ありがとう」って絶対言うと思うんです。この「ありがとう」は、子どもの自尊感情を高めるマジックワードなので、お手伝いをすることで家の中で役立っている自分とお手伝いの中で発見した自分を強化することにつながります。要は自信が持てるのです。
さらに役割というのは連鎖します。一つの役割を終えると、また次の役割が子どもを呼びにくるのです。
皆さんも経験的にあると思います。任された仕事が片付いたら、また次の仕事がふってくることが。その次々と仕事が来る流れの中で、気づけば能力や経験が蓄積されていく。内田さんの文章から引用した最後の部分はそういうことです。
役割に自分を合わせる中で能力を開発し、できることとやりたいことが広がっていく。これを文科省は「キャリア」と呼び、この役割と経験の積み重ねを進めることを「キャリア教育」といったのです。
社会人の話を聞かせたり、適職診断をさせることだけがキャリア教育じゃありません。それらはあくまで一要素です。学級で何かの係をさせてみたり、お家でお手伝いをさせてみることも立派なキャリア形成です。
ですから、お手伝いを渋り出す難しい年頃であっても、どんどんお手伝いを進めてください。断られてもめげずに声をかけましょう。僕も居場所づくり事業でご飯の片付けを子どもに呼びかけてますが断れることも多いです。でも翌週にはやってくれることもあるので、続けることが大事なんだと実感します。
僕は昨日、大阪の高槻市にある「コミュニティハウス はらいふ」というところへ行きました。最寄りの駅からは車で20分ほど山間部へ向かったところにあります。縁側からは秋らしく色づいた山々が見え、とても静かな場所です。僕の大学時代の後輩がここの管理人をしていて、打ち合わせがてら遊びに行ったのです。
(写真が「コミュニティハウス はらいふ」。HPはこちら)
後輩も僕と同じく教育大学を卒業しているのですが、今は教育と離れた仕事をしています。
「生活がしんどい高校生の支援をしていると、どんどん福祉のことに興味が出てくるし、街から離れたこの場所で畑はじめたり、コミュニティづくりをしてたら、場づくりが好きなんだなぁって思う。梅田とかもう人多すぎて、全然いきたくないけど、ここでも丁寧に暮らしてたら結構ぜいたくな暮らしできるで」
そう話す後輩の変化に驚きつつも、コミュニティハウス管理人という役割が彼の能力を開花させ、彼がやりたいことを見つける大きなきっかけになったことを実感しました。
お知らせ
「子どもが本当にやりたいことを見つけるために大人ができること」というテーマで、
子どもの自信白書の読書会を開きます。
私たちが作成した「子どもの自信白書’16」に掲載されている子どもの声を拾いながら、「子どもが本当にやりたいことを見つけるために大人ができること」って何があるのか、参加者のみなさんとお話ししながら見つけていく会です。
「子どもの自信白書’16」は当日プレゼントいたしますし、読書会に今まで参加されたことのない方でもご参加いただけます。初めてでも参加しやすい会になっていますので、ぜひご参加下さい!
日時:12月4日(日)14時〜16時 受けつけ13時半〜
場所:京都市中京区六角油小路町345-2 「学び舎 傍楽」
(地下鉄四条 阪急烏丸駅より 徒歩8分) HPはこちら
定員:10名
参加費:1,000円
企画協力:「学び舎 傍楽」
お申し込み: info@dlive.jp まで、件名「読書会申込み」 本文にお名前・所属・ご連絡先を明記の上メールを送ってください。