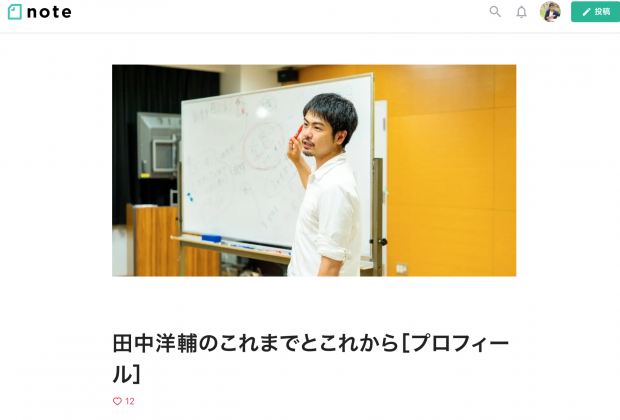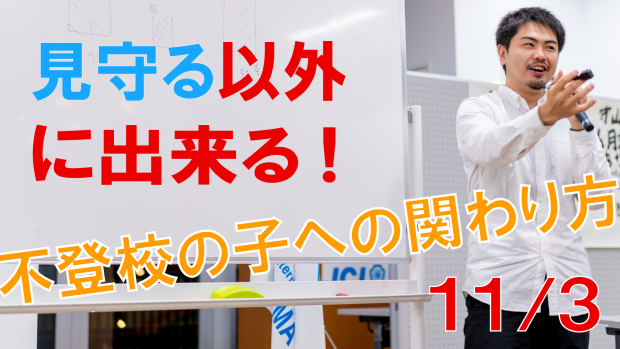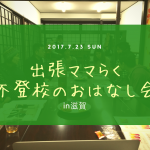はじめまして。
NPO法人 D.Liveの田中洋輔です。
僕は、普段は滋賀県の大津市で不登校の子が通うフリースクールを運営しています。
僕自身、中学3年生のときに学校がしんどくなり、高校生で不登校。大学生のときには、1年ほど引きこもりでした。
そこから立ち上がり、今の団体を立ち上げ、不登校支援をするようになりました。
LINE@やYoutubeで不登校の子への関わり方を発信するようになり、たくさんのお悩み相談や質問をいただきます。
その中で、圧倒的に多いのが「どのように関わればいいでしょうか?」というもの。
今は、インターネットを探せばたくさんの情報が出てきます。ほとんどの問題は、検索するだけで解決するような世の中。
なのに、です。
不登校の子への具体的なかかわり方ってほとんどないんですよ。
学校の先生は、「元気になるまでしばらくは、休んでいていいですよ」と言う。
カウンセラーは、「見守ってあげてください」と言う。
いや、いつまで待てばいいんでしょうか?
“しばらく”ってのはどれくらい?
1週間? 1ヶ月? 1年?
“見守る”ってなに?
なにか出来ることはないの?
しんどそうにしている子どもを見て、ただじっと見ておくだけ?
助けになりたいのに、手を出しちゃいけないの?
心の声、叫びが毎日のように届きます。
先生もスクールカウンセラーも不登校を知らない
はっきり言いますが、ほとんどの人は、不登校のことを分かっていないんですよ。
カウンセラーも学校の先生も。
だって、彼らの多くは学校に行けていた人たちです。
学校がしんどいという感覚がそもそも分からないのです。
たとえば、ラーメン大好きな人が、ラーメンを嫌いな人の気持ちが分かるでしょうか?
分からないですよね。
先生が悪いとかスクールカウンセラーがダメとかという話ではありません。
ただ、単純に理解ができないのです。
僕は、フリースクールで毎日のように不登校の子と関わります。
そして、僕自身が不登校でした。
だから、なにがイヤか。どうして欲しいか。なにで困っているかが分かります。
毎日のように子どもたちと接していきながら、学んできました。
試行錯誤をして、「こうすればいいのか」という関わり方を会得していきました。
学校の先生もスクールカウンセラーも、不登校の子と関わる機会はほとんどありません。
知らないんですよね。不登校の子の生態を。
どうして、ずっとゲームしているのか?
なぜ、昼夜逆転するのか?
分からないまま、「見守りましょう」とか「昼夜逆転は、良くないですねぇ」なんていう正論を言うのです。
仕方ないのです。知らないから。
学校の先生もスクールカウンセラーも、不登校の専門家ではありません。
料理人でも、フレンチや中華、和食などそれぞれ専門分野が違うように、彼らもすべてが出来る、分かるわけではないのです。
でも、ですよ。
でもね、じゃあ他の専門家たち、不登校支援の人たちが不登校について教えてくれたらいいじゃないですか。具体的なかかわり方を教えてくれたらいいですよね。
しかし、ないのです。ほとんどない。
結局、どうしたらいいのかよく分からないんですよ。調べても。
「前を向くためにサポートしてあげましょう」
「じっくり話を聞いてあげましょう」
抽象的な言葉ばかりが並び、具体的にどうしたらいいのかが見えないのです。
だからこそ、僕はとにかく具体的な方法をどんどん伝えていきたいと思っています。
正直、あいまいな表現をしている他の人たちの気持ちもよく分かります。
不登校と言っても、十人十色で、子どもによって対応は変わります。
子どもによって、合うこと合わないことがあるので、「こうしてください」と強く言えないのです。
でもね、絶対的な不文律のルールは存在しています。
「これだけは守る」という絶対があるのです。
その内容を今度のイベントではお伝えしようと思っています。
不登校の理解から始める
そもそも不登校の子への関わり方を理解するためには、“不登校”の理解が必要です。
なぜ、不登校になるのか?
不登校になりやすい子とは、どういう子なのか?
学校に行けない理由はなにか?
どうして昼夜逆転になってしまうのか?
この辺りのことを知っていないと、その子に合った声かけが出来ないのです。
イグアナがなにを食べるのか、どんな環境で育つのか知らないと、イグアナを飼うことが難しいように。
理解することが出来ると、自分なりに工夫して声をかけることができます。
風邪の子に、「いつまでも寝ているんじゃないよっ!」と叱る人はいませんよね?
「しばらく寝ていなさい」「あたたかくしておくんだよ」と声をかけられます。
出来ることが見えてきて、自分なりに試行錯誤もできるようになります。
また、不登校には大きく4つの段階があります。
行き渋りから始まり、フリースクールや学校へ復帰するまでの段階があるのです。
段階があるのを知らないから不安になるのです。
妊娠をするといくつかの段階を踏んでいくように、不登校もステップがあります。
そのステップが分かっていると、見通しがつきます。
「あっ、うちの子は、次はこの段階だからこうなるな」と。
人は見通しがつかないと不安になります。
あなたが不登校のことで心配になる大きな要因は、先が見えないからです。
「もしかしたら、このまま引きこもりになるんじゃないの?」
「このまま、家から出ないとどうなるんだろう?」
「毎日ゲームばかりしている日々が永遠に続くのでは?」
妊娠についてまったく知らないと、お腹が膨らんできたとき不安になるはずです。
「え? このままお腹が膨らみ過ぎたらどうしよう?」
「気持ち悪いのがずっと続くのでは?」と。
でも、つわりは一時的なものだし、いつかは赤ちゃんが生まれることをあなたは知っています。
だから、不安に感じることがないのです。
不登校の段階を知り、今、うちの子がどの段階にいるのか。そして、これからどういう経過をたどるのか。それを知っていると、だいぶ不安は軽減されます。
“しばらく”という曖昧な表現ではなく、具体的な目安が分かるのです。
すべての質問に回答します
当日は、とにかく具体的な関わり方を重点においてお話をします。
そのため、どんな学年や年齢であっても活用していただけます。
行き渋りや別室登校をしている子には、押すタイミング、引くタイミングが分かる。
ずっとゲームばかりしていて暇そうにしている子には、なにをすればいいかが分かる。
「ひまやー」と言う子には、どんなことを、どんな風に提案すればいいかが分かる。
集団や人が苦手な子には、なにが必要で、どんなことをすばれいいのかが分かる。
ご参加いただくかた、すべての悩みが解決できるように答えます。
今回、久々に東京へ行く機会があるので、講演会と質疑応答を午前と午後に分けておこないます。
参加することで、不登校の生態がどのようなものかが分かり、具体的な関わり方を知ることができます。
帰ってスグに「これしよう!」と思えます。
不安に思っていること、心配なこと、どうしたらいいか分からないことはすべて解消して帰っていただきます。
質問は、すべて答えます。
ご質問は、付箋に書いていただくシステムなので、気兼ねなく、いくらでもご質問してください。
時間が足りない場合には、動画にて後日に回答します。
(以前の講演会では、回答動画は6時間を超えました。笑 )
午後からは、よりみっちりと具体例をお話します。
ご質問や悩みを伺い、それに回答する形がアドバイスをするので、より具体的な方法を聞くことができます。
僕は、普段、いろいろな戦術を使います。子どもによって使えるものは違うので、普段の講演などではあまりご紹介できないんですよね。
うまく言葉に出来ないような小さな悩みなども、ご相談していただけます。
座談会形式でおこなうので、他のかたへのアドバイスが使えることもあるし、ヒントにもなるでしょう。
僕は、関西にいることがほとんどなので、関東に行くのは年に1度くらいです。
せっかくの機会ですので、ぜひご参加お待ちしております。
[11/3 特別参加特典]
『不登校の子に出来る30のこと』
『不登校の4つの段階と関わり方』
『子どもの変化チェックポイント -ここを見よう-』
こちらをお申し込みいただいたかたに、当日お渡しします。
(動画受講のかたは、動画配信のときにお送りします)
詳しい内容などは、下記のバナーからご覧ください。
[不登校講演] 11/3『よく分かる不登校&相談会』in 東京