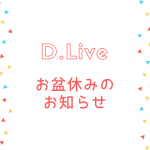こんにちは、スタッフの得津です。
D.Liveは、子ども達の居場所作りをしており、それを支える寄付を募っております。
今回、2月に行ったバレンタインチョコっと募金キャンペーンで、D.Liveに初めて寄付をしてくれた、なおさん(仮名)に改めてD.Liveの活動や寄付の使われ方についてインタビューしていただきました。
ーー今日はよろしくお願いします。わたし、D.Liveの名前は知っていたんですけど、寄付しておきながらあまり活動内容を知らなくて。まず改めてどんなことしてるか教えてください。
ありがとうございます。なかなか説明する機会もないですもんね。
D.Liveは3種類の活動をしています。
・思春期の子どもに向けた居場所作り
・不登校や思春期の子育てに悩む保護者さんに向けたイベント作りやサポート活動
・社会に向けて、D.Liveの理念や情報を発信する活動
この3つです。
ーーすごくたくさんあるんですね。社会に向けたD.Liveの理念の発信とありますが、D.Liveの理念を教えてください。
D.Liveは誰もがどんなときでも前向きに挑戦できる社会をめざしています。私たちは、今の社会は誰もが自信を失くしやすい社会だと考えています。特に子ども達は自信がないからチャレンジできない、やりたいことがあっても諦める。そんな子ども達にたくさん出会ってきました。それってすごくもったいないし、社会の損失だと思うんです。
自分は自分で大丈夫と思う気持ちや、自分を支える自信って難しい言葉で自尊感情というんですが、今の社会はこの自尊感情が下がったままになりやすい。
法人立ち上げ当時は、教育系NPOのなかで子どもの自尊感情にアプローチしているところはどこもありませんでした。だからこそ、「子どもに自信を」とキャッチコピーを掲げて活動を始めることを決めました。
ーーでは、子ども向けの居場所というのも、自分は自分で大丈夫と子ども達が思えるような居場所をされているということですか?
その通りです。現在(2020年3月時点)では、思春期の子ども達が通える3つの居場所を運営しています。
1つめは、TRY部(トライブ)。
やりたいことを叶えるための習慣づくりがコンセプトで、子ども達は一週間の生活のふり返って取り組むルーティンを決めたり、一ヶ月後に実現したいことを定めて、そのために何をするか計画を立てたりしています。
たとえば、一ヶ月後のテストで400点を取りたい子がいたら、一週間のどの時間にどんな勉強をするのか、毎日どんな勉強をどの程度するのかをTRY部のスタッフと一緒に考えます。勉強ではなく、勉強の仕方を。やりたいことの実現ではなく、やりたいことを実現する方法や習慣をTRY部では教えています。
2つめは、フリースクール昼TRY部です。
こちらは不登校の子ども達(小5〜高3)が通う教室で、学童みたいな教室です。一緒にゲームもするし、勉強もします。外遊びもするし、遠足に行ったりすることもあります。
TRY部とは全然ちがって、一緒に遊んだり楽しい時間を過ごしたりする中で子ども達は元気になって、学校に戻ったり、進路を決めたりして卒業して行きます。
最後の3つめが、TudoToko(つどとこ)です。
つどとこは草津市から委託された事業です。子ども食堂って、近年広がっているじゃないですか。あれに近い活動です。一般的な子ども食堂と違って、参加できる子ども達は市の規定(市内のひとり親家庭・不登校の家庭・生活保護世帯のみ)で決まっているのですが、毎週15名くらいの子ども達と一緒にご飯を食べたり、遊んだりしてすごしています。
どの教室でも、子ども達が学校とは違う空気感や、なんでも話せる安心感を感じてもらえるよう、定期的にスタッフやボランティアさんたちと研修やミーティングをして、教室の質を高めるようにしています。
ーー勉強ではなく勉強の仕方を教えるTRY部が個人的に一番グッときました。でも気になるのが、これらのD.Liveの活動って、どこからお金が出てるんですか?ぶっちゃけた話を聞きたいです(笑)
その質問、すごくよく聞かれます(笑)
やっぱり気になりますよね。
D.Liveの活動は事業費がほとんどです。TRY部や昼TRY部は保護者さんからお月謝をいただいていますし、つどとこは委託ですので草津市からお金をいただいております。保護者向けのイベントなどでも参加費をいただいていて、寄付は全体のうち数%ですね。
寄付を集めたり団体のファンを増したりする活動を、ファンドレイジングというんですが、ファンドレイジングを軽視しているわけではなく、単純に人手が足りないので、なかなかそちらまで手が回らないのが実情です。
ーー今回、チョコっと募金をさせてもらいましたが、D.Liveは普段から寄付を募っているんですか?
はい。モノギフト(物品寄付)、チョコっと募金のような一度きりの寄付、継続的な寄付(マンスリーサポーター)の3つがあります。
ーーそれぞれ、何に使われているか教えていただけますか。
モノギフトは教室で使う備品や消耗品を募っています。これまでに教室のスリッパや、プリンターのインク、教材用漫画、ホワイトボードマーカーなどをいただきました。子ども達といると、どうしても文房具の消費が激しいので文具の寄付は嬉しいです。
(昨年モノギフトをもらった時の写真)
チョコっと募金のような一度きりの寄付は、ボランティアさんの活動にかかる交通費と「わくわくお出かけ大作戦」の交通費に使わせていただいています。「わくわくお出かけ大作戦」は、スタッフが依頼を受けた講演先に同伴して、一緒にその地域や依頼先の課題を学ぶことです。同伴したボランティアの感想を紹介しますね。
三重県の里親研修と児童養護施設の見学に同伴させていただきました。参加されていた保護者さんは皆さん、悩みながらも明るさや責任感を持っているエネルギッシュな方ばかりで圧倒されました。 講義中、保護者さん同士で意見を交わす時間がありました。 「子どもと接するときは自分が子どもになって関わる。けど、自分が怒るときは親として怒ります。」 「子どもは大人の二面性に気づいている。子どもの前でいい顔しても、よく怒る人は自分の裏の顔を感じ取っている」 このような言葉が印象的で、自分もボランティア先の子どもに対していい面ばかりを見せようとしていたかもと思い返しました。 児童養護施設の見学では、職員さんが足りないこと、勤務時間がどうしても不規則になってしまうこと、複数の子どもたちの親になって子どもの悩みに対応することの難しさなど、これまで知らなかった施設の実情を知ることができました。 私は自分の世界を広げたくてボランティアを始めました。今回の機会はまさしくそのような機会になりました。 (大学1回生)
最後に継続的な寄付(マンスリーサポーター)は、不登校の子ども達の新しい居場所作りの積立てにさせてもらっています。実は不登校の子ども達のほとんどが、学校以外の場所に通えていません。それは、学校以外に通える場所の数が少ないからです。
都市部では、人も経営資源も多いので学校以外に通える場所の数も多いです。アクセスもしやすい。けど、私たちが活動する滋賀県の地方は本当に数が少ない。だから、ひきこもりたいわけじゃないけど、行ける場所がないから引きこもらざるを得ないなんて事例も多いです。マンスリーサポーターさんからのご支援はこの問題を解決するために使わせていただいております。
マンスリーサポーターさんには、毎月D.Liveの活動レポートを支援のお礼としてお送りしています。
ーーなるほど、ありがとうございます。では今回のチョコっと募金は、一度きりの寄付なのでボランティアさんの交通費に使われたんですか?
そうですね、交通費に使わせていただいています。今回の募金のおかげで遠方からのボランティアさんも受け入れたり、受け入れ人数を増やしたりすることができたので、本当に助かっています。
ーーもしD.Liveに寄付していくと、今後の活動でどんなことが叶いますか?
この間、フリースクールの子ども達と外遊びに行ったんです。これまでは大人の数が少なくて、行きたくても行けなかったですが、チョコっと募金のおかげでようやく実現しました。
寄付が増えていくと、こんな風に子ども達とできる活動の幅を増やしたり、先ほど話したような不登校の子どもが通える居場所を増やしたりすることができます。
これは、とある教育系NPOがされていることですが、いただいた寄付を経済的に苦しいご家庭の塾代補助に充てているそうです。私たちも、やがてはそんなことができればと思っています。
チョコっと募金をしてくださった方から、
「ボランティアさんが増えて、外遊びが実現したと知って、すごく嬉しいです。親としては、運動する機会がほしいなあといつも思っていたので。外部向けでなく、内部の子どものために募金を使われたこと、非常に納得の使いみちだと思いました。」
このような声をいただきました。D.Liveではいただいた寄付は全て子ども達や事業に使わせていただきます。
ーー事業や寄付の使われ方など、詳しいご説明をありがとうございました。最後に、D.Live的な面白さ、活動が広がるとどんな社会がつくられるのか教えていただけますか。
今までたくさん取材を受けてきましたが、ほとんどの方が聞かないような鋭い質問ですね(笑) ありがとうございます!
D.Liveが運営する教室って、どの教室もサファリパークみたいなんですよ。大人も子どもも気づけばどんどん個性的になっていく。でも衝突するわけでもない。ベタベタ引っ付くように仲がいいわけでもなく、付かず離れずの距離を保ちながら過ごしています。子ども達は、成長していないように見えるけど、ある日ガラッと変わった姿を見せます。
D.Live的な面白さってここにあって、サファリパークみたいに、のびのびとしていられることなんだと思っています。便宜上、居場所という言葉を使って事業の説明をすることが多いですが、自尊感情を育む上で本当に大切なのは「異」場所だと考えています。
つまり、学校や社会のメインストリームとは違う価値観、異なる価値観が伏流している場所。
「みんなで一致団結して運動会がんばろう!」とか、「営業ノルマ必達!」とか、学校や会社の壁に掲げられてるじゃないですか。そういうスローガンを否定する気はないですが、「かけっこだけ出たらいいよ」とか、「ノルマの3割できたら十分だからね」みたいなことを言ってもいいじゃないですか。
昔は、隣のクラスの先生とか、事務のおばちゃんがコソッと「無理しなくていいよ」と言ってくれたんですが、今の社会はそんなことを言ってくれる人が本当に少なくなりました。学校も会社も余裕がなくなったんだと思います。
となると、これらのスローガンを受ける側の子ども達や社員からすれば、スローガンや価値観に完全に合わせるか、完全に逃げてしまうかの2択しかないわけです。これが問題で、どちらに合わせても心がしんどくなってしまいます。
だから、メインストリームの価値観や評価規準とは異なる場所を作って、のびのびしたり、自分が大切にしたかった気持ち、本当はやりたかったことを考えたりする時間や機会を持ちたい。異場所があれば、メインストリームの価値観と異場所の価値観を比べたり、選んだりすることができます。
先日、フリースクールを卒業した生徒にインタビューしたら、学校では部活を頑張りたいけど、それだけじゃなくてフリースクールで出来たつながりも大事にしたいと話していました。
私たちが実現したいのは、まさにこういうことで、一つの居場所が大事なのではなく、自分が安心できる居場所をとっかかりにいくつもの関係を築いていけるようにしたい。
どんなときでも前向きに挑戦できる社会って、くじけたらピットインに戻ったり、失敗しても別の見方で評価してくれる人にアクセスしたり、誰もがこういうことができる社会なんだと思います。
ちょっと長くなってしまいましたが、D.Live的面白さや活動が広がっていくと異場所が各地にじわじわと広がっていくんだと思います。じわじわが大事です。急に広がると、D.Live的価値観に合わせるか合わせないかの2択になって、メインストリームの価値観と同じ問題が生まれてしまいますから。
これからもじわじわと活動を広げますし、D.Liveを応援してくれる人がじわじわと増えてくれると嬉しいなと思っています。
D.Liveでは活動を支えてくれるマンスリーサポーターさんや寄付を募っています!
継続的な寄付(マンスリーサポーターさん)が増えれば、不登校の子どもが通える居場所が増えます。
D.Liveのマンスリーサポーターについて、詳しくはこちらから
一度きりの寄付は、ボランティアさんの交通費と「わくわくお出かけ大作戦」に使わせていただきます。
モノギフトは子ども達と教室で使う文具や備品を募っています。
モノギフトはこちら(amazonのほしい物リストへ移動します)









![[埼玉講演の案内]もう、不登校の経験をぶっちゃけて話してやろうと思うのです。](http://www.blog.dlive.jp/wp-content/uploads/2018/07/lost-places-1549096_1920-150x150.jpg)