滋賀大学で講義をしてきました。
テーマは、『子どもとのコミュニケーションを考える』というもの。
授業させていただいたのはプロジェクト科目で、受講している学生は実習で中高生の学習支援をおこないます。2回の実習を終えて、僕の講義でした。
担当の先生には、「実習へ行っても子どもとの関わりかたで学生は戸惑ってしまう。どのように関わればいいか、また自尊感情の大切さを伝えて欲しい」というオファーをいただきました。
今まで大学に呼ばれても、基本的には講演がメイン。
活動内容や立ち上げた経緯などをお話ししていました。
今回は、「90分自由に使ってください」と、言うことだったので、授業時間すべてを使ってなにが出来るかをデザイン。
ただ「そうなんだ」と聞くだけではなく、翌週以降の実習で使える知識や機会にして欲しいと思い、授業案を考えていきました。
大切にしたのは、学生がいかに主体的になれるか。
大学の授業は、ほとんどが受け身。
でも、聞いているだけではなかなか頭には入りません。
この日、伝えたかったのは2点。
1つは、子どものやる気には、自尊感情が関係していること。
もう1つは、僕が大切にしている関わりかた。
でも、ただ単に僕が考えていることや自尊感情の知識を伝えたところで、すぐに忘れてしまいます。
そこで、より僕の話が入るように、まずは学生に考えてもらう時間を各ワークに入れました。
自尊感情の概念や構成要素の説明したあと、「どうすれば子どもの自尊感情は高まるかな?」とそれぞれがペアになって話し合う時間を設けました。
「なぜだろう?」「どうすればいいかな?」と考えたあとで、「こういう方法があります」と伝えると、ただ話をするだけのときより何倍も理解が出来ます。
授業内容
知識や枠組みの説明 →ペアワーク → 考えかたの説明
最後のペアワークは、ロールプレイング。
1人が大人役、もう1人が子ども役になって『勉強をやらせる』ワークを実施。
子ども役は、まるで子どものようにふるまいます。
「ポケモンみたいから宿題やらへん」「ゲームやりたいねん」
実際に子ども役をやることで、頭だけの理解ではなく、「ああ、こんな感じなんだな」と感じることが出来ます。
感想にも、「子どもの気持ちがわかりました」や「ゲームしたいと言われて、どのように返答したらいいか迷いました」と、具体的な疑問が出てきました。

授業の終わりには、ポストイットを模造紙に貼り、みんなでそれを見ながら解説。
わからないことなどの疑問、気づいたこと、アイデアをそれぞれ決まった色のポストイットに書くように授業が始まったときにお願いをしていました。

授業の間に解決出来た問題は端のほうに寄せ、まだ疑問になっているところを「こう思います」という感じでお話。
ここで90分が終了。
感想シートを書いてもらい、授業は終わり。

ワークショップにしたことで、学生も積極的に参加してくれ、良い学びになったのかなと思います。
なにより、「これ他でも出来るな!」という感触を得ました。
また、大学や他の場でもこのワークショップ(もう少し時間を長く)をやってみます。
受講生コメント
・子ども役をやってみて、勉強にやる気のない子はどうして勉強したいと思えないのか、相手の立場に立って考えることが出来ました。
・少し気をつけるだけで自尊感情は高められるのに、その少し気をつけるということが、大人が子どもにするのは意外と難しいのだと感じました。
子どもと関わる上で、”why?”と子どもに問いかけることを大切にしようと思いました。
・本日学んだことは、友達との間にも活きてくるかなと思いました。
・自尊感情って言われると何となく理解していましたが、今日の話を聞いてもやもやしていたものが晴れました。
子どもと接するコツを色々知れたり、ロールプレイングを通じて良いアイデアを思いつくことが出来ました。










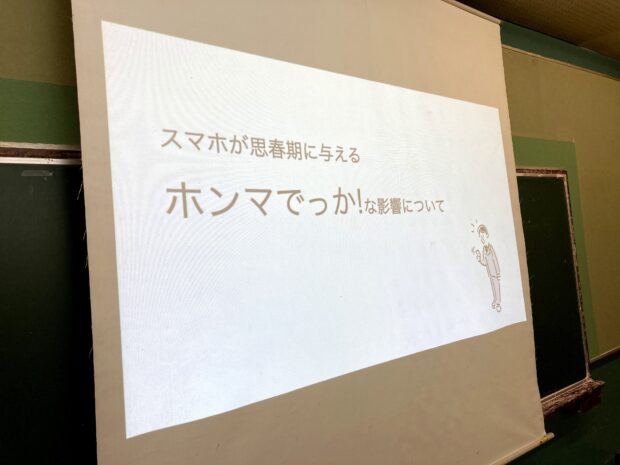
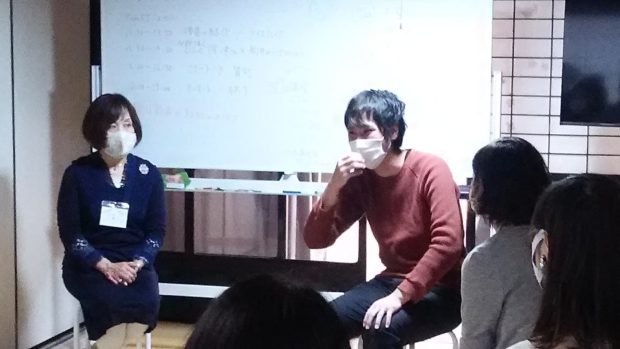




コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 「子どもとの関わりかた」について大学で講義しました。 […]