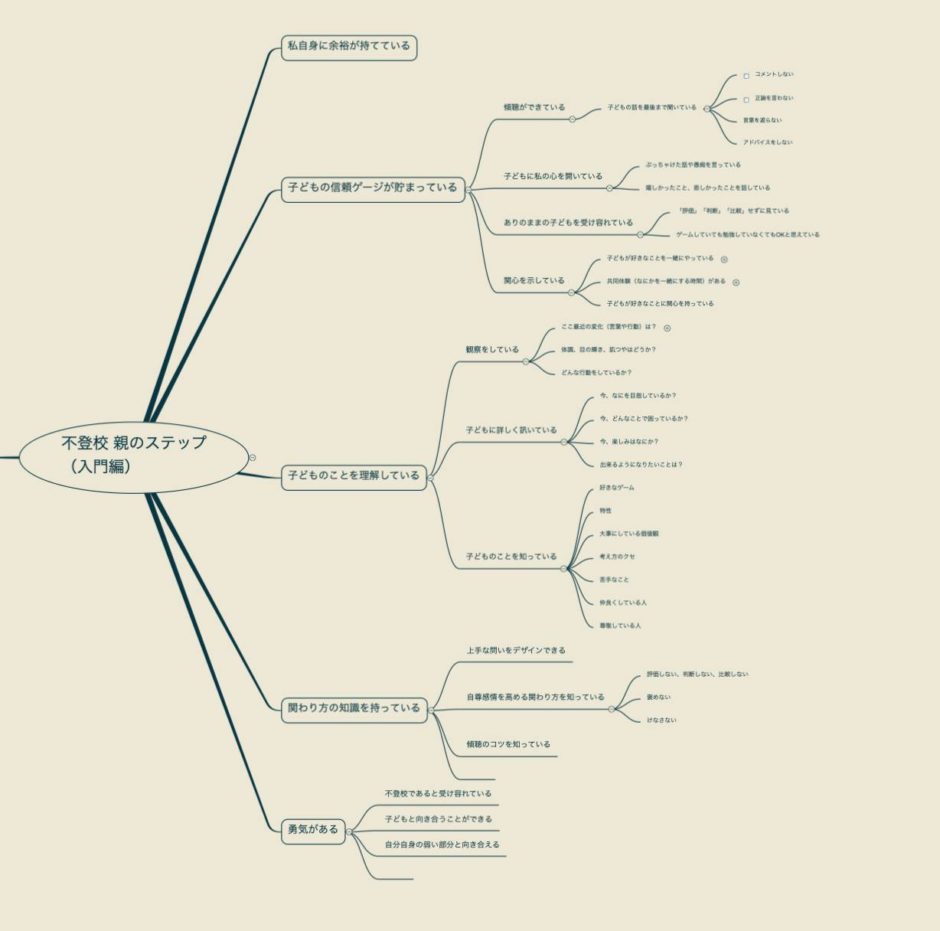コラム– category –
-

不登校のことで先生とのつきあい方や関わりが分からなくなったアナタへ
子どもが不登校になって困るのは、先生との関わり方です。学校へ復帰することも頭にいれて、先生との関係性は作っていきたい。 でも、毎日のように連絡がきたり、「今日も休みます」というのは、精神的に厳しいものがあります。 先生に「こうしてください... -

子どもを預けたいと思っても難しかった。だから自分が学んで変わることを選んだ。
「成績を上げるために塾に入れたり、仕事で帰りが遅くなるから学童に預けたりするように、不登校になってもフリースクールに子どもを預けることもできたと思うんです。でも、そうではなくて自分が不登校や人の特性について学ぼうと思ったのはどうしてなん... -

不登校の子をどうすれば元気になるか問題
なにかできないかと日頃から考えているわけでして、今は、脳科学、心理学、栄養学などの視点からいろいろ見ています。 その結果、ある程度「これが正解なんじゃないのか?」という仮説にたどり着きました。 それは、ズバリ腸内環境です。 腸と脳は、迷走神... -

コンテンツで世界は変わるんじゃないか説
講演や講座、面談で僕はことあるごとに「コンテンツに触れましょう」と言ってます。 映画、ドラマ、アニメ、マンガ、本。 良質のコンテンツとの出合いは、人生を一変する力を秘めていると思うのです。 僕が今の仕事を始めたのは、手塚治虫先生の『... -

子どもとの会話を増やすには、情報収集から始める。 問いのデザイン vol.1
この記事は、noteで公開した記事の転載になります。 コミュニケーションには、4種類あると思っています。 解決する(コンサルティング) 交渉をする(決断させる) 情報収集する(リサーチ) 相談にのる(カウンセリング) この4つのうち、一番大事なのは... -

目の前の子どもたちを心底大切にしよう、ただしそれにはまず「自分で自分のことを大切に」しよう
昨年末、僕のFacebook上でこんな記事が次々とシェアされていました。 日本中全ての大人へお願いします | 生まれてきてくれてありがとう【感謝循環型社会】 この記事を要約すると、 日本は世界的に見て人口の割合において子どもがもっとも少ない国だと自覚... -

不登校の解体新書をつくりたい。
フリースクールを始める前のこと。 まだ、不登校のことについてやっていないときのこと。 不登校については、誰かが活動をやっていて、解決策なんかもしっかり出来ているものだと思っていた。 けど、不登校の仕事をはじめてみて、それは勘違いだと気がつい... -

僕たちは、不幸な時代に生きているのかもしれない
「封建社会のほうが幸せだったのでは?」 今、受講している社会人大学の講義で教授が言った。 僕は、聞いていて「たしかにそうかもしれないな」と思った。 江戸時代は、身分は固定されていた。士農工商。受ける教育も違った。 戦争もないから、武勲をあげ... -

わたしの子どもの関わり方の履歴について
こんにちは。D.Liveスタッフの得津です。 私ごとですが、先月の今頃に義兄夫婦に子どもが産まれまして、11月頭の三連休に会いにいってきました。 まだ生後一ヶ月も経っていない赤ちゃんを抱っこさせてもらったり、ミルクをあげたりさせても... -

ときとして、子どもたちが「先生」になることだってある
僕はよく、子どもたちと関わるときに「教えてもらう」という手段を取ることがあります。 日々、弊団体D.Liveの教室や職場の学校で、小学生~高校生まで幅広い年代の子どもたちと関わっています。とくに職場では「先生」と呼ばれる、いわゆる子どもたちにな...