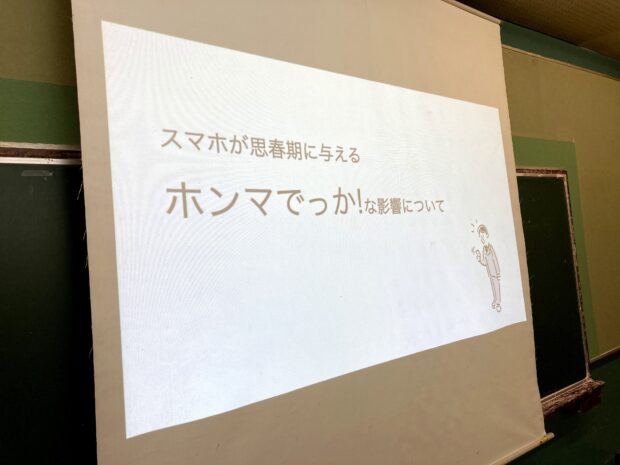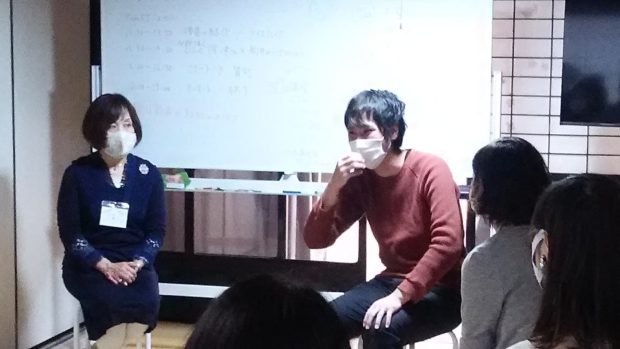「いやぁ、もうすごいんですよ!」
少し苦笑いしながら、お母さんが話してくれた。
「去年、このイベントに参加してから、何度も、何度も、話すんです。どれだけガンバったか、大変だったかを」
可愛い子には、旅をさせよ!というテーマでおこなった企画。
内容は、シンプル。
指令に書かれている物を買ってくる。

ただ、それだけ。
ただし、答えは考えても分からないものなので、道行く人たちに聞く必要がある。
近くには売っていないので、電車に乗って買いに行く。
子どもにとっては、小さな冒険。

去年、参加してくれた小学1年生の女の子は、楽しすぎたみたいで、今年も「絶対行くに決まっているやん」ということで、来てくれた。
今回は、20人近くの小学生が参加。
4チームに分かれ、そこに大人も入る。
大人(保護者)には、なにを買うのか、どこで売っているのかも伝えている。
しかし、基本的には、大人は見守るだけ。
子どもたちが冒険すると同時に、保護者の人たちは、黙って子どもを見守る訓練も兼ねている。

指令の紙を元にして、各チームは街へ繰り出す。
おろおろしてなかなか聞けないチーム。
どんどん積極的に質問をして、ヒントをもらうチーム。
「とりあえず、行ってみよう!」と言って、速攻で電車に乗るチーム。
みんなそれぞれ対応が違っておもしろい。
たった2時間のプログラム。

でも、子どもたちには大冒険。
ほとんど子どもたちだけでの行動。
一人で切符を買ったことがない子もいる。
高学年が手伝い、切符の買い方を教えてあげる。フォローをする。
帰ってきたときは、どのチームも一体感があり、すごく仲良くなっていた。
10分以上かけて行ったスーパーなのに、売っていなくて落胆したチーム。
交番へ行って教えてもらったチーム。
他にも売っているのに、わざわざ歩いて15分くらいもかかる本店まで行って商品をゲットしたチーム。
ほんと、いろんな物語があった。
子どもたちはとにかく楽しそうで、帰ってきたときには自信に満ちていた。

保護者の人が、「行くときの不安そうな顔とは打って変わって、すごく引き締まった自信溢れる顔をしていますね」と言うほど。
買ってきたお菓子をほんとうに嬉しそうに頬張る姿は、とても微笑ましかった。
戦利品のように、付いているリボンや説明書をチームメンバーで配り、それぞれが嬉しそうに持って帰っていた。
この企画、すごくおもしろい。
簡単にできて、でも子どもたちが楽しみながら、自信を得られることができる。
ぜひ、たくさんの人に試してもらいたい。
子ども会や団体などでも活用して欲しい。
下記に、簡単にやりかたを書いておくので、よかったらぜひ!


[簡単にできる ワークショップマニュアル]
1. 子どもたちが買いに行く商品を決めよう
今回は、滋賀でおこなったので、滋賀の名産品、滋賀にゆかりのあるものにしました。
どこにでも売っている物ではなく、限られた店にしか売っていないものにしましょう!
買うものは、お菓子などの食べ物が良いです。
帰ってきて、嬉しそうに食べられるのが、なによりのご褒美になります。
小学生を対象にする場合、会場の最寄り駅から2〜3駅以内に商品が売っているのがベストです。遠すぎると、時間内に帰って来られない可能性があります。
・指令の商品は、食べ物にしよう。
・買いにいく場所は、会場の最寄り駅から2〜3駅以内。
2. 指令書を作ろう!
商品を決めたら、お題になる指令書を作りましょう。この指令書は、道行く人に見せるものになります。ちょっとしたヒントをちりばめることが大切。ただし、簡単過ぎると、大人にばれるので、少し難しいくらいにしたほうが楽しいです。
・指令書は、少し難しいくらいにしよう
・ちょっとしたヒントを指令書にちりばめよう。
3. 答えをつくろう
大人には、答えと売っている場所を伝えます。
商品名、パッケージの写真、売っている場所をまとめたものを渡しましょう。
すべての答えをEvernoteにまとめて、URLだけ渡すのが簡単でオススメ!
・商品名、パッケージの写真、売っている場所をまとめよう。
・大人に渡す答え集をWordやEvernoteでつくろう。
・商品名、パッケージの写真、売っている場所をまとめよう。
・大人に渡す答え集をWordやEvernoteでつくろう。
4. ルールを決めよう!
このゲームのルールを決めましょう。
主に決めることは、「チームの人数」「予算」「大事にすること」「制限時間」です。
チームの人数は、4人〜5人くらいがオススメ。
予算は、今回は1チームあたり「1,500円」に設定しました。お土産は、だいたいその値段くらいで買えるので、この値段にしています。この金額は、買う商品によって変えてくださいね。
「大事にすること」は、”おやくそく”のようなもの。
僕は、「① たくさんの人に聞く ② 協力しよう ③ お礼を言おう」の3つを設定しました。これもイベントのコンセプトによって、ご自由に。
この企画では、とにかくたくさんのチャレンジをして欲しかったので、「どんどん聞こう!」と子どもたちに促しました。そして、チームとして協力することが大事なので、高学年には、積極的に低学年のサポートをするようにお願いしています。
制限時間は、何時までに会場へ帰ってくるのか。
時間が決まっているからこそ、ゲーム性が出ます。
今回のイベントの趣旨やルールを子どもたちに説明します。「なんだか楽しそうだぞ!」と思ってもらえると、最高ですね。だいたいどこの駅までにあるかのヒントは与えてもよいです。遠くに行きすぎると困ってしまうので。
6. [当日]チーム分けしよう!
チームを分けるとき、ただ適当に分けるとおもしろくありません。ラインナップと言って、子どもたちに順番に並ばせるゲームを僕はおこないます。たとえば、誕生日順など。何度かやって、慣れてきたところで、「では、声に出さずにやって」と言って、学年順に並んでもらいます。
並び終えると、前から「いち、に〜、さん〜」と、数字を割り振り、チームに分けます。こうすると、自然に同じ学年はばらけ、バランスのよいチームがつくれます。
7. [当日]チームリーダーを決めて、大人も割り振ろう
保護者や大人もグループに参加。できれば、自分の子どもがいないチームに参加するのがオススメです。我が子がいると、どうても口を出したくなってしまうので。
チームリーダーは、高学年から選出。リーダーには、予算の管理をしてもらいます。初めて同士の場合は、チーム内で自己紹介をしましょう。
・大人をチームに割り振ろう
指令書は、チームリーダーに出てきてもらい、ジャンケンで買ったチームから、好きな司令を選んでもらいました。ここは、ランダムでもおもしろいと思います。
9. [当日]大人に説明しよう
大人たちに、答えと販売場所などを提示します。ヒントを出すタイミングやヒントを与えるかどうかは、各グループの大人たちに任せてください。
チームリーダーに予算を渡せば、準備おっけー。いざ、出発。どこへ行くのかは、各グループにおませか。
11. 早く終わったチームには追加指令も
もし、思いのほか早く終わってしまったチームには、追加指令を与えてもオッケーです。比較的簡単にできる、近くで変える指令が楽しいですね。
12. [ゴールのあと]戦利品を食べよう
せっかく、自分たちで手に入れたお菓子。チームで一緒に美味しく味わおう。手を洗うのを忘れずに!
他のチームがどんなお題で、どんなことがあったのか知りたいですよね? 各グループに、どんなことがあったのか。なにが大変だったのか、発表してもらいましょう!
・各グループで、「楽しかったこと」「大変だったこと」を発表
【まとめ】
お題を考えるのが一番難しいです。良さそうな品を見つけ、指令書を作る。適切な難易度(難しすぎず、簡単すぎず)なのが良いです。大人なら、多くの人が知っているようなもので、少し指令書を難しくするのが良いかもしれませんね。
もし、実際にためされたかたは、どんな様子だったのか、ぜひ教えてくださいね。