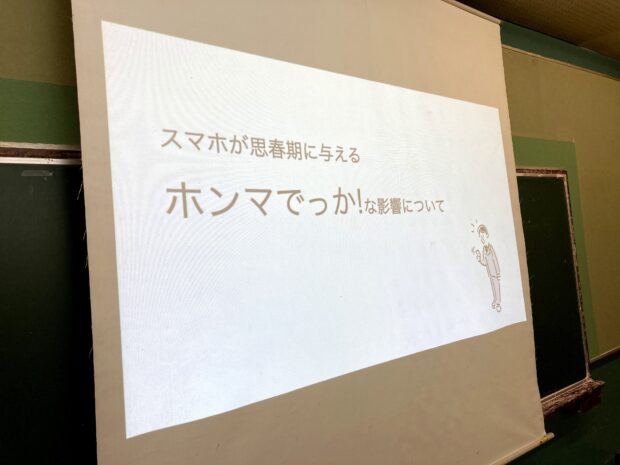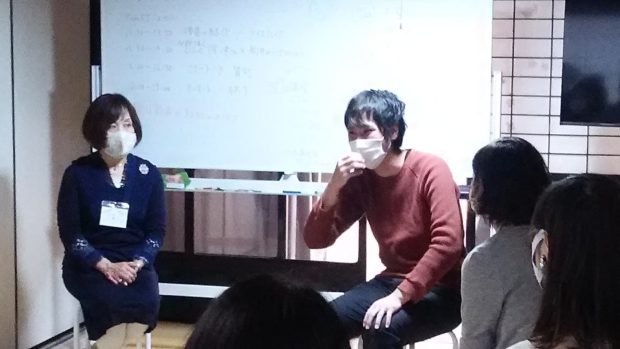こんにちは。
D.Liveスタッフの得津です。
1月21日(火)に宇治市莵道小学校育友会(PTAのことです)さまにお声がけいただき、「子どもたちが自信を持って生きていくために 〜保護者の立場でできること〜」というテーマで講演させていただきました。
昨年(2019年)6月、山城教育局主催のHUGフォーラムで私が講演したときにご参加くださった方からのプッシュがあって実現した機会です。授業参観でもない、平日お昼からの講演でしたので、5人くらい来たら良い方だよなぁと思っていたら30名ほどの保護者さんに来ていただきました。
「子どもはもう高学年なのに、親の私に寄ってくることが結構あります。高学年だからと思わず、そのまま受けて止めてやればいいんだと、お話を聞いて思いました。」
「子どもたちの話を遮らず最後まで聞いてやることの大切さ、言葉にすることを支援して、消化していく機会を与えることなど、何度聞いても心にしみる話をありがとうございます。」
「付き合い程度の気持ちで、全く期待せずに参加していました。ですが、実際には大変興味深く聞かせていただきました。HSP(他人よりも刺激に敏感な性質)や、『ほめる必要はない』とおっしゃっていたのも、印象的でした。すごく感銘受けました。」
当日、お越しくださった方々からはこのような感想をいただきました。
小学校時代、特に低学年は保護者や先生などの近しい大人からの、包み込まれている、目をかけてくれているという実感が、子どもの自信や自尊感情を育てる上では重要です。そのような実感を子どもが感じられるための関わりの一つとして、子どもの関心に関心を持つことの大切さをお話しました。
子どもの関心に関心を持つことについてお話している中で、「運ゲー・ガチャ」「陽キャ・陰キャ」「リア充・非リア」、子ども達がこういう言葉を使って生活や関係性を認識していること知っているかお尋ねしました。
ほとんどの保護者さんがこのような言葉を知らず、会としても一番熱を帯びていたトピックでしたので、子どもが使う言葉と関係の切り取り方について、講演でお話したことをこの記事にも書きます。
「運ゲー・ガチャ」
「陽キャ・陰キャ」
「リア充・非リア」
これらはオンラインやスマホゲーム、SNS、つまりはネット上で生まれ、子どもたちに浸透している言葉です。少しだけ意味を紹介しますと、こんな感じです。
「運ゲー」は、プレイヤーの腕前がゲームの勝敗や結果に殆ど結びつかず、ランダム要素、すなわち運の要素が強いゲームのこと。
「ガチャ」は、ゲームで使うキャラを引くことです。昔、駄菓子屋やゲームセンターで、カードや人形を引き当てるガチャガチャって、ありませんでしたか。要はあれと同じです。ガチャガチャと同じく、レアリティの高いキャラは当たる確率がとても低く、課金の主な原因になっています。
「陽キャ・陰キャ」は、それぞれ陽気なキャラクター、陰気なキャラクターを略した言葉です。
「リア充・非リア」は、リアル(現実)の生活が充実している人のことと、その反対を表す言葉です。
「陽キャ・陰キャ」と「リア充・非リア」は、学校やクラスにおける自分の立ち位置を示す言葉として使われています。
他にも、面白いを「草生える」「ワロタ」と表現したり、実生活で使われているネット・オンライン用語をあげればキリがありません。
問題なのは、ネット上でこれらの表現を知った子たちや、それを友だちから教えてもらった子たちが、自ら進んでこれらの言葉で自分を規定し、言葉に沿った振る舞いをすること。そして、私たち大人が知っておくべきなのは、これらの言葉が子どもたちにとってはオンラインの世界の言葉ではなく、実生活と地続きの言葉になっているということです。
まず、子どもたちが自ら進んで「陽キャ・陰キャ」などの言葉で自分を規定し、言葉に沿った振る舞いをすることについてご説明します。
思春期になると発達段階としても、子ども達は自分と相手の違いを認識したり、相手と比べたりする中で自分という存在を理解するようになります。
新しいクラスになって一ヶ月もすれば、もうクラスでの自分の位置付けなんて完了しています。早いですよ、子ども達がお互いを参照する早さは。
「あの子は派手そうだし、仲良くなれなさそうかな。この中では一番陽キャっぽいな。」
「この人と仲良くしてみたいけれど、陰キャと思われるのは嫌だな。どうしようかな。」
なんて算段をつけながら、自分はこのクラスにおいて陽キャなのか、それとも陰キャなのかを、お互いに判断しあい、そのキャラクターらしく振る舞うようになります。「陽キャ・陰キャ」という言葉は使わなくても、上・中・下くらいの判断はしています。
D.Liveで関わっている中学生女子が以前、自分のことをこんな風に言っていました。
「クラスが始まって最初の方は上のグループにいたけど、ハブられて下のグループになったことがある。でも、今は中くらいのポジションにいるかな。だから、楽しくしてるけどあまり目立たないようにしてる。」
普段使いの言葉が、クラスにおける自分の立ち位置を規定し、振る舞いを決めることを、彼女の言ったことが見事にあらわしています。
使う言葉が自分の振る舞いを変えることって、皆さんの経験でもありませんか?
英語圏の国に海外旅行へいって、たどたどしいなりに英語で会話していると、慣れてきた頃には現地の人のように「a-han」とか、「ya」とか言ってる自分がいたり。あるいは、外国からきた人が日本語を勉強し、会話する中で、おじぎや会釈を身につけたり。
言葉には自分の振る舞いや世界の切り取り方を変える力があります。ある部族を研究しようとしている文化人類学者がいたとして、その学者が研究対象の部族の言葉を研究しないなんてあり得ないですよね。相手を知るには、相手が使っている言葉、慣れ親しんでいる言葉を知る必要があります。
さらに大人が知っておくべきは、これまで紹介したネット上で使われている言葉は、子ども達にとっては実生活で見聞きする言葉だということです。
どういうことかと申しますと、私たち大人(といっても平成一桁生まれより上の世代)にとっては、ネットの世界での出来事は、あくまでネットの世界のこととして理解しています。ハンバーガーはアメリカ由来ものだし、クリスマスはキリスト教からきた文化だし、旧正月は中華圏では最も重要な祝祭ごとだと知っています。これらを日本の文化や土着の文化だとは思いません。
同じように、ネットの世界と実生活の世界を分けて私たちは理解しています。虚構と現実とか、オンラインとオフラインとか、リアルとインターネット上だとか、そういう言い方で2つに世界を分けています。
しかし、デジタルネイティブの世代にとってはオンラインとオフラインの区別が私たちの世代よりもずっとゆるやかになっています。私たちが子どもの頃は、放課後になると、遊びや習い事の時間、夕食の時間、宿題の時間など、友達と過ごす時間、家族と過ごす時間、一人でいる時間がきっぱりと分かれていました。
一方、いまの子ども達は、スマホをはじめとするインターネットを利用できるデバイスの台頭によって、全ての時間がクラスの友だちと繋がれる時間になり、それが当たり前という感覚です。
つまり、いつでも「陽キャ・陰キャ」、「リア充・非リア」、「上・中・下」で自分を規定される世界にアクセスできるということです。
このような分かりやすい分け方をされる世界にいつでもアクセスできることが望ましいことなら良かったのですが、残念ながらそんなことはありません。
「本当はやりたいことがあるのに、陰キャだから目立つようなことはやめておこう」
「あの子と仲良くなりたいけれど、今のグループの子達とは毛色が違うし、話しかけたらグループの子になんて言われるかな。怖いな。」
こんな心理がどうしたって働きます。
このように自分の心にブレーキをかけて、周りの目に合わせて行動することが、その子の自尊感情や成長の機会を損なうことは想像にかたくありません。
では、保護者の立場として何ができるのでしょう。
1つは丁寧な言葉を使うことです。家庭の中で丁寧な言葉を使うことで、ネットはネット、学校は学校、家は家と文化圏が違うことを言葉遣いを通して教えることです。実生活とネットの世界の区別がゆるやかになったとはいえ、まだ完全に溶け合っているわけではありません。子ども達だって、なんとなく世界が違うことはそれとなく分かっています。だから、言葉遣いでその境界をはっきりさせるんです。
違う文化圏、違う価値観の居場所があることは子どもにとって、ありがたいことです。D.Liveではフリースクールを経営しています。クラスに馴染めず大人しいと思われていた子が、フリースクールではすごく大きな声で笑っていて、クラスでの姿と全然違うことがよくあります。
それは、その子にとってクラスの文化が、話されている言葉が、世界の区切り方が合わなかっただけです。自分に合う居場所があれば、誰だって楽しく過ごせますし、自尊感情も健やかに育っていきます。
ですから、保護者の皆さまにはぜひとも丁寧な言葉を使って欲しいのです。
「陽キャ・陰キャ」、「リア充・非リア」、「上・中・下」
こんな分かりやすい、二項対立的な言葉だけでお子さんのことを表しきれるでしょうか。当然できないですよね。丁寧な言葉を使うというのは、敬語で話すとか、難しい言葉を使うとか、そういうことじゃありません。具体的に表現してほしいのです。
面白いことがあれば、「あのときこんなこと言ってたのが可笑しかったね。」
ムカつくことがあれば、「○○ちゃんにイジワル言われて、嫌だったんだね。」
元気付けてほしそうなときは、「覚えてる?○○があったとき、こんな風にして努力してたよね。他にも、こんなことがあったじゃない。」
なんて、具体的にあったことを、事実を話していくだけで子ども達は嬉しいし、安心します。やっぱりお母さんは私のことを分かってくれてるんだな、先生は自分のことを見てくれているんだなと思うんです。
無理に褒める必要はどこにもありません。自尊感情は、目の前の子どもの具体的な事実や姿を語る中にこそあるんです。
長くなりましたが、その一歩としてまずは子どもの関心に関心を持ってください。子どもが使っている言葉を知ってください。
D.Liveでは、子育てや教育についての講演・研修をおこなっています。