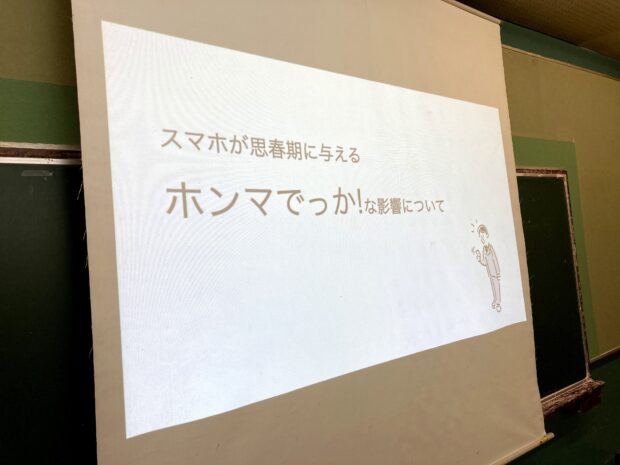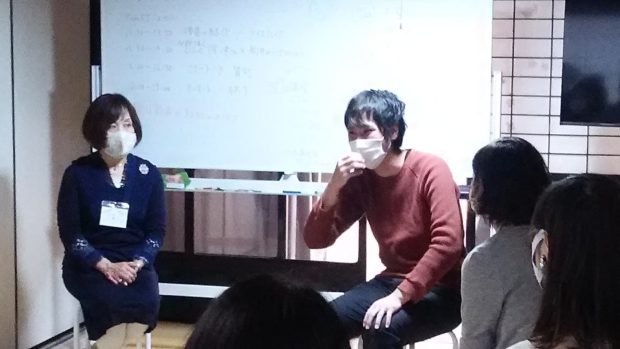こんにちは。
D.Liveスタッフの得津です。先日の5月30日(木)に、草津市の民生委員・児童委員さまに向けて傾聴をテーマにした研修をおこないました。
会場には仕事でお世話になっている方もいて、日頃の恩返しの気持ちで私たちD.Liveのスタッフが相手の話を聞くときに気をつけていることをお伝えしました。今日は、研修で話したことをみなさんにもご紹介します。
話したことは大きく二つです。
1、はじめて出会った相手に信頼してもらうためにできること
2、話を聞くときに心がけていること
1、はじめて出会った相手に信頼してもらうためにできること
常日頃、思っているのですが私たちD.Liveや民生委員・児童委員さんなどの、地域で困りごとをキャッチアップする存在って全然認知されていません。恥ずかしい話ですが、ぼくも仕事を通してはじめて民生委員・児童委員さんの役割を知りました。
私の場合だと、子どもの頃から関わる機会がなかったんですよね。親や祖父母も担当していませんでした。だから本当に知る機会がありませんでした。私みたいな人って珍しくなくて、きっと若い子育て世代のほとんどが同じじゃないでしょうか。子どもができて初めて民生委員・児童委員さんを知るんだと思います。
そうなると、民生委員・児童委員さんがせっかくお家を訪問しても「誰ですか?」となってしまいます。
ですので、初めて訪問されたご家庭には自己紹介をすること、しかも例えを入れて紹介することをお伝えしました。私たちD.Liveの場合ですと、「思春期の子どもの通訳みたいな存在です」という言い方をすることがあります。
相手が知ってそうな職業や人に例えて民生委員・児童委員の仕事を伝えると、相手もイメージがしやすいので民生委員・児童委員がどんな存在か分かってもらいやすくなると考えます。
(当日のスライドより)
次に、相談内容を引き出すためにまずはこちらから自己開示をすることを話しました。
民生委員・児童委員さんの側からすると、普段の困りごとを聞きたいと思って「最近どうですか?」と尋ねたとしても、相手からすれば「初めて出会う相手に何を話せばいいんだろう。どんなことを話せばいいんだろう」と悩んでしまいます。
こうならないためにも、自分から話題を出すのが良いです。
例えば、
「自分が子育てしていたときは、どんなところに相談すれば良いのか分からなかったし、子育てセンターはどんな相談を受け付けてくれるのかもわかりませんでした。そんな相談先についてのお困りごとはありますか?」
こう切り出してもらえると、相手は相談先についての困りごとを聞いているのかと分かります。初対面の人と話す場面では特にそうですが、相手は自分が切り出した話題に近いことを話します。自分が出した話題が、この場でのコミュニケーションにおけるお手本になるイメージです。
会話の呼び水としての自己開示です。もちろん、いきなりヘビーな話題を出されると相手も困りますから、民生委員・児童委員としてよく聞く相談内容を例に出すもの1つです。
(当日のスライドより)
2、話を聞くときに心がけていること
初めて会う人と会話ができる雰囲気になったら次は具体的に困りごとを聞いていく場面です。この時間は、普段からボランティアさんにも話している傾聴のコツと質問の作りかたについて話しました。
●傾聴のコツ
1:話すことよりも聞くことに時間を割く
2:視線をあわせる
3:タイミングよくうなずいたり、相づちをうつ
4:相手の考えを先読みしない
5:話を遮らない
6:自分の考えを押し付けない
7:相手の話の内容や考えを否定しない
引用・参考 : 「実は知らない傾聴の本質・効果・スキルUP法 ~傾聴チェックリスト付!~」
すでに勉強している人からすると、これといって目新しい内容ではありませんが私たちの現場での例を出しながら説明いたしました。
●質問の作りかたについて
先ほども言いましたが、生活の困りごとを聞くつもりで「最近どうですか?」と尋ねても相手は何を答えたら良いのか悩んでしまいます。家族のこと、仕事のこと、近所づきあいのことなど、なにを答えてもOKじゃないですか、この質問だと。相手にしてみれば、考える幅が広すぎて言葉に詰まってしまいます。
すでに定期的に会っている人ならこの質問でも問題ありませんが、初対面の人にはこの質問は避けたほうがいいです。私たちが保護者さんやお子さんと初めての面談をするときは答えやすい質問から始めるようにしています。
(例)不登校に悩む保護者さんと話すとき
1、どれくらい学校を休んでいるんでしょう? (日数を答えるだけでいい質問)
2、お子さんは学校が好きですか? (イエス、ノー、分からない、の3択で選べる質問)
3、お子さんが学校に行けない理由はなんでしょう? (どんな答えもありえる質問)
4、お母さんはどうなってほしいですか? (どんな答えもありえる質問)
「最近どうですか?」のような、どんな答えもありえる質問はだいたい3回目に質問を目安に投げかけるようにしています。
yes/noで答えられる簡単な質問から、どんな答えでもありえるような質問に切り替えるのは、質問する側の気持ちの面としてもちょっと難しいところはありますが、相手の話をていねいに聴こうという気持ちで臨めば意外とスムーズに進みます。
研修では、これらの話をした後に練習する時間をとりました。普段の研修では、参加された方々がペアで話しあう機会がないと聞いていましたので、どうなるかドキドキしましたが皆さん積極的に練習に参加していただきました。
研修後も個別に、「こんな場面ではどんな風に話を聞けば良いですか?」という質問をいくつかいただきました。参加された皆様の関心の高さが伝わってくる研修でした。