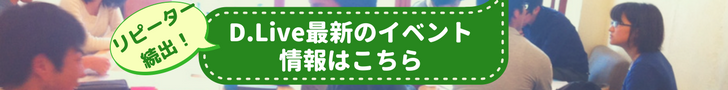こんにちは。
D.Liveスタッフの得津です。
昨日、「不登校の子どもはなぜ朝起きられないのか」というテーマで講座をおこないました。
どうして夜遅くまでゲームをしてしまうのか。
朝起きる理由があれば子どもは起きられるのか。
不登校になってからどうしても朝に起きられない子どもの心理を、スタッフの山本が実体験や参考資料を元に話しました。
その講座に参加されたお一人が「いつまでも子どもがこのままなんじゃないかと思って不安になるんです」と話してくださいました。
子どもが不登校になるなんて思わなかったでしょうし、自分自身も不登校になったことがあるわけじゃない。だから、子どもにどうしていけばいいか分からないし、好転しそうもない毎日に不安になる。そのお気持ちに他の保護者さんもその方の言葉に深く共感されていました。
何も変わらないなんてことはないでしょうし、それも頭ではわかっているんだけど不安な気持ちもあるというのが実際のところだと思います。
では、不安な気持ちとどう付き合っていけばいいのでしょうか。
そのヒントが論語にあると、先日私がたまたま参加した会で気づきました。
論語とは、中国の思想家である孔子の言葉を弟子達がまとめた書物のことです。
この論語について、能楽師の安田登さんが「身体感覚で『論語』を読みなおす。―古代中国の文字から―」という本を出版されました。先日、その出版記念イベントで安田さんが話されていたことをご紹介いたします。
論語の一番はじめにこんな言葉があります。
「子曰、學而時習之、不亦説乎」
子曰く、学びて時に之(これ)を習ふ。
亦(また)説(よろこ)ばしからずや。
学ぶことの悦びをといた言葉です。教科書にもよく載っているので、覚えている方もおられるかも知れません。
この漢文を訳すときに、「而」という字は意味がない置き字だと学校で教えられることが多いと安田先生はおっしゃっていました。今の学校ではどうか分かりませんが、少なくとも私は先生のおっしゃるように、置き字は訳さないと習ったことを覚えています。
しかし、2500年以上伝え続けられてきた言葉に無駄な字があるだろうか。
いや、ありはしないというところから安田先生の「而」についての考えが説明されます。
人の成長というのは時間の経過に沿って右肩上がりに成長していくものだと考えられがちです。
しかし実際はそんなことありません。長く出来ない時間が続いて、ある日突然できるようになります。乳児や幼児の成長を思い出してください。ある日突然つかまり立ちができるようになったり、「ママ」と喃語を話せるようになったり、走ったりすることができるようになったりしたと思います。これは乳幼児に限ったことではありません。成人した私たちも同じです。
人の脳というのは思った以上にデジタルで、できない時間のほんの小さな変化を感じ取ることはできないと安田先生はおっしゃいます。しかし、確かに小さな変化は存在する。この、できるようになるまでの時間感覚を表したのが「而」ではないかというのが安田先生の考えです。
この話を聞いた時、真っ先に不登校の子のことが浮かびました。
一見すると確かに何も変わっていないように見えます。
夜遅くまでゲームしてるし、学校のことどうするか聞いても答えない。
そんな状態を見ていたら親としては不安でいっぱいになります。
ただ、実は子ども自身もストレスフルな「而」の時間にあると思うんです。
だからこそ、子どもが「而」の時間から抜け出た時に必要な手助けができる備えを、「而」の時間に子どもがあるうちにしておくことが不安との付き合い方ではないでしょうか。