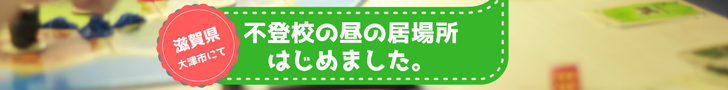9月18日の今日。
不登校の生徒が通う教室「昼TRY部」での出来事。
ぼくたちはカードゲームをしていた。
祝日だからか、人数が少なかった。
せっかくだからと、大人も子どもも一緒になってカードゲームに夢中になっていた。
たわいもない話をしながら。
冗談を言いながら。
笑い合いながらカードゲームを進めていた時にそれは起こった。
もしかしたら、言うつもりのなかった言葉かもしれない。
ポロっと口をついて出た言葉かもしれない。
けど、たしかに中学生の彼は言った。
まるで日常会話のように。
さっきまで話してた冗談の続きのように。
好きな食べ物でも話す時のようにスラスラと言ってのけたのだ。
「おれ、小学校のときいじめられたことあるわ。松ぼっくりとか投げられた。はは(笑)」
気を抜いたら、完全に取りこぼしてしまいそうなくらい自然に出た言葉だった。
ここで話を止めたらきっと彼はいやがる。
ぼくは、話を止めずにカードゲームを続けることにした。
話を聞きながら、ぼくは彼の流れるような自己開示にただただ感服していた。
当然だけど、いじめられることはとても辛い。
いじめの内容も辛いが、いじめられたという事実そのものが子どもの心に深く重くのしかかる。
いじめられたことでさらに自分で自分を傷つけることだってある。
こんな具合に。
「自分はいじめられた人間なんだ。よくないとさんざん学校で言われてきたいじめに遭ってしまった。きっとお母さんをいやな気持ちにさせてしまう。なんてことだ。」
だから、この手のカミングアウトは勇気がいる。
話すことで、その時のことを思い出して辛くなることもある。
自分が、周りから「いじめられる弱い立場の人間なんです」と
思われるんじゃないかという不安がよぎることもある。
それでも彼は笑い飛ばして言えたのだ。
ぼくは彼を尊敬した。
今日はたまたま不登校の生徒たちの居場所での出来事だった。
だが、このような不意におとずれる生徒の自己開示は、実はよくある。
この瞬間をぼくは絶対に逃さない。
この自己開示をきちんと受け止めて聞くことが、生徒とぼくとの信頼関係をつくることになる。
信頼関係が強くなればなるほど、ぼくがいる居場所を好きになる。安心して通うになる。
安心感が生まれれば、その場所でやりたいことが芽生えてくる。やりたいことが生まれれば、それが学校復帰や進学の意欲につながる。
だからぼくはこの瞬間を絶対に逃さない。
一緒にいた学生ボランティアさんが、この日の帰りに
「不登校の子どもっていっても、普通の子と変わらないんですね。少しおどろきました。」
と言っていた。
間違ってはいないが、生徒たちへの理解が足りない。
この日はじめてきた学生さんだったので、たしなめることはしなかったが「普通の子と変わらない」わけはない。
たとえば、小学校の頃にいじめられたと話した中学生の彼。
彼は、ぼくの教室ではよくしゃべる。
好き嫌いのはっきりした性格なので、ぼくが用意した課題が気に入らなかったら「やりたくない」と言う。
同じ教室に通う他の生徒にも遠慮はしない。
言葉がきついこともあるので、「怖い子。嫌なことを言う子」と誤解されるかもしれないが、根は優しいし友だちと仲良くなっていくことが大好きな生徒だ。
よく話す部分だけを見れば、学生さんのように「普通の子と変わらない」と思うかもしれない。
しかし、そんなことはない。
今日、彼が話してくれたようにいじめという辛い経験もしてきている。
彼だけじゃない。
他の生徒だってそうだ。彼らなりにイヤな経験や、辛い経験をして今がある。
笑っていられる。
一緒にカードゲームもできる。
彼らのそんな姿を見ると、ぼくは草木の育ちを思い出す。
まっすぐ育った草木が風雨で折れたり曲がったりすると、折れたところから新しい芽が出たり、曲がったところが太くなったりする。草木についた傷が、自分自身をたくましくするのだ。
まるで生徒たちと同じじゃないか。
辛い経験が自分をより強くする。
しかし、今を生きる子どもたちにはとって、自分をたくましくする風雨が強すぎるんじゃないだろうか。
いじめられて学校にいけなくなってしまった。
大好きな部活がうまくいかなくて居場所がない。
友だちにいつもからかわれているような気がしてスマホを離せない。
生徒の話を聞くたびに、子どもたちだけではどうしようもないことが多いことに気づかされる。
声を上げないだけで、困っている子どもはたくさんいる。
自分で立ち上がれないくらい辛い経験をした子どもに必要なのは添え木だ。
折れた草木に支えてこれ以上傷つかないようにし、養分を与える添え木。
ぼくは子どもにとっての添え木でいい。
自分だけじゃ抱えられないことを一緒に抱えて、立ち直る力を与える添え木。
自分だけで何ともならないことで困っている子どもたちにとって必要なこと。
それは寄り添い支える添え木と、添え木に出会える居場所なんじゃないだろうか。