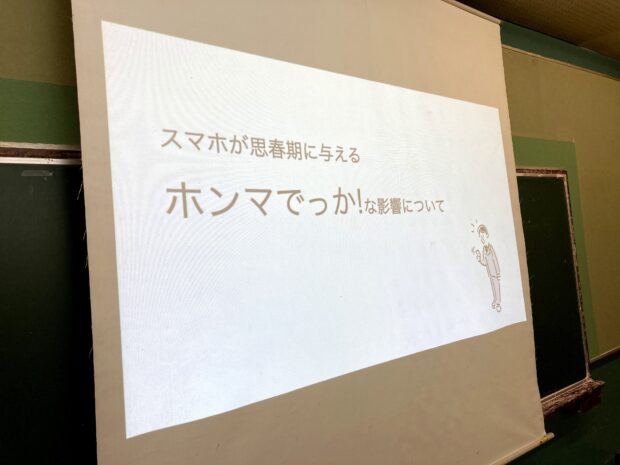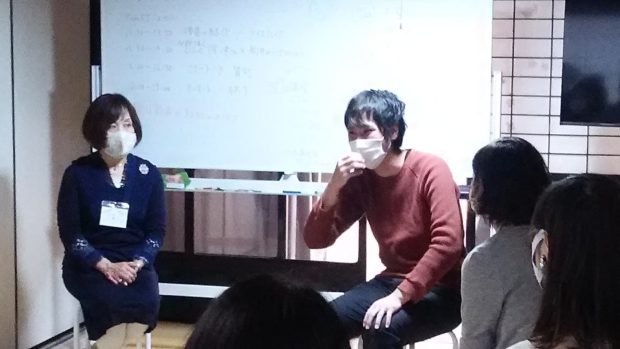7月29日(日)に、不登校のおはなし会in滋賀を開催しました。
京都で不登校のおはなし会を開かれている「学び舎 傍楽」の駒井さんをゲストにむかえ、駒井さんのお子さんが不登校になったときの体験談を語ってもらったり、参加者同士で話したいことをグループで話したり。あっという間の2時間でした。
愛知県や兵庫県から参加されるかたもおられ、本当に嬉しい限りです。
長くて暗いトンネルにいる気持ちだったけど、今は子どもが不登校になってよかったと胸を張って言える
「お姉ちゃんのほうが不登校になったときは、本当になんでかわからなかったですね」
お子さん二人のうち、お姉ちゃんが不登校になったときのことを駒井さんはこう語っていました。理由がわからなかったので、本当に青天の霹靂だったそうです。どうしていいかわからず、当時は無理やり学校に連れて行くこともしょっちゅうだったそうです。
「今となっては良くなかったと分かりますが、ついやってしまいましたね。」
お姉ちゃんとの綱引きをしてるうちに、弟さんのほうも不登校になり、どうしていいかわからなかった駒井さんの救いになったのは同じ立場のお母さんでした。
すがるように参加した不登校の親の会で、子どもの不登校を先に経験した先パイから「5、6年ずっとやで」と言われた時は、そんなに付き合っていかないといけないのかと思ったそうです。しかし、それからは子どもをなんとかしようとしなくなったそうです。
「親の会にいくようになってから、子どもとの関係も変わって来ましたね。ようやく子どもが自分の気持ちを話してくれるようになりました。」
今ではお子さんは二人とも社会人で立派に活躍しているそうです。不登校で悩むお母さんたちに、駒井さんは言います。
「きっと、長く暗いトンネルにいるような気持ちだと思います。私もそうでした。でも、私は子どもが不登校になってよかったと思います。だからこそ気づけることもたくさんありました。みなさんにとっても、そうであってほしいです。」
何かしてあげたい気持ちを、ぼくたちはどう飼いならしていくのか
アンケートで、「イベントに参加される前、どんなことでお悩みでしたか?」と聞いたところ
・不登校のうけとめかた
・子どもとの関わり方
・今、何をしてあげられるか
などがありました。
保護者さんの何かしてあげたい気持ちがあって参加されたことが伝わってきます。
しかし、子どもに対して何かしようという気持ちが強すぎると、どうやらよくないということが駒井さんの話から分かります。駒井さんのお話の後、参加者同士で交流の時間をとりました。そこでも、何かしたくなる自分とどう付き合っていくかが話の中心だったように感じます。
親ですから、当然何かしたくなります。
勉強や進路だってすごく心配です。でも、ここで手を焼きすぎると子どもの気持ちが離れていくかもしれません。
かつて、京都で活躍する庭師さんを呼んで子育てについて考える会をしました。その時に庭師さんが、草木を育てるためにギリギリまでほったらかしにするとおっしゃっていました。枯れそうになるギリギリのときに水をあげると、その草木はたくましく育つそうです。
逆に水をやりすぎるとダメになることもあるし、なんだかひ弱な草木になることもあるそうです。
子どもの関わりについても、まったく同じだなと思います。
どこで手をかけるべきか、その見極めはすごく難しいですが「何かしてあげたい気持ち」にちょっと待ったをかけて、気持ちを飼いならすことも必要だと私は感じます。
やり場のない気持ちは、駒井さんのように不登校を話せる会に顔を出したり、リフレッシュに出かけたりすることに向けてはいかがでしょう。親御さんが外に出ることは、不登校のお子さんにとってもいいんですよ。
イベント後の感想
最後に、参加されたかたの感想をいくつかご紹介いたします。
「子どもに”やらない”選択肢や、毎日の小さなミッションを与えること、昼間の外出をゆるすことを知れてよかったです。」 (N・Kさん)
「参加されたみなさんがとても明るかった事といろんな方の意見が聞けたことがよかったです。」(M・Iさん)
「参加者同士でいっぱい話せて楽しかったです!”やらなくていい”選択肢をつくりたいと思います」(A・Oさん)
「体験談など、どうしたらいいかわからなかった話が聞けたので、来てよかったです。また、同じ立場の方と交流できてよかったです。」(R・Nさん)
今後の「不登校のおはなし会in滋賀」の開催日時はカテゴリーの「イベント情報」からご確認ください。