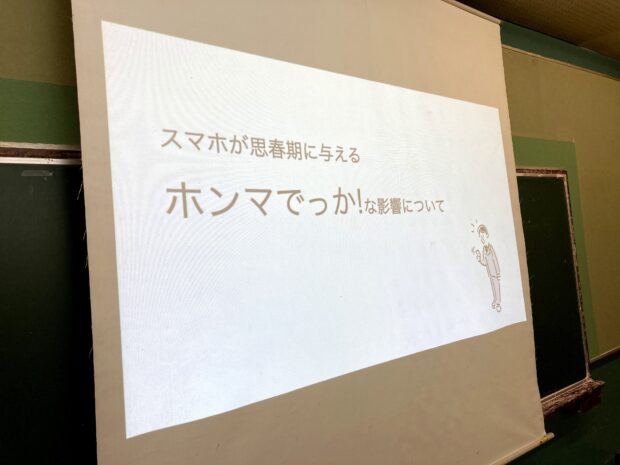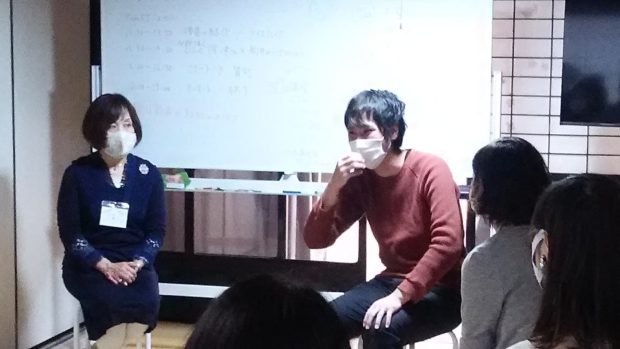先日、草津小学校のPTAにて講演をおこないました。
テーマは、『子どもの自尊感情と自信を持たせる方法』です。
今回は、物語、創作を交えながら、どんなことを話したのかをご紹介します。

講演が終わり、陽子は学校を出て、車に乗り込んだ。
今まで、子育てに関する講演は、いくつか聞いたことがある。
しかし、今日はこれまで聞いたものとは違った。
「すぐ使える方法を今日は、お伝えします」と、講師の田中さんは言っていた。
その言葉どおり、「これやってみたい」と思うことが、たくさんあった。
陽子には、2人の子どもがいる。
小学5年生になる葵(あおい)は、しっかりしているものの、大人しい子。
外で遊ぶよりも、家で本を読むのが好きだ。
小学2年生の颯太(そうた)は、やんちゃな男の子。
スポーツ少年団に入って、サッカーをしている。

子育ては、大変だ。
平日、陽子は市内にある大型ショッピングモールにあるカフェで、週4日パートをしている。
勤務時間は、10時から14時まで。
仕事が終わると、モール内にあるスーパーで買い物をして、家に帰る。
帰宅し、少し落ち着こうと思ったら、すぐに子どもたちが帰ってくる時間になる。
長女の葵は、もうすぐ思春期に入る。
今はまだ学校であったことをなんでも話してくれるけれど、だんだん話してくれなくなるのかと思うと、不安になる。
颯太は、運動が得意だけれど、勉強は苦手だ。
これから算数も難しくなってくる。
「大丈夫?」と、心配になって、いつも「早く宿題しなさい」と怒鳴ってしまう。
2人とも、優しくて良い子だけれど、自主性がなくて少し心配していた。
葵は、言ったら手伝ってくれることもあるけれど、自分から動くことはない。
颯太の口グセは、「めんどくさい」だ。
「この子たち、大丈夫?」と不安に思っていたけれど、田中さんは「心配しなくて大丈夫ですよ」と、笑顔で話してくれた。
陽子は、講演で聞いた話を思い出していた。

「うちの子、自主性がないんです……」と、たくさんの親御さんがおっしゃいます。
でもね、それは当然なのです。
今の子は、自主性を育む場所がどこにもないのです。
『ドラえもん』を観ると分かりますが、遊ぶとき、子どもたちは空き地に集まります。
そして、こう言うのです。
「なにをしよう?」と。
遊びに行く場所は、空き地や裏山くらいです。
つまり、自分たちで考えて、なにもないところから遊びを生み出す必要があった。
でも、今は違います。
ゲームがあり、スマホがあります。
なにも考えなくても、全ては用意されているのです。
そうすると、自分で考える必要がありません。
ゲームを取り出して、画面の指示にしたがってボタンを押せばいいのですから。
だから、あなたのお子さんだけ自主性が無いわけではありません。
今の時代、ほとんどの子が自主性を持てていないのです。
環境が、子どもの自主性を欠落させてしまっています。
じゃあ、どうすればいいのか?
簡単です。
自主性を育ませる機会を作ってあげたらいいのです。
陽子は、田中さんが「みんな自主性がないのです」と言ってくれて、救われた気がした。
みんな同じだと思うと、ほっとしたのだ。
講演で、「こんな方法がありますよ」と教えてもらい、週末に早速実践してみた。

朝ご飯を食べているとき、葵と颯太に「今日の夕食、なにが食べたい?」と聞いた。
すると、2人は、「ハンバーグ!」「焼肉!」「お寿司!」と、それぞれ口にする。
陽子は少し考えたあと、2人に聞いてみる。
「じゃあ、ハンバーグ作ってみる?」
葵と颯太は、「え?」と顔を見合わせる。
てっきり、外食だと思っていた2人は、虚を突かれたように、固まっている。
気にせず陽子は、続ける。
「今まで、2人とも料理はほとんどしたことないよね? 葵は学校でカレーを作ったことがあるけれどね」
「せっかくの週末。颯太もサッカーの試合がなくて、家にいるし。
時間はかかってもいいから、2人でハンバーグを作ってみない?」
葵は、素直に「うん。やってみる」と言った。
颯太は、いつものように「めんどくさいなー」と言っている。
いつもの陽子なら、ここで怯んでいたかもしれない。
しかし、教わったテクニックがある。
「ああ、そっかぁ。やっぱり、颯太には難しいよねぇ。出来ると思っていたけどなぁ。そっかぁ。じゃあ、颯太はハンバーグ作るのやめておこうね」
すると、颯太は、ムスッとした顔で、「いや、ハンバーグなんて余裕やし」と言う。
陽子は、たたみかける。
「いや、いいよ。ハンバーグ作るの難しいし」
「出来るって! やるよっ!めっちゃ美味しいハンバーグ作ったるわっ」
田中さんが話していた言葉を思い出しながら、ここまで簡単なのか……と、陽子は苦笑する。
自主性がないならば、自主性を伸ばす機会を作ってあげればいいのです。
オススメは、料理です。
子どもに料理をさせてみる。
でも、子どもによっては、気が乗らない場合があります。
まぁ、そんなときはあんまり無理させる必要はありません。
本人が「やりたい!」と思うことが大切なので。
ただ、「なんとなくめんどくさい」って場合もあります。
そんなときは、うまく子どもを乗せてあげてください。
どうするか?
期待を伝えるのです。
「私は、あなたが出来ると信じていますよ」ってね。
そして、煽るのです。
「そっかぁ、出来ないよね。私の見間違えだったなぁ。あなたには、まだ難しいね」って。
言うとおりだった。
いつもは、「めんどくさい」という颯太には、キツく言うか、「もういい」と陽子は諦めていた。
しかし、期待を伝え、煽ることで、颯太は簡単にやる気になった。
「ええっと、次はどうするんだっけ……」
講演で聞いたメモを見返しながら、次にやることを確認する。

子どもがやる気になるのには、決まったルールがあります。
難しい言葉で、フロー体験いいます。
このフロー体験には、4つの要素があるのですが、まずは、“適切な難易度”を設定すること。
難しすぎると、子どもはイヤがります。
そして、簡単すぎても飽きてしまう。
ちょうど良い難しさの課題を与えてあげてください。
「そうそう。まずは、適切な難易度だったな」
葵は、一人でスーパーで買い物をすることができる。
たまに、おつかいを頼んでも、しっかり牛乳やバターを買ってきてくれる。
颯太は、ほとんどおつかいもしたことがない。
お金だけを渡し、「買い物へ行ってきなさい」では、きっと難しいだろう。
そこで、別々に課題を出すことにした。
「葵は、1,800円で4人分のカレーに使う具材を買ってきて。予算内に収まったら、なにを買ってもいいわ。ただし、買ったものは全てカレーに使うこと」
「颯太は、カレー粉を選んできて。どれがいいかは自分で決めなさい。けれど、買っていいかの最終判断はお姉ちゃんにしてもらうこと。選んだものは、お姉ちゃんに見せて、これでいいかどうか聞いてね」
2人だけでスーパーまで行かせようかとも思ったけれど、車で連れていくことにした。
今回、少し難しい課題だ。
自分たちだけでスーパーへ行くとなると、負担が大きくなる。
買い物がメインではなく、あくまでも調理するまでが今回の課題。
ヘタに体力を使うのは得策ではないと、陽子は考えた。

スーパーへ着くと、車を駐車場に止めて、2人をおろした。
1,800円が入っている財布とタブレットを渡し、あとは見守ることにした。
付いていくと、口出しをしてしまうと思ったからだ。
フロー体験で大切なことの2つ目は、“集中を妨げられない”ってことです。
つい口出しをしてしまうことありますよね?
「任せる」って言ったのに、少し失敗したら言ってしまうこと。
これは、良くありません。
子どものやる気を一気にそぐことになります。
だから、口出しはしないでください。ガマンです。
もし、ガマンできないならば、遠くから見守る。
物理的に距離をとることです。
話を聞いていて、陽子は、「私は、絶対に口出ししてしまうな」と思った。
そのため、車で送ろうと思ったとき、付いていくことは止めておこうと決めていた。
「ガンバって行ってきなさい。もし、どうしてもわからないことがあれば、帰ってきていいから。ただし、私はなにも答えないわ。代わりに、私のスマホを貸してあげる。これで調べたらいいから。お店の人や他の大人に聞くのは、もちろんオッケーよ」
陽子は、そう言って2人を送り出した。
アドバイスをしないのは、フロー体験に沿ってのことだった。
自分でコントロールしている感覚ってのが、大切です。
結局、誰かがやってくれる。
自分がガンバっても意味がないと思うと、本気でやろうと思いませんよね?
安易に、頼らせることは、子どもたちのチャレンジにならない。
“自分たちでやっている”というコントロールを奪うことになると陽子は思った。
そして、1,800円だけを渡したのも、フロー体験のルールを元にしている。
直接的なフィードバックがあるってのが、やる気に繋がります。
簡単に言うと、うまくいったかどうかがスグにわかるってことです。
4人分のカレーを作るのに必要な食材を買うと、だいたい1,600円ほどだ。
ギリギリの金額を渡したことで、子どもたちは「もしかしたら、これだけ買ったらお金が足りないかも知れない」と思うだろう。
もし、お金が足りなかったら、「うまくいかなかった」というのがスグにわかる。
予算内におさまると、とても気持ちいいに違いない。
だから、あえて余裕があまりない、中途半端な金額を陽子は子どもたちに渡した。
買い物がうまくいったとしても、帰ってからは調理がはじまる。
包丁を使うのは、まだ危ないので、野菜を切る作業は陽子がやろうと思っている。
しかし、あくまでもサポートだ。
あとの作業は、ほとんど子どもたちに任せる。
田中さんは、言っていた。
「いやぁ、料理いいですよ。ただし、まずいものになったとしてもガマンしてあげてください。良薬は口に苦しです」
果たして、上手にカレーが出来るのか不安だ。
まぁ、最悪、まずかったら、みんなで笑いながら食べたらいい。
きっと、次はもっと上手なカレーを作ることができるだろう。
お金も手間も、ほとんどかからない。
けれど、こんな機会は、きっと子どもたちに大きな成長をもたらしてくれるだろうと陽子は、確信していた。
なぜなら、スーパーへ向かうため、お金を持って車から出ていった子どもたちの顔がとても凜々しく見えたからだ。
今度は、日帰り旅行の計画を子どもに立てさせてみようと思っている。
予算だけを決めて、あとは子どもたちに任せた旅を。
「今まで、私たち、親がなんでもかんでもやり過ぎていたな……」と、陽子は反省した。
「もっと、任せてあげないと、子どもは成長しないし、自主性も身につかないな……」
けれど、落ち込むことはなかった。
「こんなことで出来るかも?」
「あれ、させてみようかしら?」
アイデアが溢れるように出てくる。
さぁ、今度は子どもたちにどんなことをチャレンジさせてみようか。
陽子は、考えただけでワクワクしてきた。
子どものことで不安に思い、悩んでいたことがなんだかずっと昔のように思える。
「あれ? 子育てってこんなにおもしろかったっけ?」
なんがか可笑しくて、つい笑ってしまった。
きっとこれからも、子育てで悩むことはあるだろう。
不安で心配になることもたくさんあると思う。
でも、なんだか陽子は、「大丈夫だ」と思えた。
子どもは、フィールドさえ用意してあげたら、勝手に育っていく。
私たち親は、ただ子どもが活躍する機会だけを作ってあげたらいいんだ。
来週、来月、来年には子どもたちはどんな表情をするようになっているのだろう。
陽子は、子どもたちの成長を想像しただけでドキドキしていた。